生前の諸葛亮(しょかつりょう)が案じた通り、ほどなく魏延(ぎえん)が反乱を起こす。南鄭(なんてい)に入った楊儀(ようぎ)と姜維(きょうい)は、諸葛亮から託された計略に従い、あえて城外へ出たうえ、魏延にあることをしてみせるよう言う。
魏延が言われた通り叫んだところ、彼のすぐ後ろにいた馬岱(ばたい)にあっけなく討ち取られた。成都(せいと)で諸葛亮の葬儀が執り行われた後、その遺言により、遺骸(いがい)は漢中(かんちゅう)の定軍山(ていぐんざん)に葬られた。
第311話の展開とポイント
(01)引き揚げ途中の蜀軍
旌旗(せいき)色なく、人馬声なく、蜀山の羊腸たる道を哀々と行くものは、五丈原頭(ごじょうげんとう)の恨みを霊車(霊柩車〈れいきゅうしゃ〉)に駕(が)して、むなしく成都へ帰る蜀軍の列だった。
★原文「施旗色なく」だが、ここは「旌旗色なく」としておく。なお、講談社版(新装版)やそれより古い講談社版では、「旌旗色なく」となっていた。
「行く手に煙が望まれる。この山中に不審なことだ。誰か見てこい」
楊儀と姜維は物見を放ち、しばらく行軍を見合わせた。すでに道は有名な桟道の険阻に近づいていたのである。
一報、二報。偵察隊は次々に帰ってきた。この先の桟道を焼き払い、道を阻めている一軍があると言い、それは魏延に違いないとのこと。
文吏である楊儀が色を失うと、姜維が言った。
「心配はない。日数はかかるが、槎山(さざん)の間道を通れば、桟道によらずに南谷(なんこく)の後ろへ出られる」
★『三国志演義(7)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)の訳者注によると、「『三国志』(蜀書・魏延伝)に『楊儀等槎山通道、昼夜兼行』というが、槎山通道はもともと『山の木を切り開いて道を通す』という意味である」という。
険阻や隘路(あいろ)を迂回(うかい)して、全軍は辛くも南谷をふさいでいる魏延軍の後ろへ出た。
途上から楊儀は、この顚末(てんまつ)を成都へ報ずる。ところがその前に、魏延からも上表が届いていた。
(02)成都
「楊儀、姜維の徒が、丞相(じょうしょう。諸葛亮)の薨(こう)ぜられるや、たちまち兵権を横奪し、乱を企てております。臣は彼らを討つ所存です」
これが魏延からの上奏であり、後から届いた楊儀の上表には、それとはまったく反対の実情が訴えられてきた。
諸葛亮の訃が報ぜられると、成都宮の内外は哀号の声と悲愁に閉じられ、劉禅(りゅうぜん)も皇后も日夜悲しみ嘆いている。
★皇后については先の第259話(02)を参照。
そのような折なので、この変に対しても、いかに裁いてよいかと判断に迷った。
すると蔣琬(しょうえん)が、こう言って慰める。
「丞相は遠く出られる日より、密かに魏延の叛骨(はんこつ)は憂いの種としておられました。平素そのご活眼ある丞相のことゆえ、必ずや死後の慮りをなされ、何らかの策を遺して逝かれたに違いありません。しばらく次の知らせをお待ちあそばしませ」
蔣琬の言はさすがによく事態を見、諸葛亮の遺志を知るものだった。
★井波『三国志演義(7)』(第105回)では、この意見を述べたのは蔣琬ではなく呉太后(ごたいこう)。
(03)南谷(褒谷〈ほうこく〉)
魏延は数千の手勢をもって桟道を焼き落とし、南谷を隔てて構えていた。だが、相手が間道づたいに後ろへ迫っていたことに気づかなかった。必然、彼の盛んなる覇気叛骨も一敗地にまみれ去る。
魏延の手勢の大半は、千尋の谷底へ追い落としを食らい、残余の兵を抱えて命からがら逃げ延びた。
(04)南鄭
魏延は付き従っていた馬岱に励まされ、兵備を改めて南鄭への急襲をもくろむ。
南谷を渡り、魏延に一痛打を加え去った楊儀と姜維らは、先を急いで諸葛亮の霊車を南鄭城の内に安んずる。そして殿軍(しんがり)が着くのを待ち、魏延の動きをうかがう。
魏延の一軍がまっしぐらに攻めてくると聞くと、姜維は楊儀を戒めた。
「小勢とはいえ、蜀中一の勇猛。加うるに、馬岱も彼を助けておる。油断はなりませぬぞ」
楊儀の胸には、このときとばかり、思い出されたものがある。諸葛亮から臨終の折に授けられ、後日、魏延に変あるときに見よと遺言されていた、あの錦の囊(ふくろ)だった。
★諸葛亮が楊儀に錦の囊を授けたことについては、先の第309話(02)を参照。
囊の中には一書が納められていた。諸葛亮の遺筆たるは言うまでもない。封の表には、「魏延、叛を現し、その逆を伐(う)つ日までは、これを開いて秘力を散ずるなかれ」としたためてある。
楊儀と姜維は囊中(のうちゅう)の遺計が教えるところに従って、急に作戦を変更した。
すなわち閉じたる城門を開け放ち、姜維は銀鎧(ぎんがい)金鞍(きんあん)という武者ぶりに、丹槍(たんそう)の長きを横に抱え、手兵2千に鼕々(とうとう。鼓を打ち鳴らす音)と陣歌を上げさせて城外へ出る。
魏延は遥かにそれを見、同じく雷鼓して陣形を詰め寄せてきた。やがて漆黒の馬上に朱鎧緑帯し、龍牙刀を引っ提げて躍り出たる者こそ魏延だった。
味方であった間は、さまでとも思えなかったが、こうして敵に回してみると、なにさま魁偉(かいい)な猛勇に違いない。姜維も並ならぬ大敵と知って、心中に諸葛亮の霊を念じながら叫んだ。
「丞相の身もいまだ冷えぬうちに、乱を企むほどの悪党は蜀にはいないはずだ。日ごろを悔いて、自ら首を霊車に供え奉りに来たか!」
魏延は唾して軽くあしらい、こう言った。
「まず楊儀を出せ。楊儀から先に片づけ、しかる後に貴様の考え次第では、また相手にもなってやろう」
すると後陣の中から、たちまち楊儀が馬を進めて言う。
「魏延! 野望を持つのもいいが、身の程を量って持て。一斗の瓶(かめ)へ百斛(ひゃっこく)の水を入れようと考える男があれば、それは馬鹿者だろう」
さらに楊儀は続ける。
「『誰が俺を殺し得んや』と三度叫んだら、漢中はそっくり汝(なんじ)に献じてくれる。言えまい。それほどの自信は叫べまい」
魏延は何度でも言ってやろうと、馬上に反り返って大音を繰り返す。
「誰が俺を殺し得んや。誰が俺を殺し得んや。おるなら出てこいっ!」
そのとき、彼のすぐ後ろで大喝が聞こえた。
「ここにいるのを知らぬか。それっ、この通り殺してやる!」
魏延が振り向いた頭上から、戛然(かつぜん)、一閃(いっせん)の白刃が下りてくる。どうかわす間も受ける間もない。首は血煙を噴いてすっ飛んだ。ワアッと敵味方とも囃(はや)す。
血刀の滴を振りつつ、すぐに楊儀と姜維の前に寄ってきたのは馬岱。諸葛亮の生前に、馬岱は秘策を受けていた。魏延の反意は部下の本心ではなかったので、兵はみな彼とともに帰順する。
★井波『三国志演義(7)』(第104回)では、諸葛亮が馬岱に秘策を授けたことが書かれていた。しかし吉川『三国志』では、先の第309話(02)でこのことに触れておらず、いくらかわかりにくさが感じられる。
(05)成都
かくて、諸葛亮の霊車は無事に成都へ着く。四川の奥地はすでに冬だった。蜀宮は雲低く垂れて涙恨を閉ざし、劉禅以下、文武百官が喪服して出迎えた。
諸葛亮の遺骸は漢中の定軍山に葬られる。宮中の喪儀や諸民の弔祭は大変なものだったが、定軍山の塚は故人の遺言により、極めて狭い墓域に限られた。
石棺には時服(普段着)一着を入れたのみで、当時の慣例としては質素極まるものだったという。
「身は死すともなお漢中を守り、毅魄(きはく。強くしっかりとした魂)は千載(1千年)に中原(ちゅうげん。黄河中流域)を定めん」となす、これが諸葛亮の遺志であったに違いない。
蜀朝は諡(おくりな)して、忠武侯という。
その廟中(びょうちゅう)には、後の世まで一石琴を伝えていた。軍中つねに愛弾していた故人の遺物(かたみ)である。一搔(いっそう)すれば琴韻(琴の音)清越(澄んでいて高い)。
多年の干戈(かんか)剣戟(けんげき)の裡(うち)にも、なお素朴なる洗心と雅懐(風流な心持ち)を心がけていた丞相その人の面影を偲(しの)ぶに足ると言われている。
渺茫(びょうぼう)1,700年。民国(中華民国の略称)今日(こんにち)の健児たちに語を寄せていう者、あにひとり定軍山上の一琴のみならんやである。
「松ニ古今ノ色無シ」
相響き相奏で、釈然と覚めきたれば、古往今来すべて一色。この輪廻(りんね)と春秋の外ではあり得ない。 (『三国志』完)
管理人「かぶらがわ」より
諸葛亮から秘策を授けられていた馬岱に、あっさりと斬られてしまう魏延。史実でも、楊儀の命を受けた馬岱が、魏延を追撃して斬り殺したとありました。
魏延は史実でも、『三国志演義』でも、報われない最期だったと思います。数々の戦功を立てて相当な地位まで昇りながらも、イマイチ溶け込めていない印象が残りました。
また魏延については、当初から人相にケチをつけられたり、いかにも謀反を起こすような人物として描かれていましたが――。無理やり悪役に仕立てられた印象も受けました。

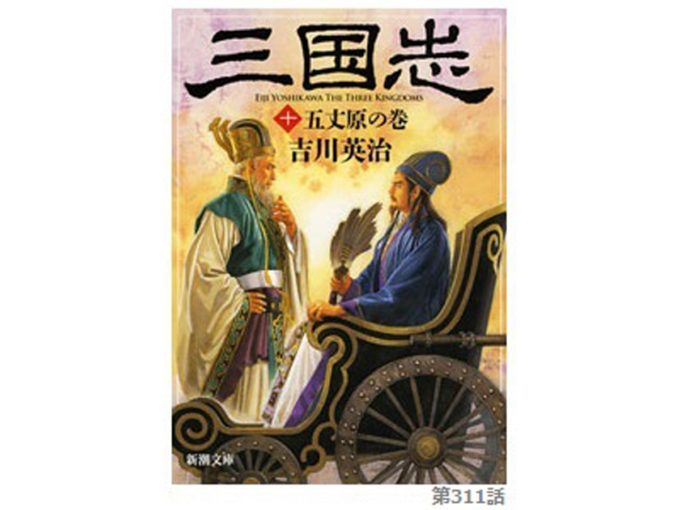
















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます