【姓名】 趙儼(ちょうげん) 【あざな】 伯然(はくぜん)
【原籍】 潁川郡(えいせんぐん)陽翟県(ようてきけん)
【生没】 171~245年(75歳)
【吉川】 第206話で初登場。
【演義】 第066回で初登場。
【正史】 登場人物。『魏書・趙儼伝』あり。
卓越した調整能力で名将をまとめる
父母ともに不詳。息子の趙亭(ちょうてい)は跡継ぎ。
趙儼は動乱を避け、同郡の杜襲(としゅう)や繁欽(はんきん)とともに荊州(けいしゅう)へ赴き、ひとつの家で一緒に暮らした。
後に趙儼らは、さらに南方の長沙(ちょうさ)へ移る。
196年、曹操(そうそう)が天子(献帝)を迎えて許(きょ)に都を置くと、趙儼は繁欽に言った。
「鎮東将軍(ちんとうしょうぐん。曹操)は時運に応じ、一世に名を上げられたからには、よく華夏(かか。中国)を正してお救いになるに違いない。私は誰に帰服すればよいのかわかったぞ」
翌197年、趙儼が老若の者を助けながら許に着くと、曹操は彼を朗陵県長(ろうりょうけんちょう)に取り立てる。
朗陵県には勢力を笠に着る者が多くいて、思いのまま振る舞っていた。
趙儼は最もひどい者を逮捕して取り調べ、死罪に該当すると判断し投獄した後、陽安郡(ようあんぐん)の役所へ上申したうえで釈放。以後、趙儼の権威や恩愛が明らかとなる。
このころ袁紹(えんしょう)が軍勢をひきいて南方へ侵入し、使者を遣って豫州(よしゅう)の諸郡を味方に付けようと誘う。それらの多くは誘いを受けたが、陽安郡だけは動揺しなかった。
陽安都尉(ようあんとい)の李通(りとう)は急いで戸調(こちょう。家ごとに割り当てられた税)を取り立て、集めた綿や絹を許に送って忠心を示そうとする。
趙儼は李通を説き、近隣の諸郡が背く中で味方として懐いているわが郡の民から、さらに綿や絹を取り立てるべきではないと述べる。
そして荀彧(じゅんいく)に手紙を送り、郡民が二心を抱いていないことを説明し、取り立てた綿と絹を民に返したいと願い出た。
そのうち荀彧を通じて曹操の通達が届き、綿と絹を民に返すことが認められる。みな歓喜し、郡内も安定した。
後に趙儼は中央へ入り、司空掾属主簿(しくうえんぞくしゅぼ)となる。
★曹操が司空を務めていた期間は196~208年。
当時、于禁(うきん)が潁陰(えいいん)に、楽進(がくしん)が陽翟に、張遼(ちょうりょう)が長社(ちょうしゃ)に、それぞれ駐屯しており、気力に任せた勝手な振る舞いが多く、互いに協調しようとしなかった。
そこで趙儼が3人の軍の参軍(さんぐん)を兼ねることになり、事あるごとに教え諭す。その結果、于禁・楽進・張遼は親しく付き合うようになったという。
208年、曹操が荊州討伐に乗り出すと、趙儼は章陵太守(しょうりょうたいしゅ)を兼任し、都督護軍(ととくごぐん)として于禁・張遼・張郃(ちょうこう)・朱霊(しゅれい)・李典(りてん)・路招(ろしょう)・馮楷(ふうかい)の7軍を統括する。
その後、趙儼は丞相主簿(じょうしょうしゅぼ)を経て扶風太守(ふふうたいしゅ)に昇進した。
★曹操が丞相を務めていた期間は208~220年。
211年、曹操は渭南(いなん)で韓遂(かんすい)と馬超(ばちょう)の軍を大破する。
捕虜にした5千の兵は、平難将軍(へいなんしょうぐん)の殷署(いんしょ)らに取り仕切らせた。そして趙儼が関中護軍(かんちゅうごぐん)となり、これらの諸軍を統括した。
たびたび羌族(きょうぞく)の来攻による被害が出たため、趙儼は殷署らをひきいて新平(しんぺい)まで追撃し、大いに討ち破る。
また、屯田民として寄留した呂並(りょへい)が将軍を自称し、徒党を集めて陳倉(ちんそう)に立て籠もると、再び趙儼は殷署らをひきいて攻撃し、たちまち壊滅させた。
その後、漢中(かんちゅう)の守備を助けるため1,200の兵を送れとの命令が届き、集まった兵たちを殷署が指揮して行くことになる。急に家族と離れることになり、兵はみな憂鬱(ゆううつ)な様子だった。
趙儼は変事が起こるのを心配し、彼らを斜谷口(やこくこう)まで追いかけて激励する。併せて殷署に注意を促した。
引き返した趙儼は、雍州刺史(ようしゅうしし)の張既(ちょうき)の官舎に泊めてもらう。殷署らが40里進むと兵が反乱を起こし、殷署の安否もわからなくなった。
このとき趙儼がひきいていた歩騎150人は、みな反乱を起こした兵と同じ部隊に属しており、姻戚関係のある者もいた。
彼らは漢中に向かった兵が反乱を起こしたと聞くと、驚いて武装を整え、落ち着かない様子を見せる。
このような状況で趙儼が帰途に就こうとしたため、張既らは、本営も騒乱になっているだろうから、確かな情報を待つべきだと主張。
しかし趙儼は、速やかに本営の兵を慰撫(いぶ)したほうがよいと考えたので出発する。
趙儼は30里進んで休憩し、付き従う者たちに事の成否をよく教え諭す。みな二心を抱かないと言い、覚悟を決めた。
さらに進んで軍営に着くと、反乱者と手を結んだ800余人を召し出して取り調べ、主導者以外の罪は問わなかった。
219年、樊(はん)にあった征南将軍(せいなんしょうぐん)の曹仁(そうじん)が、劉備(りゅうび)配下の関羽(かんう)に包囲される。
趙儼は議郎(ぎろう)のまま曹仁の軍事に参画することになり、南方へ行き、平寇将軍(へいこうしょうぐん)の徐晃(じょこう)とともに進軍。
こうして樊に到着したものの、ほかの援軍は来ておらず、すでに関羽の包囲陣は完成していた。
徐晃の兵だけでは敵の包囲を解けないのに、味方の諸将は速やかに救援するよう厳しく責め立てる。
そこで趙儼が現状を分析してみせ、今は敵の包囲陣に迫り、密かに曹仁と連絡を取って救援があることを知らせ、樊城の将兵を奮い立たせるべきだと説く。
やがて北方の援軍も到着したので、協力して関羽軍を退ける。
それでもなお関羽の船団が沔水(べんすい)を占拠しており、襄陽(じょうよう)との連絡は断ち切られたままだった。
このとき孫権(そんけん)が関羽の輜重(しちょう)を襲撃して奪ったため、関羽は南へ引き揚げる。
曹仁が諸将を集めて軍議を開くと、みな追撃して関羽を捕らえるべきだと述べた。
ただ趙儼は、すでに孤立している関羽を、孫権の目の上の瘤(こぶ)として残しておくほうがよいと主張する。
曹仁は趙儼の意見を容れて戦闘態勢を解いたが、ほどなく曹操からも、関羽を追撃するなという急ぎの命令が届いた。
220年、曹丕(そうひ)が魏王(ぎおう)を継ぐと、趙儼は侍中(じちゅう)となる。
しばらくして駙馬都尉(ふばとい)に任ぜられ、河東太守(かとうたいしゅ)や典農中郎将(てんのうちゅうろうしょう)を務めた。
222年、趙儼は関内侯(かんだいこう)に封ぜられる。
この年、孫権軍が国境地帯に侵入すると、征東大将軍(せいとうだいしょうぐん)の曹休(そうきゅう)が5州の軍勢をひきいて防いだが、趙儼は召されて軍師を務めた。
孫権軍の撤退後に魏軍も帰還。
趙儼は宜土亭侯(ぎどていこう)に爵位が進み、度支中郎将(たくしちゅうろうしょう)に転ずる。後に尚書(しょうしょ)に昇進した。
224年、曹丕の孫権討伐に付き従って広陵(こうりょう)まで行き、その地に留まり征東軍師を務めた。
226年、曹叡(そうえい)が帝位を継ぐと、趙儼は都郷侯に爵位が進み、封邑(ほうゆう)600戸を賜る。
そして監荊州諸軍事(かんけいしゅうしょぐんじ)・仮節(かせつ)となったが、このときは病気のために赴任できず、再び尚書に任ぜられた。
後に地方へ出て監豫州諸軍事となり、大司馬軍師(だいしばぐんし)に転じ、中央へ戻って大司農(だいしのう)となった。
239年、曹芳(そうほう)が帝位を継ぐと、趙儼は監雍涼諸軍事(かんようりょうしょぐんじ)・仮節に任ぜられ、征蜀将軍(せいしょくしょうぐん)に転ずる。
次いで征西将軍(せいせいしょうぐん)・都督雍涼諸軍事に移った。
243年、趙儼は老齢と病気を理由に帰還を希望し、召し還されて驃騎将軍(ひょうきしょうぐん)となる。
245年2月、司空に昇進。
同年6月、趙儼が75歳で死去すると穆侯(ぼくこう)と諡(おくりな)され、息子の趙亭が跡を継いだ。
管理人「かぶらがわ」より
本伝によると、趙儼は同郡の辛毗(しんぴ)・陳羣(ちんぐん)・杜襲とともに名を知られ、「辛陳杜趙」と称されていました。こうした名声を背景に、長く諸将の監督にあたっています。
趙儼自身は戦場に出て敵とやいばを交えることは少なかったのでしょうが、腕自慢の猛将たちの間をうまく調整する能力は、曹操以来ずっと重宝され続けたのですね。
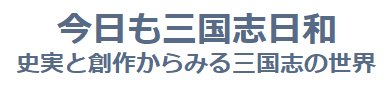














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます