【姓名】 曹拠(そうきょ) 【あざな】 ?
【原籍】 沛国(はいこく)譙県(しょうけん)
【生没】 ?~?年(?歳)
【吉川】 登場せず。
【演義】 第109回で初登場。
【正史】 登場人物。『魏書・彭城王拠伝(ほうじょうおうきょでん)』あり。
魏の曹操(そうそう)の息子で曹丕(そうひ)の異母弟、彭城王
父は曹操、母は環氏(かんし)。同母兄には曹沖(そうちゅう)、同母弟には曹宇(そうう)がいる。
息子の曹琮(そうそう)は曹沖の跡継ぎとなり、曹範(そうはん)および曹闡(そうせん)は曹子整(そうしせい)の跡継ぎとなった。
曹拠は211年に范陽侯(はんようこう)に封ぜられ(封邑〈ほうゆう〉は5千戸)、217年に宛侯(えんこう)に移封された。
221年には宛公に爵位が進み、222年に章陵王(しょうりょうおう)、同年に義陽王(ぎようおう)に移封された。
その後は彭城王や済陰王(せいいんおう)を経て、224年に定陶県王(ていとうけんおう)に移封。232年に諸王の封邑が改められ、再び彭城王に移封された。
237年、中尚方(ちゅうしょうほう。宮中で使う器物を製作する役所)に人を遣り、禁止されている器物を作らせた罪により1県2千戸を削られる。しかし、239年には削られた封邑が返された。
正元(せいげん)年間(254~256年)から景元(けいげん)年間(260~264年)にたびたび加増され、4,600戸となった。
管理人「かぶらがわ」より
237年に封邑が削られた件については、本伝の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く王沈(おうしん)の『魏書』に、曹叡(そうえい)の詔(みことのり)が載せられています。
罪状と処分の内容だけを伝えるのではなく、『尚書』を引用して行いを慎むよう諭していたり、当時は何かと煩雑だったんだなと……。
一方で、こうするからこそ詔に重みが出るというか、味わいがあるなとも感じます。
また『三国志』(魏書・斉王紀)の裴松之注に引く魚豢(ぎょかん)の『魏略』には、「254年に司馬師(しばし)が曹芳(そうほう)の廃位を企てた際、次の皇帝として、彭城王だった曹拠を擁立しようとした」とあります。
しかし郭太后(かくたいこう。明元郭皇后)が難色を示したため、結局は高貴郷公の曹髦(そうぼう)が迎えられました。
曹拠は曹丕の異母弟ですから、曹丕の息子である曹叡の正室だった郭太后から見れば、叔父にあたる曹拠が帝位に即くと、確かに具合が悪そうですよね。
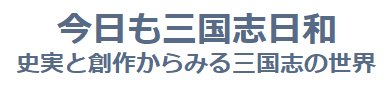














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます