長安(ちょうあん)から脱出した献帝が、生き残った百官とともに荒れ果てた洛陽(らくよう)への還幸を果たす。
この窮状を救ってくれたのは、真っ先に駆けつけてきた曹操(そうそう)だった。
第13話の展開とポイント
(01)兗州(えんしゅう)
荀彧(じゅんいく)が曹仁(そうじん)に詔書の内容を教える。
★ここで荀彧に詔書の内容を語らせる形式で、曹操が呂布(りょふ)と戦っていた間の長安の動きを説明していた。
董卓(とうたく)の部将だった李傕(りかく)と郭汜(かくし)が天子(献帝)をさらい、その後で仲間割れを起こした。そして、天子と百官は人質として李傕と郭汜の双方に翻弄され、長安は廃虚と化し、水や食糧も枯渇したと。
天子には安集将軍(あんしゅうしょうぐん)の董承(とうしょう)が護衛に付き、長安から逃れて東の洛陽を目指し、その道中で詔(みことのり)を書き、諸侯に急ぎ助けを求められたのだとも。
★また、ここで荀彧が「長安から洛陽へはボウトウ山(?)を通らねばならない。この山は兗州から500里足らず……」とも言っていた。後の第23話(04)で出てくる芒碭山(ぼうとうざん)のことではないと思うが、よくわからなかった。
(02)冀州(きしゅう)
袁紹(えんしょう)のもとにも献帝から助けを求める詔が届く。許攸(きょゆう)は天子を招くよう勧めるが、田豊(でんぽう)は反対する。
袁紹は詔に応じず、献帝を放っておくことにし、青州(せいしゅう)と幽州(ゆうしゅう)の攻略を優先する。
(03)ボウトウ山
曹操自ら天子の取り込みに動き、ボウトウ山を通過する。
(04)洛陽
献帝が百官とともに、荒れ果てた洛陽に還幸する。
★ここで献帝役の役者が子役から入れ替わり、青年バージョンとして初登場。
ほどなく曹操の援軍が到着。曹操は献帝に拝謁して鶏の汁物を献上し、百官にも振る舞う。
(05)洛陽 長楽宮(ちょうらくきゅう)
曹操が献帝に閲兵を求める。献帝はこの場で曹操を大将軍(だいしょうぐん)に任じたうえ、武平侯(ぶへいこう)に封ずる。
曹操は武力を背景として、献帝に許(きょ)への遷都を迫る。やむなく献帝も認め、許への遷都を宣言する。
(06)許へ向かう曹操
曹操が荀彧に皇帝の名で詔を作らせ、許への遷都を広く知らせただけでなく、各地の諸侯、刺史(しし)、太守(たいしゅ)、将軍らに参内を命ずる。また、許を許都(きょと)と改めたうえ、「建安(けんあん)」と改元して大赦を行う。
(07)西暦196年 許県遷都
献帝が曹操の上奏を承認し、袁紹を大将軍・ブテイ侯(?)に、袁術(えんじゅつ)を驃騎将軍(ひょうきしょうぐん)・チュウギ侯(?)に、劉表(りゅうひょう)を前将軍(ぜんしょうぐん)・トウアン侯(東安侯?)に、公孫瓚(こうそんさん)を後将軍(こうしょうぐん)・セイアン侯(西安侯?)に、それぞれ封ずる。
一方で曹操は、自身の恩典を特に求めなかった。
★先の(05)で曹操が大将軍に任ぜられたこととの兼ね合いがわからなかった。袁紹に大将軍を譲ったのであれば、その点に触れておくべきだったと思う。
★献帝の冠の玉飾り、子ども時代には9旒(りゅう)しかなくてテキトーだったが、ここでは12旒に増えたように見える。天子は12旒が正しい。
★なお、ここで出てきた爵位はいずれもよくわからなかった。
(08)冀州
袁紹のもとに献帝の詔が届く。袁紹は大将軍・ブテイ侯となり、冀州と青州に加えて幷州(へいしゅう)の統治も認められる。
袁紹は皆に、秋の収穫後に15万の兵で幽州と幷州を攻め、そのあと曹操討伐の準備を整えるよう命ずる。
(09)許都
曹操は荀彧の献策した駆虎吞狼(くこどんろう)の計を用い、献帝の詔を使って劉備(りゅうび)と袁術が戦うよう仕向ける。
(10)徐州(じょしゅう)
劉備のもとに献帝の詔が届く。劉備は正式に徐州牧(じょしゅうぼく)に任ぜられたうえ、車騎将軍(しゃきしょうぐん)・ブギ侯(?)に封ぜられる。この際、勅使は劉備に別の密書も手渡す。
★ここで官爵を授けられる前、劉備は偏将軍(へんしょうぐん)だったことになっていた。いつ誰から任官されたのかわからず。
★この場面では勅使が出入り口から入ってきて、そのままの向きで劉備への詔を読み上げていた。勅使の立つ側が高くなってはいたが、州牧の席を背にして読み上げる形にしたほうがよかったと思う。
管理人「かぶらがわ」より
袁紹は荀彧のような参謀がいなかったのが痛いですよね。正史『三国志』によれば、荀彧は袁紹に仕えたことがあり、ほどなく見限って曹操に鞍(くら)替えしています。
まだまだ献帝の利用価値は高い。許への遷都により、曹操は覇者としての地位を固めることになりました。ほかの諸侯は重要な判断をミスった感じ。
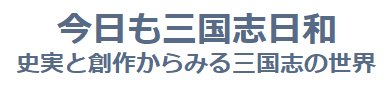
















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます