柴桑(さいそう)に到着した魯粛(ろしゅく)はさっそく登城するが、府堂では曹操(そうそう)から送られた檄文(げきぶん)への対応を巡る協議が続いていた。
その翌日、城内の一閣に招かれた諸葛亮(しょかつりょう)は、集まった呉の重臣たちを次々と論破していく。
第146話の展開とポイント
(01)柴桑
諸葛亮と魯粛を乗せた船は、やがて長江から潯陽江(じんようこう)の入り江に入る。そこからは陸路、西南に鄱陽湖(はようこ)を見ながら騎旅を進めた。
そして柴桑の街に着くと、魯粛はひとまず諸葛亮を客館へ案内し、自身はただちに登城する。府堂では文武百官が集まり大会議中だった。
孫権(そんけん)は魯粛を呼び入れて席を与えると、曹操から送られた檄文(げきぶん)を見せた。さらに魯粛は、満座の大半は戦わないほうがいいという意見に傾いていると聞く。
張昭(ちょうしょう)ほかの重臣たちは、みな口をそろえて不戦論を唱える。孫権はやや疲れを見せ、「衣服を更(か)えてまた聴こう」と席を立ち、殿裏へ隠れた。衣を更えるとは休息の意味である。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「更衣は着替えという意味から転じて、高貴な者が厠(かわや)へ行くこと」だという。
魯粛はひとりだけついていく。孫権が意中を察して親しく尋ねると、魯粛は勃然と主戦的な気を吐いた。みな自己の保身と安穏を先に考え、ご主君のお立場も国恥も大事と考えていないと。
若い孫権はこの言葉に動かされる。消極論には迷いを抱くが、積極論には本能的にも血が高鳴った。
ここで魯粛は、江夏(こうか)から諸葛亮を連れてきたことを話し、親しく意見を聴くよう勧める。そこで孫権はこの日の評議を一応取りやめ、明日また改めて参集するよう諸員に言い渡す。
翌日、柴桑城の一閣には呉の知囊(ちのう)と英武とが20余人も居並んでいた。諸葛亮は魯粛に導かれてくると、居並ぶ人々にいちいち名を問い、いちいち礼を施してから、静かに客位の席へ着く。
一同こもごもの挨拶が済むと、まず張昭が皮肉な質問をした。
劉備(りゅうび)どのから三顧の礼をもって迎えられ、魚が水を得たようなものだとまで喜ばれたあなたなのに、その後は荊州(けいしゅう)も取らず、新野(しんや)も追われ、惨めな敗亡を遂げられたのは、いったいどういうわけなのかと。
諸葛亮は、新野という僻地(へきち)に兵も兵糧も乏しい中、曹操の大軍の強襲を受けながらも、白河(はくが)での水攻めや博望(はくぼう)での火攻めなど、決して醜い壊走はしていないと反論。
★白河での水攻めについては先の第140話(05)を参照。
★博望での火攻めについては先の第138話(03)を参照。
当陽(とうよう)では一時、惨めな離散を体験したものの、これも主君を慕う数万の百姓老幼が陸続とついてきたため、ついに江陵(こうりょう)へ入ることができなかった結果であり、それもまた主君の仁愛を証するもので、恥なき敗戦とは意義が違うのだと説く。
これを聴いた張昭は沈黙。さしもの彼も、心を取りひしがれたような面持ちに見えた。
続いて虞翻(ぐほん)が立ち上がり、曹操の大軍への対策を尋ねる。
諸葛亮は、曹操は100万と号しているが、実数は7、80万というところだろうと言い、それも袁紹(えんしょう)や劉表(りゅうひょう)の兵を併せたもので、いわゆる烏合(うごう)の衆。何を恐れるほどなものがあろうかと説く。
虞翻は劉備の惨敗ぶりを持ち出して大言を笑うが、諸葛亮は呉の国政に携わる重臣たちが、主君に降伏を勧めている惰弱、卑劣ぶりを非難。
虞翻が口を閉じると、代わって歩隲(ほしつ。歩騭)が立つ。
そして、蘇秦(そしん)や張儀(ちょうぎ)の詭弁(きべん)を学び、三寸不爛(ふらん)の舌を振るって遊説に来たのかと問う。
★新潮文庫の註解によると「(蘇秦と張儀は)戦国時代に合従連衡(がっしょうれんこう。六国が同盟し、大国の秦に対抗すること)の外交策を説いた縦横家(合従や連衡を説いた人々)」だという。
諸葛亮は、蘇秦と張儀は弁舌のみの人物だったわけではないと言い、曹操の宣伝や威嚇(いかく)に乗ぜられ、たちまち主君に降伏を勧めるような自己の小才をもって推し量り、「蘇秦、張儀の類い」などと軽々しく口にする者には、まじめに答える価値もないと一蹴する。
歩隲が顔を赤らめてしまうと、薛綜(せつそう)が唐突に問うた。
「曹操とは何者か?」
★薛綜は、先の第135話(01)であざなの敬文(けいぶん)として既出。
諸葛亮が間髪を入れず(少しの隙間も置かず。正しくは「間、髪を入れず」)に「漢室の賊臣」と答えると、薛綜は、その解釈は根本的に誤謬(ごびゅう)であると指摘。
いま漢室の政命は尽き、曹操の実力は天下の3分の2を占めるに至り、民心も彼に帰せんとしている。これを賊と言うなら、舜(しゅん)も賊、禹(う)も賊、武王、秦王、高祖、ことごとく賊ではないかと。
★新潮文庫の註解によると「(武王は)周王朝の始祖。殷を滅ぼした」という。
★同じく新潮文庫の註解によると「(秦王は)秦の始祖である始皇帝。王とするのは貶称(へんしょう)。六国を滅ぼした」という。
★同じく新潮文庫の註解によると「(高祖は)漢帝国の始祖である劉邦(りゅうほう)のこと。秦を滅ぼした」という。
諸葛亮は薛綜を叱り、「ご辺(きみ)の言は、父母もなく主君もない人間でなければ言えないことだ」と評する。「人と生まれながら、忠孝の本(もと)をわきまえぬはずはあるまい」とも。
そのうえ「貴下(あなた)は主家が衰えたら、曹操のようにたちまち主君の孫権をないがしろになされるか?」と問い返した。
代わって陸績(りくせき)が論じかける。
相国(しょうこく)の曹参(そうさん)の後胤(こういん)で、漢朝累代の臣である曹操と、中山靖王(ちゅうざんせいおう。劉勝〈りゅうしょう〉)の末裔(まつえい)と称しながら、その生い立ちは蓆(むしろ)を織り履(くつ)を商っていた劉備。これを比べるに、いずれを珠とし、いずれを瓦とするか、おのずから明白ではないかと。
★陸績は、先の第135話(01)であざなの公紀(こうき)として既出。
諸葛亮は、以前に陸績が袁術(えんじゅつ)の席上で橘(タチバナ。柑子〈コウジ〉の古い名前。蜜柑〈ミカン〉の類い)を懐に入れたという話に触れた後、至徳をたたえられた周の文王や、武王を諫めた伯夷(はくい)と叔斉(しゅくせい)の態度を論じ、今の曹操の行いは、家門が高ければ高いほど、その罪は深大なのだと説く。
★新潮文庫の註解によると「幼い陸績が袁術の席で、母への孝のため蜜柑を持ち帰った話は『二十四孝』に記される」という。
主君の劉備については、大漢400年の治乱の間には必然、多くの門葉や支族も僻地に流寓(りゅうぐう)されており、あえなく農田に血液(血筋)を隠しておられたことが何の歴史の恥になるだろうかと述べ、時が来たって草莽(そうもう)の内より現れ、泥土を去り珠金の質を世に挙げられたことは、当然の帰趨(きすう)だとする。
それなのに、履を綯(な)っていたからと卑しみ、蓆を織っていたからと蔑むなど、そのような目をもって世を見、人生を見、よくも一国の政事(まつりごと)に参ぜられたものではあると、陸績を非難した。
陸績が胸ふさがり二の句も継げないでいると、代わって厳畯(げんしゅん)が立つ。
★厳畯は、先の第135話(01)であざなの曼才(まんさい)として既出。
厳畯は、諸葛亮の弁舌をたたえながらも揶揄的(やゆてき)に言った。
「そも、きみはいかなる経典によってそのような博識になったのか。ひとつその蘊蓄(うんちく)ある学問を聴こうではないか」
諸葛亮は一喝して答える。
「末梢(まっしょう)を論じ枝葉をあげつらい、章句に拘泥して日を暮らすのは世の腐れ儒者の仕業である。何で国を興し民を安んずる大策を知ろう」
すると程秉(ていへい)は、「では、文は天下を治むるに無用のものと言われるか?」と反駁(はんばく)。
★程秉は、先の第135話(01)であざなの徳枢(とくすう)として既出。
諸葛亮は早吞み込みをしないようにと言い、学文には小人の弄文と、君子の文業とがあると答えた。
満座声なく、鳴りを潜めてしまったので、ここで諸葛亮が一問してみる。
「最前からおのおのの声音を通してこの国の学問を察するに、その低調さに憫然(びんぜん)たるものを覚える。この観察にご不平はおありか?」
それに対し、もう誰も立って答える者がなかったとき、沓音(くつおと)高く入ってきた者があった。
管理人「かぶらがわ」より
単身で呉へ乗り込み、まさに三寸不爛の舌を振るう諸葛亮。こういった問答はまとめるのも大変でした。
もしこの場に同席していたら、諸葛亮に何か言えると思います? よくよく考えて発言しないと、ただただ己の無知ぶりをさらけ出すことになるのでしょうね……。

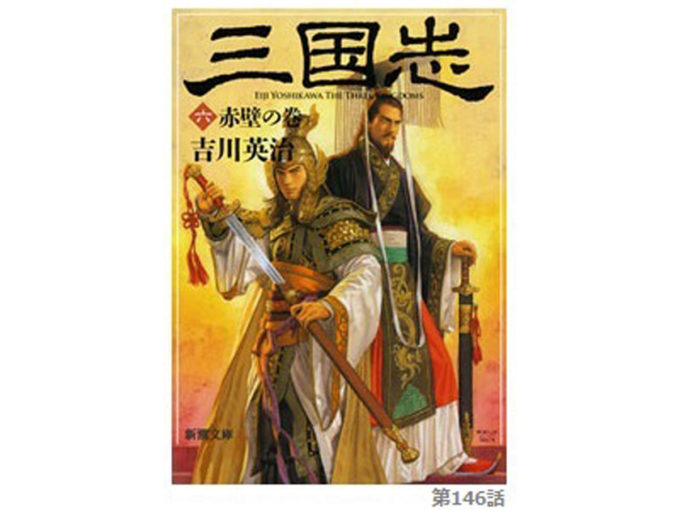
















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます