天蕩山(てんとうざん)を奪われた張郃(ちょうこう)と夏侯尚(かこうしょう)は、定軍山(ていぐんざん)まで逃げ延び、夏侯淵(かこうえん)に味方の劣勢を伝える。
夏侯淵の報告を受けた南鄭(なんてい)の曹洪(そうこう)から急報がもたらされると、曹操(そうそう)は自ら大軍をひきいて都(鄴都〈ぎょうと〉)を発つ。そして道中、藍田(らんでん)で蔡邕(さいよう)の山荘に立ち寄った。
第220話の展開とポイント
(01)葭萌関(かぼうかん)
「ご辺(きみ)はすでに張郃に勝ちたれど、夏侯淵には及ぶまい」
思いがけぬ諸葛亮(しょかつりょう)の言葉に、黄忠(こうちゅう)の憤懣(ふんまん)はやるかたなく、色をなして迫った。
「むかし廉頗(れんぱ)は年80に及んで、なお米1斗と肉10斤を食い、天下の諸侯これを恐れ、あえて趙の国境を侵さなかったと言います」
「まして私はいまだ70に及ばず、何ゆえ老いたりとて、さように軽んじられるのですか? それがしただひとり、3千余騎をひきい、必ず夏侯淵の首を取ってまいるでしょう」
諸葛亮はなお聴かない。だが、黄忠が幾度となく執念深く許しを乞うので、ついに折れ、条件を付して許す。
「強いて行かれるならば、法正(ほうせい)を監軍(かんぐん)として同伴なさい。そして万事合議し、慎重に事を行うがよろしい。決して軽々になさってはなりません。我もまた兵をもって援助しましょう」
黄忠は文字通り勇躍、兵をひきいて出発した。
その後、諸葛亮は密かに劉備(りゅうび)に言った。
「老将黄忠、ただ簡単に許しては駄目なのです。ああして言葉をもって励まし、初めて責任もいっそう強く感じ、相手の認識も新たにすると申すものです。ただいま出発いたしましたが、別に援兵を送る必要がありましょう」
劉備の許しを得ると、さっそく諸葛亮は趙雲(ちょううん)を呼び寄せて命ずる。
「ご辺は一手の兵をひきい、小路より奇兵を出し、黄忠に力を添えてほしい。しかしながら、黄忠が勝ちにあらば、決して出ることなかれ。彼が敗色濃き折を見て助けよ」
また劉封(りゅうほう)と孟達(もうたつ)にも、ともに3千余騎をひきいて、山中の険阻なるところに堂々と旗を立て、味方の勢いの盛んなるを示し、敵の心を惑わすべしと申しつけた。
さらに厳顔(げんがん)を巴西(はせい)と閬中(ろうちゅう)へ行かせ、張飛(ちょうひ)や魏延(ぎえん)と交代して難所を固めさせる。張飛と魏延は還って漢中(かんちゅう)攻略をなさんと。
加えて下弁(かべん。下辨)に人を遣り、馬超(ばちょう)に諸葛亮の計を伝える。こういう完璧な攻略手配を秩序よく行った。
(02)定軍山
天蕩山を追われて逃げ延びた張郃と夏侯尚は、夏侯淵に会って進言した。
「味方は大将を討たれ、多くの兵を損じたり。そのうえ劉備自ら蜀の大軍を配し、漢中を攻めんとの説あらば、即刻、魏王(曹操)に救援の兵を求めたまえ」
夏侯淵は大いに驚き、この旨を南鄭の曹洪に報じ、曹洪もまた早馬を飛ばして都(鄴都)の曹操に伝えた。
(03)鄴都
急報に接すると、曹操は急いで文武の大将を召集し、緊急会議を開いた。この席で長史(ちょうし)の劉曄(りゅうよう)が、曹操自身の出馬を促す。
曹操は実(げ)にもとうなずき、「先ごろも汝(なんじ)が言を用いずして、今これを後悔している」と称し、一議もなく、即時40万の大軍を起こした。
★ここにある「先ごろも……」は、漢中を攻略した曹操に、司馬懿(しばい)や劉曄がこのまま劉備を討つよう勧めて容れられなかったことを指している。先の第208話(01)を参照。
魏の大軍は(建安〈けんあん〉23〈218〉年の)7月に都を発ち、9月には長安(ちょうあん)へ入る。
(04)長安
ここで曹操は陣容を整え、まず全軍を三手に分けた。主力の中軍には自ら臨み、先陣を夏侯惇(かこうじゅん)、後陣を曹休(そうきゅう)とする。
(05)潼関(どうかん)
絢爛(けんらん)たる軍容は粛々と辺りを払い、潼関まで進む。曹操は遥かに樹木の生い茂ったところを見て、「あれはいずくぞ?」と問う。
従者が答える。
「藍田と申すところです。あの樹林の内が、すなわち蔡邕の山荘でございます」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(蔡邕は)後漢末を代表する儒学者。かつて無理やり董卓(とうたく)に招聘(しょうへい)された。第2巻『人間燈』参照」という。
近侍の答えに、曹操は往事を思い出して、山荘を訪れようと言った。
むかし蔡邕と交わりを深めていたころの話だが、彼には蔡琰(さいえん)という娘があった。縁あって衛道玠(えいどうかい)に嫁いだものの、韃靼(だったん)に生け捕られ、胡(えびす)のために無理に妻とされてしまった。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)では、「『後漢書・列女伝』によれば、蔡琰の前夫の名は衛仲道(えいちゅうどう)とするのが正しい。衛仲道と蔡琰の間には子がなかったため、夫が死ぬと蔡琰は実家に帰った」という。
蔡琰の悲嘆は天地も崩れるばかりだったが、ついに胡の子をふたりまでも生んだ。しかし、明けるにつけ暮るるにつけ、この砂漠不毛の国に捕らわれては、故郷恋しく、涙に袖の乾く間もなかった。
とりわけ、胡が好んで吹く笳(か)という笛を聴くたびに、郷愁は増すばかりで、ついには思慕の悲しさから、自ら18曲(『胡笳十八拍〈こかじゅうはっぱく〉』)を作曲した。
この曲がいつしか伝え伝わり、中国に流布されたのを、偶然に曹操が聴いた。曹操は心情の哀れさに、韃靼国へ人を遣わし、千両の黄金をもって蔡琰を渡すよう交渉した。
胡の左賢王(さけんおう)も、曹操の勢いが盛んなるを知っていたので、渋々ながら蔡琰を還してよこした。曹操は喜び、彼女を董紀(とうき)に娶(めあわ)せた。
いま図らずも蔡邕の山荘と聞き、大軍を先に進ませると、曹操は近習(きんじゅう)の者100騎ほどを連れて、董紀の屋敷を訪れた。
★胡の左賢王は先の第120話(04)にも登場しているが、ここで登場した左賢王と同一人物なのかはわからない。
★『三国志演義大事典』によると「左賢王とは匈奴の貴族において四角(しかく)と呼ばれる4人の王のうち最高位のもので、太子または単于(ぜんう。匈奴の最高指導者)の後継者に与えられる称号である」という。
★同じく『三国志演義大事典』では「『後漢書・列女伝』によれば、董紀の名は董祀(とうし)とするのが正しい。董祀は蔡琰と同郷で、屯田都尉(とんでんとい)を務めた」という。
★新潮文庫の註解によると「(匈奴は)北方の異民族。漢の高祖(劉邦〈りゅうほう〉)に対抗した冒頓単于(ぼくとつぜんう)以来、強大な勢力を有していた」という。
(06)藍田 董紀邸
ちょうど主人の董紀は所用で留守だったが、曹操のわざわざの来駕(らいが)と聞き、蔡琰は驚いて自ら丁重に迎えた。
曹操は堂に座して健勝を喜び、堂内を眺める。ここで壁に碑文を書した画軸があるのに気づき、「これは、いかなるものか?」と尋ねた。
蔡琰は畏(かしこ)まって答える。
「これは曹娥(そうが)と申す者の碑文でございます。むかし和帝(劉肇〈りゅうちょう〉)の朝(ちょう。ひとりの天子が位にあった期間)、会稽(かいけい)の上虞(じょうぐ)というところに、曹旴(そうく)と申すひとりの師巫(かんなぎ。神に仕えて舞いやお祈りをし、人に神の言葉を伝える者)がおりました」
★新潮文庫の註解によると「(和帝は)後漢の第4代皇帝。在位88~105年」という。
「この人は神楽の上手な人で、ある年の5月5日、したたか酒に酔いまして、舟の上で舞いますうち、誤って川に落ち、水に溺れて死にました」
「その人に14歳になる娘がありましたが、これを泣き悲しみまして、毎日毎夜、川の縁を巡っておりましたが、七日七夜目、とうとう娘も淵(ふち)に飛び込んでしまったのです」
曹操は感じ入ったごとく、まじろぎもせず、蔡琰が語るを聴き入っていた。
「それから5日目のことでございます。その娘が父の屍(しかばね)を背負うて水面に浮かび出ましたので、里の人々は父を思う娘の一念に驚きましたが、この心を哀れに思いまして、懇ろに岸辺に葬りました」
「ほどなく、このことが上虞県令(じょうぐけんれい)の度尚(どしょう)と申す人から奏されますと、天子は『孝女なり』と仰せられ、邯鄲淳(かんたんじゅん)に文章を起草するよう命ぜられ、それを石に刻ませました。邯鄲淳はこのときわずか13歳で、筆を執って文を作り、一字も訂正しなかったと申します」
「父の蔡邕はこのことを聞きまして、碑の下に行き、その文を見ようとしましたが、すでに日が没して読むことができません。そこで指で石をなで、筆画を探って読み感じ、碑背に八字を書き付けました。後になって里人が、その八字を刻み付けました。そちらにございますのが父の筆の跡です」
蔡琰の指すほうを見れば、「黄絹幼婦(こうけんようふ)。外孫韲臼(がいそんさいきゅう)」と八字が書かれてあった。
曹操はこの文を読み下すと、蔡琰に向かい、「汝、この八字の書の意味を知るか?」と尋ねる。
蔡琰は頰を染めて答えた。
「父が書きましたもの。その意(こころ)を知りたくは思っておりましたけれど、いまだにその意味を解しかねております」
曹操は席にあった大将たちに向かって、「誰か、この文意を解した者があるか?」と見回したが、そろってただ首をうなだれ、答える者はない。
するとそのうちからひとり、「それがし、解き得たように存じます」と立ち上がった者がある。見れば主簿(しゅぼ)の楊修(ようしゅう。楊脩)だった。
曹操は、彼が文意を語りだそうとするのを抑えて言った。
「さようか。しかし、しばらくそれを言わずにおるように。予も考えてみよう」
(07)藍田
曹操は馬にまたがり、董紀の屋敷を出る。しばらくして、莞爾(かんじ)とした顔を表し、楊修に考えを申してみよと言った。
楊修は、よどみなく説明する。
「これは確かに隠し詞(ことば)に違いございません。黄絹と申すは色の糸。文字にしますれば『絶』の字にあたります。幼婦は少(わか)き女、『妙』の字です。外孫は女(むすめ)の子、これ『好』でありましょう。韲臼は辛きを受ける器で、『辞』の字にあたると考えます」
「これを連ねて『絶妙好辞』。邯鄲淳の文を賛して、絶(すぐ)れて妙(たえ)なる好(よ)き辞(ことば)と褒めたものと存じますが」
曹操は大いに驚き、予の考えもまったく同じであったと賞した。山荘を出て本軍を追い、日ならずして漢中に着く。
(08)漢中(南鄭)
曹洪は恭しく出迎え、まず張郃がたびたびの戦に敗れたことを語った。
だが、曹操は温かい心を示して言う。
「これは張郃の罪ばかりではない。勝敗は武士の常の道。とがむることはあるまい」
続いて曹洪は目下の情勢を報告。
「敵は劉備自ら大軍を指揮し、黄忠に命じて定軍山を攻めさせた様子です。ところがどうしたことか、夏侯淵は大王がおいでになると聞き、固く守るのみで、戦闘をいたさぬ模様でございます」
これを聞くと、曹操は早く使者を遣わすよう言い、潔く出でて戦うよう計らえと命じた。
そばにいた劉曄はこう諫める。
「夏侯淵は性急のうえに剛直ですから、おそらく敵の計略にかかって痛い目に遭うに違いありません。おやめになったほうがよろしいでしょう」
しかし曹操は聞き入れず、手ずから王命を書して、定軍山の夏侯淵のもとに使いを遣った。
(09)定軍山
夏侯淵は曹操の親書を見て勇躍した。さっそく兵を整えると、張郃を呼んで言った。
★曹操の親書の冒頭に「詔(みことのり)シテ夏侯淵ニコレヲ知ラシム」とあった。帝位に即いたわけでもないのに、ここで「詔シテ」はないだろう……。
「ただいま大王の大軍は漢中に到着。予に命じて敵を討たしめんとす。予は久しくこの所を守り、一度も会心の勝負をなさず、髀肉(ひにく)の嘆をかこちいたり。明日、自ら出でて思うさま戦い、まず黄忠を生け捕ってみせよう」
張郃はこれを危なっかしく聞き、堅く守られるのが賢明だと、極力出撃を思いとどまらせようとした。
★髀肉の嘆については、先の第122話(06)および第170話(01)を参照。正史『三国志』では「蜀書・先主伝」の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く司馬彪(しばひゅう)の『九州春秋』に見える。
管理人「かぶらがわ」より
天蕩山に続き、定軍山の攻略に向かう黄忠。諸葛亮はあえて厳しい言葉をかける一方、各方面からの支援態勢を整えます。これに対し、曹操も大軍をひきいて到着。漢中の攻防戦は新たな局面を迎えました。
曹娥の碑のエピソードも盛り込まれていて、何だかあわただしい感じの第220話でした。

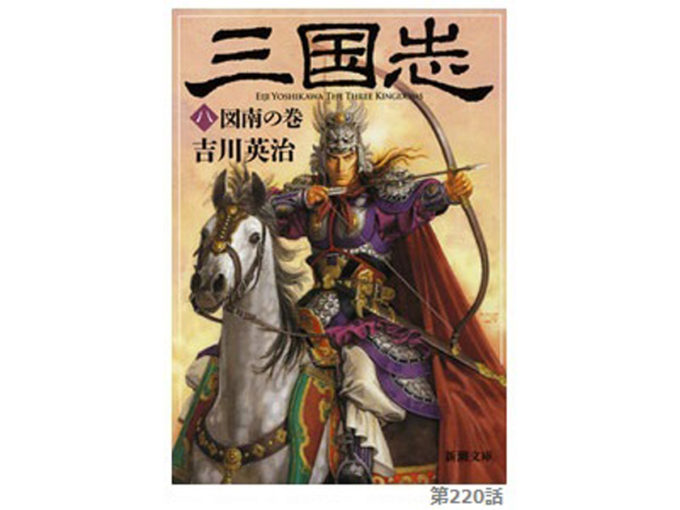


















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます