太和(たいわ)元(227)年、魏の曹叡(そうえい)は曹真(そうしん)を大都督(だいととく)に任じ、20万の大軍を委ねる。副将には郭淮(かくわい)が選ばれ、さらに王朗(おうろう)が軍師として従軍することになった。
やがて諸葛亮(しょかつりょう)ひきいる蜀軍と、祁山(きざん)の前で対陣した魏軍。ここで王朗が陣頭に馬を進め、諸葛亮の論破を試みるが――。
第281話の展開とポイント
(01)洛陽(らくよう)
このとき(蜀の建興〈けんこう〉5〈227〉年)、魏は太和元年にあたっていた。
★原文「大化元年」だが、ここは「太和元年」としておく。ただの誤りなのか、何か特別な意味があるのかは判断つかず。
魏の国議は、国防総司令の大任を一族の曹真に命ずる。彼は固辞したものの、曹叡は許さない。
さらに王朗もこう言った。
「将軍は社稷(しゃしょく。土地と五穀の神。国家)の重臣。ご辞退あるときではございません。もし将軍が行かれるなら、それがしも不才を顧みずにお供して、命を捨てる覚悟でともに大敵を破りましょう」
この言に動かされ、ついに曹真も決意し、副将には郭淮が選ばれる。
曹叡は曹真に大都督の節鉞(せつえつ。天子が賊を討伐する将軍に賜った割り符と鉞〈まさかり〉)を授け、王朗には軍師たれと命じた。王朗は献帝の世より仕え、すでに76歳となっている。
(02)長安(ちょうあん)
長安の軍勢20万騎、実に美々しい出陣だった。先鋒の宣武将軍(せんぶしょうぐん)の曹遵(そうじゅん)は曹真の弟にあたる。副先鋒は盪寇将軍(とうこうしょうぐん)の朱讃(しゅさん)だった。
(03)渭水(いすい)の西
やがて魏の大軍は、渭水の西に布陣する。ここで王朗が言った。
「いささか思うところがあります。大都督には明朝、大陣を展開され、旌旗(せいき)のもと威儀厳かに、それがしのなすことを見ていてください」
曹真が、何を計ろうとされるのかと尋ねると、王朗は、何の計もないと答える。ただ一舌の下に諸葛亮を説破し、彼の良心をして魏に降伏させてみせると。
(04)祁山
翌朝、魏蜀両軍は祁山の前に陣を張る。三通の鼓が鳴った。しばし剣箭(けんせん。戦)を休め、開戦に先立ち、ひと言なさんとの約声である。
★『完訳 三国志』(小川環樹〈おがわ・たまき〉、金田純一郎〈かねだ・じゅんいちろう〉訳 岩波文庫)の訳注によると、「太鼓をひとしきり(しばらく続く様子に)打ち立てるのを一通という。その数は唐代の兵法書によると333回を一通とする由である(『通典〈つてん〉』巻149に引く趙国公王琚〈おうきょ〉の『教射経』)。三通は合計1千回に近い打ち方となる」という。
諸葛亮は四輪車の上から、魏の軍(いくさ)立てを感じ入ったように眺めていた。そしてサッと門旗を開くや、関興(かんこう)や張苞(ちょうほう)らに守られつつ、中軍を出て敵陣の正面に止まる。
「約により、漢の諸葛丞相(じょうしょう)これに臨めり。王朗、疾(と)く出でよ」
声に応じて魏軍の門旗が揺れ動く。白髯(はくぜん)の王朗が黒甲錦袖をまとい、馬を進めて近づいてくる。
ここで王朗は陣頭の大論戦を挑む。まずは魏の正義を説き、この戦いの名分を明らかにしようとした。
敵味方とも鳴りを静めて耳を傾けたものの、特に蜀の軍勢までが、道理のあることかな、と声には出さぬが、嗟嘆(さたん)してやまない様子。
心ある蜀の諸将は一大事だと思った。敵側の弁論に魅惑され、蜀の三軍がこう感じ入っているようでは、たとえ戦いを開始しても勝てるわけがない。
傍らに立つ馬謖(ばしょく)も心配そうな目をし、車上の諸葛亮の横顔を見ていた。諸葛亮は山より静かな姿をしている。終始黙然と微笑を含んでもいた。
馬謖は思い出す。むかし季布(きふ)という口舌の雄が、漢の高祖(劉邦〈りゅうほう〉)を陣頭で論破し、ついにその兵を破り去った例がある。王朗が狙っているのはまさにその効果だ。
早く丞相が何とか論駁(ろんばく)してくれればよいが、と密かに焦燥(しょうそう)していると、やがて諸葛亮がおもむろに口を開いて言い返した。
「申されたり王朗。足下(きみ)の弁や誠によし。しかし、その論旨は自己撞着(どうちゃく)と欺瞞(ぎまん)にすぎず、聞くに堪えない詭弁(きべん)である。さらばまず説いて教えん」
結論的には、漢朝に代わるべく立った蜀の朝廷と魏の朝廷とのいずれが正しいかになる。要するに、その正統論だけでは、魏には魏の主張があり、蜀には蜀の論拠があって、これは水掛け論に終わるしかない。
そこで、諸葛亮はもっぱら理念の争いを避け、衆の情念を突いたのである。果たして彼が言葉を結ぶと、蜀の三軍はワアッと大呼を上げてその弁論を支持し、自己の感情をその言説に加えた。
それに反して、魏の陣は啞(おし)のごとく滅入っていた。しかも、当の王朗は諸葛亮の痛烈な言葉に血が激し、気がふさがり、恥じ入るごとくうつむいていたと思われる。だが、そのうちにひと声うめくと馬上から転(まろ)び落ち、そのまま息絶えてしまう。
諸葛亮は羽扇を上げ、次に敵の都督の曹真いでよ、と呼び出して告げる。
「まずは王朗の屍(しかばね)を後陣へ収めるがよい。人の喪に付け入り、急に勝利を得んとするような我ではない。明日、陣を新たにして決戦せん。汝(なんじ)よく兵を整えて出直してきたれ」
(05)曹真の本営
力と頼む王朗を失い、曹真は序戦に気をくじいてしまう。副都督の郭淮はそれを励ますべく、必勝の作戦を力説して勧める。曹真も心を取り直し、さらばと、密なる作戦の備えにかかった。
(06)諸葛亮の本営
そのころ諸葛亮は、帳(とばり)の内へ趙雲(ちょううん)と魏延(ぎえん)を呼び入れて、ふたりして魏陣へ夜襲を仕掛けよと命じていた。
魏延は、曹真も兵法にかけてはひとかどの者ですから、おそらく不成功に終わるでしょう、と不安を述べる。
これに対して諸葛亮が教えた。
「こちらの望みは、彼がこちらの夜襲があることを知るのをむしろ願うものだ。思うに曹真は祁山の後ろに兵を伏せ、蜀の夜襲を引き入れ、その虚にわが本陣を急突して、一挙に撃砕せんものと、今や鳴りを潜めているに違いない」
「そこでこちらは、わざとご辺(きみ)たちを彼の望み通りに差し向けるのである。途中で変があれば、すぐにこうこうせよ」
次いで関興と張苞にもそれぞれ一軍を与え、祁山の険阻へ差し向ける。馬岱(ばたい)・王平(おうへい)・張嶷(ちょうぎ)には別に一計を授け、本陣付近に埋伏させておく。
かくとは知らぬ魏軍は、曹遵と朱讃らの2万余騎を密かに祁山の後方へ迂回(うかい)させ、蜀軍の動静をうかがっていた。
そこへ「敵の関興と張苞の両軍が蜀陣を出て、味方の夜討ちに向かった」という情報が伝わったので、曹遵らは突如、山の陰を出て蜀の本陣を急襲した。敵の裏をかき、手薄な留守を突こうとしたものである。ところが諸葛亮は、すでに裏の裏をかいていた。
魏軍が蜀の本陣へ突入してみると、柵の四門に旗風が見えるばかりで、一兵の敵影もない。のみならず、たちまち山と積んである諸所の柴(シバ)がバチバチと炎を発し、その火炎は天を焦がして地をたぎらせた。
曹遵と朱讃は退くように命ずるが、どうしたわけか、味方は少しも退かない。かえって、好んで炎の中心へ押しなだれてきた。それもそのはず、すでに魏軍の後ろには至るところで蜀軍が駆け迫り、隊尾から激しく撃滅の猛威を加えていたのである。
馬岱や王平などに加え、夜襲に向かったはずの張嶷や張翼(ちょうよく)なども急に引き返し、敵の後方を断った。そしてほとんど、全魏軍を袋の鼠(ネズミ)としてしまったのである。
魏軍はしたたかに討たれ、炎の中に焼け死んだり、踏みつぶされた者も数知れない。曹遵と朱讃すら、わずか数百騎を連れたのみで、辛くも逃げ帰るほど。しかもまた、その途中で趙雲の一手が道を遮り、なお完膚なきまでに殲滅(せんめつ)を期すものがあった。
(07)曹真の本営
さらに魏の本陣へ戻ってみれば、ここも関興と張苞の奇襲に遭い、総軍壊乱を来しているというありさま。何にしてもこの序戦は、惨憺(さんたん)たる魏の敗北に始まり、全壊状態に終わる。
曹真も遠く退き、おびただしい負傷者や敗兵をいったん収め、全軍の再整備をなすのやむなきに立ち至った。
管理人「かぶらがわ」より
陣頭で憤死する王朗って……。この設定は何だかなぁ。史実の王朗は魏の太和2(228)年に亡くなっていますが、曹真の軍師として諸葛亮と対峙(たいじ)したことはありません。
諸葛亮が陣頭に立ち、王朗を通じて魏を論破する。あぁすっきり、といったところでしょうけど、こういう創作はあまり感心しませんね。

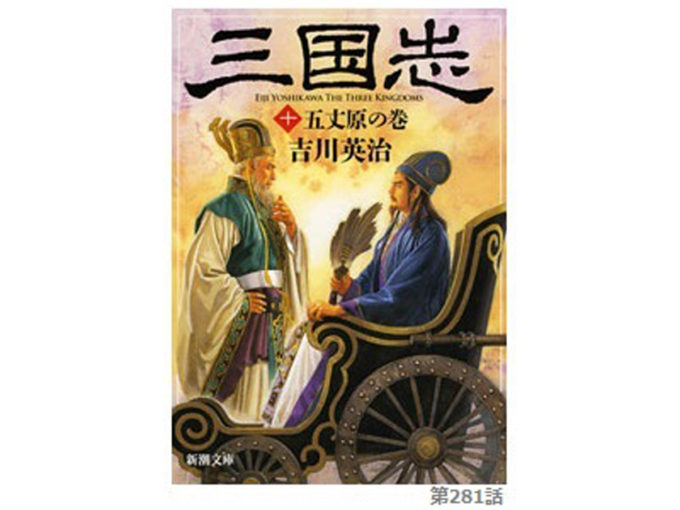














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます