曹操(そうそう)は蜀を手にした劉備(りゅうび)の動きを封ずるべく、まずは漢中(かんちゅう)の張魯(ちょうろ)攻めを決断する。
曹操は自ら大軍をひきいて遠征に臨み、策を用いて陽平関(ようへいかん)を突破すると、敵方の楊松(ようしょう)を内応させ、南鄭(なんてい)も陥す。張魯は降伏し、曹操は新たに漢中を版図に加えた。
第207話の展開とポイント
(01)許都(きょと) 丞相府(じょうしょうふ)
「急に魏公(曹操)が、あなたと夏侯惇(かこうじゅん)のおふたりに内々に密議を諮りたいとのお旨である。すぐ府堂までお越しありたい」
賈詡(かく)の手紙を受け取った曹仁(そうじん)は、洛中の屋敷から内府へ急ぐ。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第66回)では、このとき曹仁と夏侯惇は許都におらず、曹操が使者を遣って呼び寄せている。
ここの政庁の府でも、曹仁は魏公の一門に連なる身なので、肩で風を切るような態度だった。どこの門も大威張りで通る。
だが、曹操のいる中堂の入り口まで来ると、「こらっ、待て!」と何者かに誰何(すいか)された。見ると許褚(きょちょ)が狛犬(こまいぬ)のように剣をつかみ、番に立っている。魏公はお昼寝中だから、通ってはならないというのだ。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、夏侯惇よりひと足先に許都に到着した曹仁が、曹操に会うため夜中に丞相府にやってきたとある。また、曹操はちょうど酒を飲んで寝たところで、室内に入ろうとした曹仁を許褚が遮ったともあった。
曹仁は、お昼寝中でも構わないと言うが、許褚はどうしても通さない。頑として入れなかった。
やむなく待っているうちに、ようやく曹操が昼寝から起きたとある。曹仁はやっと通されて曹操に会うと、ありのまま話した。
聞くと曹操は、「それは虎侯(ここう。許褚のあだ名)らしい。彼のような男がいればこそ、予も枕を高くして臥(ふ)すことができる」と、かえって彼の忠誠を大いに褒めた。
まもなく夏侯惇が来て、賈詡も顔を出した。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、(許褚が曹仁の入室を遮った日から)数日も経たないうちに夏侯惇も許都に到着し、曹操は一緒に征伐について話し合ったとある。
曹操は3人をそろえてから、今日の用向きを語りだす。
「近ごろよくよく考えると、どうも蜀をあのまま放っておくのは将来の大患だと思う。何とか今のうちに、玄徳(げんとく。劉備のあざな)を蜀から切り離す方法はないだろうか?」
夏侯惇は、それをなすには、まず漢中が問題になると言い、今なら一鼓して討ち破れるだろうとの見解を述べる。
曹操が、西征の大旅団を編制して張魯を討つかと言いだすと、賈詡も言った。
「あそこを取れば、蜀の兵は扉の口を封じられた糧倉の鼠(ネズミ)のようなもので、中で居食いを続けていても、その運命は知れたものです」
(02)漢中
漢中は騒動した。とりわけ張魯と一門は、連日の軍議に追われる。魏の大軍が三手に分かれてくるという。一手は夏侯惇、一手は曹仁、一手は夏侯淵(かこうえん)と張郃(ちょうこう)。そして曹操自身も中軍にあると。
★井波『三国志演義(4)』(第67回)では、夏侯淵と張郃が先鋒、曹操自身が諸将をひきいて中軍、曹仁と夏侯惇が後詰め、という三手に分かれていた。
この動きに対し、張衛(ちょうえい)を大将に、楊昂(ようこう)や楊任(ようじん)などが続々と陽平関へ向かった。
(03)陽平関の関外
陽平関は左右の山脈に森林を擁し、長いすそ野には諸所に険阻もあり、一望雄大な戦場たるにふさわしかった。関を隔つこと15里、すでに魏の西征軍の先鋒は陣地を構築し始めている。
陽平関の序戦では魏の先鋒が大敗を喫した。敗因は魏兵が地勢に暗かったことと、漢中軍がよく奇襲を計り、敵を各所で寸断し、孤立した軍を捉えては殲滅(せんめつ)を加えるという戦法に出たことが奏功したものとみえた。
「若い若い。汝(なんじ)らの攻撃を見ていると、まだまるで児戯に等しい――」
曹操は、前線からなだれ打って逃げてきた先鋒の醜態に怒り、夏侯淵と張郃に言った。そして自ら先陣を編制し、許褚と徐晃(じょこう)を従えて一高地へ上った。
しかし、曹操が張衛らの布陣を見ていたところ、背後の山から驟雨(しゅうう)のように矢が飛んでくる。驚いて振り返ると、敵の楊昂・楊任・楊平(ようへい)などの旗印が、ふもとの退路を断ちにかかっていた。
★楊平の名は正史『三国志』や『三国志演義』に見えない。
この日から翌日にかけ、またしても魏軍は莫大(ばくだい)な兵を損じた。3日目にも挽回がつかず、曹操も苦戦に陥り、万死のうちに一生を拾って逃げ帰ったほどである。
陣を70里ほど退き、対峙(たいじ)すること50余日。曹操は「ひとまず許都へ帰って出直そう」と触れた。一夜のうちに、魏の旌旗(せいき)は忽然(こつぜん)と搔(か)き消えた。
漢中軍の帷幕(いばく。作戦計画を立てる場所、軍営の中枢部)では、「今こそ退く魏兵を追い、徹底的に殲滅すべし」となす楊昂の説と、「いやいや、曹操は謀計の多い人物だ。うかとは追えない」という楊任の説とが対立。
結局、楊昂は我説を張り、ついに五寨(ごさい)の軍馬を挙げて追撃に出た。漢中の破滅はこれが重大な一因をなす。せっかくここまで勝ち続けていたものを、曹操の計に乗り、一遍に無にしたものだった。
この日は霧風という、大陸的な気流の激しい中に、咫尺(しせき。極めて近い距離。咫は8寸、尺は10寸)も分かたぬほど濃霧が立ち込めていたのである。
楊昂の軍勢が出た夕方、陽平関の下で開門を求める軍馬があり、味方が帰ったものと考えて門を開くと、魏の夏侯淵が3千の精鋭を連れて突き入ってきた。
★井波『三国志演義(4)』(第67回)では、このとき夏侯淵が突き入ったのは陽平関ではなく、楊昂の砦(とりで)。楊昂の5つの砦の守兵が逃げ出した後、敗報を聞いた張衛も陽平関を放棄し、皆で南鄭へ逃げ帰ったとあった。
夜に入ったうえに留守は手薄だったため、炎の城頭高く、たちまち魏の旗が立てられてしまう。総司令の張衛は、いち早く南鄭へ逃げ落ちる。
楊昂は後方の火の手に驚いて追撃をやめ、あわてて引き返したが、途中で許褚の手勢に捕捉され、完膚なきまでに粉砕された。楊昂自身も、あえなく屍(しかばね)を野にさらした。
★井波『三国志演義(4)』(第67回)では、楊昂を討ち取ったのは張郃。
残る楊任も、張衛の後を追って南鄭関へ逃げ延びたが、この惨めな敗戦に張魯が激怒。「それ以上退く者は即座に首を刎(は)ねる」と、厳重な督戦令を出した。
そのため楊任は再び陽平関を指して戦いに行ったが、途中で猛進してきた夏侯淵と出会い、これもまたあえなく路傍に戦死した。
★井波『三国志演義(4)』(第67回)では、楊任が討たれる前に、配下の部将の昌奇(しょうき)も夏侯淵に討たれている。だが、吉川『三国志』では昌奇を使っていない。
曹操の大軍は、切り開く先鋒の快速に続いて陽平関を抜き、南鄭関までひと息に来た。
(04)漢中
漢中の府は、すでに指呼の間にある。張魯は事態の重大に震え上がり、文武の百官に大呼した。
「今や存亡の最後に迫った。誰かこの危急にあたって漢中を救う者はないか?」
すると閻圃(えんほ)が、龐徳(ほうとく。龐悳)しかいないと叫ぶ。すでに馬超(ばちょう)はこの国にいないのに、その一族の龐徳だけが、どうしてひとり漢中に残っているのか――。
★龐徳は馬超の腹心に違いないが、その一族とまでは言えないのでは?
いぶかる者もあったが、もちろん張魯は知っていた。馬超が葭萌関(かぼうかん)へ向かったとき、龐徳は病のために、行を共にしなかったのである。その後は病も癒え、近ごろは元気だという。
★馬超が葭萌関へ向かったことについては、先の第203話(02)を参照。ただし、そこでは龐徳の病に触れていなかった。
張魯は膝を打って閻圃の進言を容れ、すぐ呼びに遣る。龐徳は重大な命を受けるや、1万余騎をひきいて前線へ赴いた。
(05)南鄭関の関外
龐徳きたると聞くと、曹操は何とかして手捕りになし、魏の味方にしたいものだ、と全軍の諸将へ内示する。
これを受け、諸軍はもっぱら神経戦に持ち込む。数段に備えを立て、いわゆる車掛かりとなり、順番に接戦しては退き、新手が出てはすぐ次に代わるという戦法を採った。
しかし龐徳は疲れない。この間にさえ許褚と馬を駆け合わせ、烈戦50余合に及んで勝負なしに引き分けながら、なお余裕しゃくしゃくとして次の備えに当たっていた。
ここで賈詡が一計を献ずる。そのせいか翌日の魏軍は崩れ立ち、十数里退いた。龐徳は魏の陣屋を占領したが、いつになく敵の勢いに手ごたえがないので、決して油断はしていない。
果たせるかな、その夜半、魏の大軍が四方から起こった。龐徳は「その策には乗らぬ」とばかり、鮮やかに南鄭の城内へ引き揚げた。
占領した魏の陣屋には、たくさんの兵糧や軍需品があったので、それらの鹵獲品(ろかくひん)はみな先に城内へ搬入させていた。
ところが、戦利品を搬入する雑軍の中に、魏の間諜(かんちょう)が混ざっていたものとみえ、城内にある楊松の屋敷を訪ねていた。
(06)南鄭 楊松邸
「手前は魏公曹操の腹心の者ですが……」と、男はひるみもなく正面を切る。そして、肌に着けてきた黄金の胸当てと曹操直筆の書簡を取り出し、「まずはご一覧ください」と言った。
楊松は漢中の重臣だが、常に賄賂を好み、悪辣(あくらつ)な貪欲家として有名だった。黄金の胸当てを見ると目を細め、垂涎(すいぜん)せんばかりな顔色を示す。
のみならず曹操の書簡には、彼が夢想もしなかった恩爵の好餌をもって裏切りを勧めてある。一も二もなく、楊松は内応を約した。
(07)漢中
楊松は漢中へ行き、すぐ張魯に龐徳の讒言(ざんげん)を呈する。彼は本気で戦っていない。曹操と内通しているかもしれないので、お調べになる必要があると。
★このあたりでは南鄭関(城)と漢中が別の場所のように描かれていたが、漢中郡の郡治(郡の役所が置かれた場所)が南鄭県であり、両者は同じ場所。
張魯はこの佞弁(ねいべん)に乗せられ、龐徳を呼び返した。
龐徳が取るものも取りあえず帰ってみると、張魯は思いも寄らない怒り方で、果ては首を刎ねんと罵った。
傍らの閻圃が執り成したので、張魯は一命を預けておくとした。龐徳は怏々(おうおう)と楽しまぬものを抱き、是非なく再び戦場へ出る。
(08)南鄭関の関外
こうして龐徳は、あえて無謀な戦闘に突入。単騎で敵陣深くへ斬り入り、帰ろうとしなかった。
そのとき、丘の上から曹操が呼びかける。
「龐徳、龐徳。どうして急に犬死にを焦るか。なぜ我に降伏し、大丈夫(だいじょうふ。意志が堅固で立派な人物)の命を全うしようとしないのだ」
龐徳は丘に向かって馬を躍らせたが、そのふもとで忽然と影を失う。深さ20尺もある落とし穴へ、馬もろとも落ちてしまったのである。
龐徳は降伏し、その日から曹操の一臣に列した。
(09)漢中
伝え聞いた張魯は「楊松の言った通りだ」と、いよいよ信頼し、何事も彼に諮った。
だが、もう南鄭も落城し、漢中市街は曹操軍の鉄環に包まれんとしている。すでに外郭の防御も放棄し、味方が四散しだしたと知ると、張衛は焦土作戦を主張したが、楊松は反対して無血譲渡を勧めた。
張魯は転倒の中にも、「国財は民の膏血(こうけつ。苦労して手に入れた収入)から生まれた国家の物である。私にこれを焼棄するは、天を恐れぬものだ」と、よく事理を分別。
そこで城内の財宝や倉廩(そうりん)にことごとく封を施し、一門の老幼を連れ、その夜の二更(午後10時前後)ごろ南門から落ち延びた。
漢中占領後、曹操は言った。
「官庫の財宝を封印して兵火や略奪から救い、そのまま次代の司権者に渡すとなした行いは、けだし張魯一代の善行といえよう。神妙な仕方というべきだ」
そこで巴中(はちゅう)へ人を遣り、降参するなら一族は保護してやろうと言い送った。
(10)巴中
楊松は曹操の申し入れに応ずるよう勧めたが、張衛は何としても聞かない。勝ち目のない抗戦を続け、我から求めて討ち死にした。
★井波『三国志演義(4)』(第67回)では、張衛を討ち取ったのは許褚。
曹操が残敵を掃討しながら巴中へ出馬してきた折に、張魯は城を出て、ついにその馬前に拝伏した。もちろん楊松がそばについていた。彼は内心、自分の功を非常に高く評価している顔つきである。
ところが楊松には目もくれず、曹操は馬を下り、張魯の手を取った。そして慰めて言う。
「倉廩を封じて兵燹(へいせん。戦争のために起こる火事)から救われたことは、まさに天道の嘉(よみ)するところである。曹操はそのお志に対し、足下(きみ)を鎮南将軍(ちんなんしょうぐん)に封ずるであろう」
なお曹操は、張魯の旧臣のうち5人を選んで列侯に加えたが、その中に閻圃の名はあったが、楊松の名はなかった。
楊松は密かに自負した。
「俺にはもっと大きな恩爵が、やがて沙汰されるに違いない――」
(11)漢中
漢中平定の祝賀日、街の辻(つじ)で首斬りが行われた。罪人の首は細々と痩せている。意外にも、それが楊松だった。
管理人「かぶらがわ」より
漢中の平定を果たし、新たに龐徳を配下に加えた曹操。降伏した張魯を厚遇する一方、国を売った楊松は容赦なく切り捨てます。
吉川『三国志』には、楊松のような人物が何人も出てきます。呂布(りょふ)に斬られた牛輔(ぎゅうほ)の腹心の胡赤児(こせきじ)とか、曹操に処刑された苗沢(びょうたく)とか――。いつの時代も、欲をかくと手痛い目に遭うものなのですね……。
★胡赤児の最期については、先の第41話(02)を参照。
★苗沢の最期については、先の第181話(09)を参照。

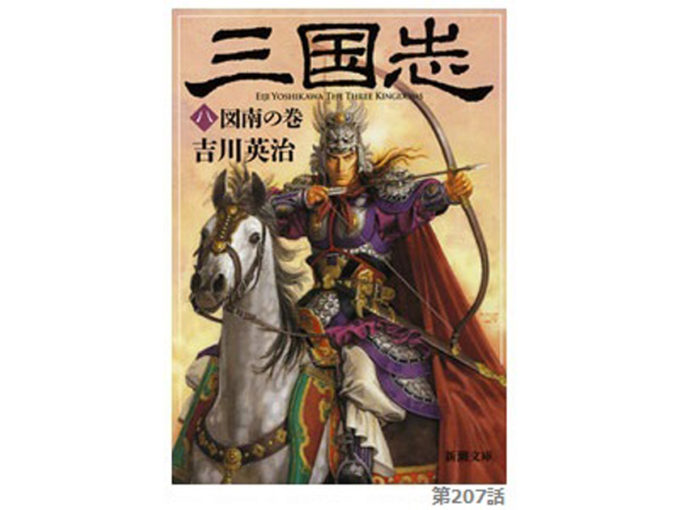















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます