-193年- 癸酉(きゆう)
【漢】 初平(しょへい)4年 ※献帝(劉協〈りゅうきょう〉)
月別および季節別の主な出来事
【01月】
甲寅(こういん)の日(1日)、朔(さく)
日食が起こる。
『後漢書』(献帝紀)
★李賢注(りけんちゅう)によると「袁宏(えんこう)の『後漢紀』に、『(午後4時ごろにあたる)晡(ほ)の8刻前、太史令の王立(おうりゅう)が献帝に上奏し、『太陽が(日食が予想されている宿)度をよぎりますが、(日食の)変異は起こりません、と述べた』。『朝臣は(天譴〈てんけん〉である日食が起こらないということで)みなお祝いを申し上げた。ところが献帝がこれを確認させると、晡の1刻前になって日食が起こった』」
「『賈詡(かく)は献帝に上奏し、王立は観測をつかさどる立場でありながら(事象を)明確にできず、上下の者を誤らせました。どうか刑獄の官に下されますように、と述べた。献帝は、天道は遥かなもの。その事象は明らかにしがたいものだ。(そもそも日食は、天が朕に対して天譴として下すものであって、)罪を史官に負わせようとしては、ますます不徳を重ねるばかりである、と言っ(て許し)た』とある」という。
【01月】
丁卯(ていぼう)の日(14日)
献帝が大赦を行う。
『後漢書』(献帝紀)
【春】
曹操(そうそう)が、鄄城(けんじょう)に陣を置く。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【?月】
荊州牧の劉表(りゅうひょう)が、袁術(えんじゅつ)の糧道を絶つ。袁術は軍をひきいて陳留郡に入り、封丘に駐屯。黒山の残党と匈奴の於夫羅(おふら)らが袁術を助けた。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【?月】「匡亭(きょうてい)の戦い」
曹操が、匡亭の袁術配下の劉詳(りゅうしょう)を攻める。曹操は、加勢に駆けつけた袁術を大破し、袁術は封丘に退却した。
『三国志』(魏書・武帝紀)
★『続漢書』(郡国志)の劉昭注(りゅうしょうちゅう)によると「(陳留郡の平丘県にある)匡人亭(きょうじんてい)は、曹操が袁術を討ち破った場所である」という。
【?月】
曹操が、封丘の袁術を包囲しようとする。袁術は、包囲網が完成する前に襄邑に逃げた。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【?月】
曹操が襄邑を攻め破り、袁術が逃げ込んだ太寿に進み、堀割を決壊させて城に水を注ぎ込む。さらに袁術は寧陵に逃げた。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【?月】
曹操が袁術の追撃を続ける。袁術は九江まで逃げた。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【03月】
袁術が、揚州刺史の陳温(ちんおん)を殺害し、淮南を拠点とする。
『後漢書』(献帝紀)
【03月】
長安の宣平門の外屋が自然に壊れる。
『後漢書』(献帝紀)
★李賢注によると「『三輔黄図』に、『(宣平門は)長安城の東面北頭の門である』とある」という。
【夏】
曹操が袁術の追撃から引き返し、定陶に陣を置く。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【?月】
陶謙(とうけん)が徐州牧に、趙昱(ちょういく)が広陵太守に、王朗(おうろう)が会稽太守に、それぞれ任ぜられる。
『正史 三国志8』(小南一郎〈こみなみ・いちろう〉訳 ちくま学芸文庫)の年表
【05月】
癸酉の日(22日)
雲がないのに雷が鳴る。
『後漢書』(献帝紀)
★ここでは具体的な場所についての記述はなかった。
【06月】
扶風で大風が吹き、雹(ひょう)も降る。
『後漢書』(献帝紀)
【06月】
華山が崩れ、その山肌が裂ける。
『後漢書』(献帝紀)
【06月】
献帝が、太尉の周忠(しゅうちゅう)を罷免し、太僕の朱儁(しゅしゅん)を太尉に任じたうえ、録尚書事とする。
『後漢書』(献帝紀)
【?月】
下邳の闕宣(けつせん)が数千の軍勢を集め、天子を自称する。
『三国志』(魏書・武帝紀)
⇒06月
下邳国の賊である闕宣が、天子を自称する。
『後漢書』(献帝紀)
【?月】
徐州牧の陶謙が、闕宣と結んで兵を挙げ、泰山郡の華県・費県の両県を奪ったうえ、任城国(じんじょうこく)を攻略する。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【06月】
水害がある。
『後漢書』(献帝紀)
★ここでは具体的な場所についての記述はなかった。
【06月】
献帝が、侍御史の裴茂(はいぼう)を遣わして詔獄を視察させ、軽罪の者を赦免する。
『後漢書』(献帝紀)
【06月】
辛丑(しんちゅう)の日(20日)
天狗(てんこう。音がする流星)が西北の空を流れる。
『後漢書』(献帝紀)
★李賢注によると「『前書音義』(『漢書』楚元王伝の顔師古注〈がんしこちゅう〉)に、『(流星は)音がすれば天狗とし、音がしなければ枉矢(おうし)とする』とある」という。
【09月】
甲午(こうご)の日(?日)
献帝が、儒生40余人の試験を行い、上第の者は郎中に、これに次ぐ者は太子舎人に、それぞれ任じたうえ、下第の者は罷免する。
『後漢書』(献帝紀)
【09月】
献帝が詔を下し、老儒生を哀れむ考えを示したうえ、「この9月の試験により罷免された者を、太子舎人とするように」とした。
『後漢書』(献帝紀)
★李賢注によると「劉艾(りゅうがい)の『献帝紀』に、『このとき長安中でこの件に関する童謡が流行し、頭はもう真っ白、稼ぎはとても足りゃしない。上着をたたんで袴(こ)をからげ、いざ古里へ帰ろじゃないか。そしたら聖主が哀れんで、みな郎官にしてくれた。こんな布衣など捨て去って、玄黄の服に着替えなきゃ、と囃(はや)した』とある」という。
★『全譯後漢書 第2冊』(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉、岡本秀夫〈おかもと・ひでお〉、池田雅典〈いけだ・まさのり〉編 汲古書院)の補注によると、「ここでの李賢注にいう謡(童謡)は、単なるわらべうたではなく、その形式を借りた豪族層の輿論(よろん)の発露であった」という。
【?月】「曹嵩(そうすう)の死」
曹操の父である曹嵩が、陶謙配下の部将に殺害される。
『正史 三国志8』の年表
【秋】
曹操が徐州の陶謙を攻め、10余城を陥す。陶謙は城を固守し、あえて出撃しようとはしなかった。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【10月】
太学で儀礼が執り行われる。献帝は永福門に行幸して観覧し、博士以下に差をつけて下賜を行った。
『後漢書』(献帝紀)
【10月】
辛丑の日(22日)
長安で地震が起こる。
『後漢書』(献帝紀)
【10月】
星が天市をよぎる。
『後漢書』(献帝紀)
★李賢注によると「袁宏の『後漢紀』に、『星が天市をよぎるのは、天子が都を遷(うつ)し、その後にまた東遷する兆候である』とある」という。
★『全譯後漢書 第2冊』の補注によると「天市は星座の名。彗星が天市に現れるのは、外軍の徴である」という。
【10月】
献帝が、司空の楊彪(ようひゅう)を罷免し、太常の趙温(ちょうおん)を司空に任ずる。
『後漢書』(献帝紀)
【10月】
公孫瓚(こうそんさん)が、大司馬の劉虞(りゅうぐ)を殺害する。
『後漢書』(献帝紀)
【12月】
辛丑の日(23日)
地震が起こる。
『後漢書』(献帝紀)
★ここでは具体的な場所についての記述はなかった。
【12月】
献帝が、司空の趙温を罷免する。
『後漢書』(献帝紀)
【12月】
乙巳(いっし)の日(27日)
献帝が、衛尉の張喜(ちょうき)を司空に任ずる。
『後漢書』(献帝紀)
★李賢注によると「『献帝春秋』は(張喜の)『喜』の字を『嘉』の字に作る」という。
【12月】
献帝が、漢陽・上郡の両郡を分割して永陽郡を設置し、郷(県の管轄下に置かれた行政区画の単位)や亭(郷の管轄下に置かれた行政区画の単位)を属県とする。
『続漢書』(郡国志)の劉昭注に引く『献帝起居注』
【?月】
この年、袁術の指示を受けた孫策(そんさく)が、長江を渡る。その後、孫策は数年で、江東を手中に収めることになった。
『三国志』(魏書・武帝紀)
【?月】
この年、献帝が、太傅の馬日磾(ばじってい)と太僕の趙岐(ちょうき)を派遣し、関東(函谷関以東の地域)の将軍たちを和解させようとした。
『三国志』(魏書・袁紹伝〈えんしょうでん〉)
★この記事については、昨年(192年)8月の『後漢書』に同じものがあった。昨年の8月からこの年(193年)にかけ、各地の慰撫を続けていたと解釈すべきか?
ただ、この年の6月の『後漢書』には、太僕の朱儁が太尉に任ぜられたという記事がある。ということから、この年とは言っても、少なくとも6月以前を想定していると思われる。
【?月】
この年、琅邪王(ろうやおう)の劉容(りゅうよう)が薨去(こうきょ)した。
『後漢書』(献帝紀)
【?月】
この年、献帝が、(巴郡の充国県を)再び分割して南充国県を設置した。
『続漢書』(郡国志)の劉昭注に引く譙周(しょうしゅう)の『巴記』
特記事項
「この年(193年)に亡くなったとされる人物」
曹嵩(そうすう)・曹徳(そうとく)・劉虞(りゅうぐ)
「この年(193年)に生まれたとされる人物」
張温(ちょうおん)A ※あざなは恵恕(けいじょ)・駱統(らくとう)
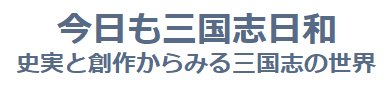


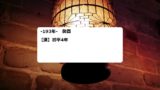












コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます