-269年- 己丑(きちゅう)
【晋】 泰始(たいし)5年 ※武帝(司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 (宝鼎〈ほうてい〉4年) → 建衡(けんこう)元年 ※帰命侯(孫晧〈そんこう〉)
月別および季節別の主な出来事
【01月】
癸巳(きし)の日(1日)
晋の司馬炎が、郡国の計吏・守相(太守と国相)・令長を重ねて戒め、任地の特産品の活用に努め、徒食や商いによる行きすぎた利益の追求を禁ずる。
『晋書』(武帝紀)
【01月】
丙申(へいしん)の日(4日)
晋の司馬炎が聴訟観(ちょうしょうかん)に臨み、自ら未決囚に再尋問を行い、多数の囚人を許して釈放させる。
『晋書』(武帝紀)
【01月】
丙申の日(4日)
2頭の青龍が、晋の滎陽(けいよう)に現れる。
『晋書』(武帝紀)
【01月】
呉の孫晧が、息子の孫瑾(そんきん)を皇太子に立てる。さらにほかの息子たちも、淮陽王と東平王に、それぞれ封じた。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【02月】「秦州の設置」
晋の司馬炎が、雍州の隴右(ろうゆう)5郡、涼州の金城郡、梁州の陰平郡をもって秦州を新設する。
『晋書』(武帝紀)
⇒02月
晋の司馬炎が、雍州・涼州・梁州の3州を分割して秦州を設置したうえ、胡烈(これつ)を秦州太守に任じ、異民族の対策にあたらせる。
『正史 三国志8』(小南一郎〈こみなみ・いちろう〉訳 ちくま学芸文庫)の年表
⇒02月
晋の司馬炎が、雍州・涼州・梁州の3州を分割して秦州を設置したうえ、胡烈を刺史に任ずる。
『正史三國志群雄銘銘傳 増補版』(坂口和澄〈さかぐち・わずみ〉著 光人社)の『三国志』年表
★『正史 三国志8』の年表にある「秦州太守」にいくらか引っかかっていた。『正史三國志群雄銘銘傳 増補版』の『三国志』年表では「刺史」とあるので、ここは「秦州刺史」とすべきだろう。
【02月】
辛巳(しんし)の日(20日)
2頭の白龍が、晋の趙国に現れる。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
辛巳の日(20日)
青州・徐州・兗州の3州で洪水が発生したため、司馬炎が使者を遣わし、被災民の救済にあたらせる。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
壬寅(じんいん)の日(?日)
晋の司馬炎が、尚書左僕射(しょうしょさぼくや)の羊祜(ようこ)を都督荊州諸軍事に、征東大将軍の衛瓘(えいかん)を都督青州諸軍事に、東莞王(とうかんおう)の司馬伷(しばちゅう)を鎮東大将軍・都督徐州諸軍事に、それぞれ任ずる。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
丁亥(ていがい)の日(26日)
晋の司馬炎が詔を下し、官吏の勤務評定が適切に行われていないという問題を採り上げる。そこで今後は、特に優れた者を列挙して毎年報告させ、自ら功労を見定めることにした。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
己未(きび)の日(?日)
晋の司馬炎が詔を下し、蜀の丞相を務めた諸葛亮(しょかつりょう)の孫である諸葛京(しょかつけい)に、(蜀の旧臣の中から)才能に従って吏を登用させる。
『晋書』(武帝紀)
【04月】
晋で地震が起こる。
『晋書』(武帝紀)
★ここでは具体的な場所についての記述はなかった。
【05月】
辛卯(しんぼう)の日(1日)、朔(さく)
鳳皇が晋の趙国に現れる。
『晋書』(武帝紀)
【05月】
辛卯の日(1日)、朔
晋の司馬炎が、交趾(こうし)・九真・日南の3郡を対象に、刑期が5年の罪人の刑を減免する。
『晋書』(武帝紀)
【06月】
晋の鄴奚官督(ぎょうけいかんとく)の郭廙(かくい)が上疏して5か条の諫言を述べ、その言葉が甚だ切実かつ率直だったため、司馬炎が屯留令(屯留県令)に抜てきする。
『晋書』(武帝紀)
【06月】
晋の西平出身の麴路(きくじ)が(諫言があるときに打ち鳴らす)登聞鼓を打ち、不吉な批判を長々と述べる。これを受けて担当官吏が上奏し、麴路を棄市(公開処刑)とするよう要請した。
だが、司馬炎は「(そのような諫言が出てくることは)自分の過失である」と言い、この件を不問に付した。
『晋書』(武帝紀)
【06月】
晋の司馬炎が、鎮軍将軍の官を廃止し、再び左将軍と右将軍の官を設置する。
『晋書』(武帝紀)
【07月】
晋の司馬炎が、群公を招いて直言を聴く。
『晋書』(武帝紀)
【09月】
彗星が紫宮(紫微宮)に現れる。
『晋書』(武帝紀)
【10月】
丙子(へいし)の日(19日)
晋の司馬炎が、汲郡太守(きゅうぐんたいしゅ)の王宏(おうこう)の治績をたたえ、穀物1千斛を下賜する。
『晋書』(武帝紀)
【10月】「呉の改元」
呉の孫晧が、「宝鼎」を「建衡」と改元したうえ、大赦を行う。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【11月】
晋の司馬炎が、弟の司馬兆(しばちょう)を追封したうえ、諡号(しごう)を贈って城陽哀王とし、皇子の司馬景度(しばけいたく)に跡(城陽王)を継がせる。
『晋書』(武帝紀)
★『晋書』(城陽王兆伝)には、司馬兆が10歳で夭折したとあるものの、いつのことだったかは書かれていない。
【11月】「陸凱(りくかい)の死」
呉の左丞相の陸凱が死去する。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【11月】
呉の孫晧が、監軍の虞汜(ぐし)、威南将軍の薛珝(せつく)、蒼梧太守(そうごたいしゅ)の陶璜(とうこう)らを遣わし、荊州から陸路を取らせる。
その一方、監軍の李勖(りきょく)と督軍の徐存(じょそん)らには建安から海路を取らせ、両者に、合浦で合流して晋の交趾を攻めるよう命じた。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【12月】
晋の司馬炎が詔を下し、州郡に勇猛で人並み外れて優れた者を推挙させる。
『晋書』(武帝紀)
【?月】
この年、郗鑒(ちかん)が生まれた(~339年)。
『正史 三国志8』の年表
特記事項
「この年(269年)に亡くなったとされる人物」
応貞(おうてい)・辛憲英(しんけんえい)・陸凱(りくかい)
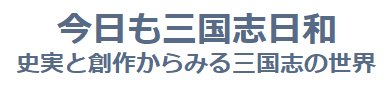

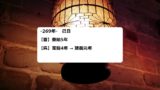













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます