-228年- 戊申(ぼしん)
【魏】 太和(たいわ)2年 ※明帝(曹叡〈そうえい〉)
【蜀】 建興(けんこう)6年 ※後主(劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 黄武(こうぶ)7年 ※大帝(孫権〈そんけん〉)
月別および季節別の主な出来事
【01月】
魏の司馬懿(しばい)が、蜀に内通しようとした新城の孟達(もうたつ)を攻め、これを斬殺したうえ、その首を洛陽に届ける。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★ここで「『魏略』にいう」として、「司馬懿が、孟達の部将の李輔(りほ)と孟達の甥の鄧賢(とうけん)を誘ったところ、鄧賢が城門を開き、司馬懿の軍勢を導き入れた。孟達は、包囲されること16日で敗北し、その首は洛陽の大通りの四つ辻で焼かれた」とある。
【01月】
魏の曹叡が、新城郡から上庸・武陵・巫(ふ)の3県を分割し、上庸郡としたうえ、錫県(せきけん)を錫郡とする。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【?月】「諸葛亮(しょかつりょう)の第一次北伐、街亭の戦い」
蜀の諸葛亮が、魏との国境を越えて軍を進める。天水・南安・安定の3郡の官吏と民衆が、諸葛亮に呼応した。
曹叡は、大将軍の曹真(そうしん)を遣わして関右の軍勢を統率するよう命じ、一斉に進発させた。
右将軍の張郃(ちょうこう)が、街亭で蜀軍を大破し、諸葛亮は逃走した。こうして蜀に呼応した3郡も再び平定された。
『三国志』(魏書・明帝紀)
⇒春
蜀の諸葛亮が出兵し、魏の祁山(きざん)を攻めたものの、勝つことはできなかった。
『三国志』(蜀書・後主伝)
⇒?月
蜀の諸葛亮が関中に出て、祁山まで兵を進める。これを受け、天水・南安・安定の3郡が魏に背き、蜀に付いた。
『正史 三国志8』(小南一郎〈こみなみ・いちろう〉訳 ちくま学芸文庫)の年表
⇒?月
蜀の馬謖(ばしょく)が、諸葛亮の指示を守らなかったため、街亭で魏軍に大敗する。これを受けて蜀は軍を退いた。
『正史 三国志8』の年表
⇒?月
蜀の諸葛亮が祁山に進出したものの、街亭で魏に敗れ、その責任を問うて馬謖を斬る。
『三国志全人名事典』(『中国の思想』刊行委員会編著 徳間書店)の関連略年表
【02月】
丁未(ていび)の日(17日)
魏の曹叡が長安に行幸する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★ここで『魏略』に載録するところの、明帝(曹叡)が天下に発布し、併せて益州に告示した文書として、「巴蜀の将吏・官吏・民のうち、諸葛亮に脅かされてやむなく従った者は、公卿以下みな降伏を許す」とある。
【03月】
呉の孫権が、息子の孫慮(そんりょ)を建昌侯に封ずる。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【03月】
呉の孫権が東安郡を廃止する。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【04月】
丁酉(ていゆう)の日(8日)
魏の曹叡が洛陽宮に還幸し、獄囚のうち、死刑囚以下の者を赦免する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★ここでは死刑囚以下の者とあったが、死刑囚以外の者とすべきではないのか?
★『後漢書』などを読むと、当時は死刑囚も含め、減刑や赦免が行われていたことがわかった。軽罪ならともかく、死刑にあたるような重罪まで赦免しないだろうと思っていたが、これは誤解だった。
★またここで「『魏略』にいう」として、「このとき『明帝(曹叡)がすでに崩御され、行幸に付き従った群臣が、雍丘王の曹植(そうしょく)を擁立した』というデマが広まった。洛陽では卞太后(べんたいこう)や群公はじめ、みな恐れおののいていた。しかし明帝(曹叡)が無事に還幸すると、みなこっそりと曹叡の顔色をうかがった。卞太后は、初めにデマを言いふらした者を調べようとしたが、明帝(曹叡)は、『世間の者がみな言っていたことですから、どうして調べることなどできましょうか』と言った」とある。
【04月】
乙巳(いっし)の日(16日)
魏の曹叡が、先の蜀軍撃退の勲功について、それぞれ格差をつけたうえ、封爵と領地の加増を行う。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【05月】
魏で大干ばつが起こる。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【05月】
呉の鄱陽太守の周魴(しゅうほう)が、呉に背いたように見せかけ、魏の曹休(そうきゅう)をおびき寄せる。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【06月】
魏の曹叡が詔を下す。「儒者を尊重して学問を大切にすることは、帝王の教化の根本である」として、「博士を選りすぐり、その才能に応じ、侍中や常侍に任命せよ。また郡国についても、貢士(こうし)には、経学に優れた者を優先して起用するようにさせよ」というもの。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【春または夏】
魏の田豫(でんよ)が通訳の夏舎(かしゃ)を、鮮卑の大人(たいじん。部族の有力者)の軻比能(かひのう)の娘婿である鬱築鞬(うつちくけん)のもとへ遣わす。しかし、夏舎は鬱築鞬に殺害されてしまった。
『三国志』(魏書・鮮卑伝)
【09月】「石亭の戦い」
魏の曹休が、諸軍をひきいて皖(かん)に到着する。曹休は、石亭で呉の陸議(りくぎ。陸遜〈りくそん〉)と戦って敗北した。
『三国志』(魏書・明帝紀)
⇒08月
呉の孫権が自ら皖口まで進み、陸遜に命じて部将たちを指揮させ、魏の曹休を襲わせる。陸遜は、石亭で曹休を徹底的に討ち破った。
『三国志』(呉書・呉主伝)
⇒08月
呉の周魴が、偽って魏に降伏を申し入れ、曹休を誘い込む。呉の陸遜が、石亭で曹休を討ち破り、曹休は、賈逵(かき)の援護を受けて何とか生還した。
『正史 三国志8』の年表
【09月】
乙酉(いつゆう)の日(29日)
魏の曹叡が、息子の曹穆(そうぼく)を繁陽王に封ずる。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【秋】
魏の田豫が、西部の鮮卑である蒲頭(ほとう)と泄帰泥(せつきでい。泄帰尼〈せつきじ〉)をひきいて長城から出撃し、鮮卑の大人の鬱築鞬を大破する。
『三国志』(魏書・鮮卑伝)
【10月】「曹休の死」
庚子(こうし)の日(14日?)
魏の大司馬の曹休が死去する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【10月】
魏の曹叡が詔を下す。公卿や側近たちに対し、「優れた大将を、それぞれひとりずつ推挙せよ」というもの。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【11月】
魏の司徒の王朗(おうろう)が死去する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【12月】「諸葛亮の第二次北伐」
蜀の諸葛亮が、魏の陳倉を包囲する。魏の曹真は、費曜(ひよう)らを遣わして蜀軍にあたらせた。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★『魏略』…郝昭(かくしょう)の活躍について。
⇒冬
蜀の諸葛亮が、再び散関を出て魏の陳倉を包囲したものの、兵糧が尽きたため撤退する。魏の王双(おうそう)がこれを追撃したところ、諸葛亮は反撃して王双を斬り、そのあと漢中に帰還した。
『三国志』(蜀書・後主伝)
【12月】
魏の曹叡が、公孫淵(こうそんえん)を遼東太守に任ずる。もともと遼東太守だった公孫恭(こうそんきょう)の兄の息子である公孫淵が、公孫恭から位を強奪したもの。
『三国志』(魏書・明帝紀)
⇒?月
この年、公孫淵が公孫恭を脅迫し、その位を奪い取った。明帝(曹叡)は、さっそく公孫淵に揚烈将軍・遼東太守の位を授けた。
『三国志』(魏書・公孫度伝〈こうそんたくでん〉)
【?月】
この年、鮮卑の大人の素利(そり)が死去した。息子が幼かったため、魏の曹叡は素利の弟の成律帰(せいりつき)を王(帰義王〈きぎおう〉)に立て、代わって配下を統率させた。
『三国志』(魏書・鮮卑伝)
【?月】「呂範(りょはん)の死」
この年、呉の大司馬の呂範が死去した。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【?月】
この年、呉の孫権が、合浦郡を珠官郡と改めた。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【?月】
この年、呉の将軍の翟丹(てきたん)が魏に奔った。
『三国志』(呉書・呉主伝)の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く『江表伝』
特記事項
「この年(228年)に亡くなったとされる人物」
王朗(おうろう)A ※あざなは景興(けいこう)・賈逵(かき)A ※賈充(かじゅう)の父・諸葛喬(しょかつきょう)・曹休(そうきゅう)・馬謖(ばしょく)・孟達(もうたつ)A ※あざなは子度(したく)・楊洪(ようこう)・駱統(らくとう)・呂範(りょはん)
「この年(228年)に生まれたとされる人物」
王蕃(おうはん)
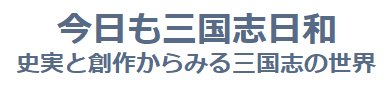














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます