-270年- 庚寅(こういん)
【晋】 泰始(たいし)6年 ※武帝(司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 建衡(けんこう)2年 ※帰命侯(孫晧〈そんこう〉)
月別および季節別の主な出来事
【01月】
丁亥(ていがい)の日(1日)、朔(さく)
晋の司馬炎が、(新年を迎えて)軒(けん)に臨むが、音楽の演奏は控える。
『晋書』(武帝紀)
【01月】
丁亥の日(1日)、朔
呉の将軍の丁奉(ていほう)が、晋の渦口(かこう)に侵入したものの、揚州刺史の牽弘(けんこう)が撃破する。
『晋書』(武帝紀)
【03月】
晋の司馬炎が、刑期が5年以下の罪人を赦免する。
『晋書』(武帝紀)
【春】
呉の万彧(ばんいく)が、武昌から建業へ戻る。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【春】
先(269年11月)に晋の交趾(こうし)攻めに向かっていた呉の李勖(りきょく)が、建安を経由する道程が難渋したことから、道案内にあたった部将の馮斐(ふうひ)を殺害したうえ、軍勢をまとめて帰還する。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【03月】
呉で天火(雷)が降り注ぎ、1万余戸が焼けて700人の死者が出る。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【04月】
2頭の白龍が、晋の東莞(とうかん)に現れる。
『晋書』(武帝紀)
【04月】「施績(しせき。朱績〈しゅせき〉)の死」
呉の左大司馬の施績(朱績)が死去する。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【05月】
晋の司馬炎が、寿安亭侯の司馬承(しばしょう)を南宮王に封ずる。
『晋書』(武帝紀)
【06月】
戊午(ぼご)の日(4日)
晋の秦州刺史の胡烈(これつ)が、万斛堆(ばんこくたい)の反虜を攻め、力戦の末に戦死する。
これを受けて司馬炎が詔を下し、尚書の石鑒(せきかん)を行安西将軍・都督秦州諸軍事に任じ、奮威護軍の田章(でんしょう)とともに討伐にあたらせる。
『晋書』(武帝紀)
⇒06月
晋の胡烈が、鮮卑の討伐にあたったものの、返り討ちに遭って戦死する。
『正史 三国志8』(小南一郎〈こみなみ・いちろう〉訳 ちくま学芸文庫)の年表
【07月】
丁酉(ていゆう)の日(14日)
晋の司馬炎が、隴右(ろうゆう)の5郡で侵攻の被害に遭った者の租賦(そふ)を免除し、自活できない者には穀物を貸し付ける。
『晋書』(武帝紀)
【07月】
乙巳(いっし)の日(22日)
晋の城陽王の司馬景度(しばけいたく)が薨去(こうきょ)する。
『晋書』(武帝紀)
【07月】
乙巳の日(22日)
晋の司馬炎が詔を下し、泰始(265年)以来、秘書省の官吏がすべての重要事項を記録し、その副本を作成していることに触れ、今後も重要事項があるたび、適切につづり集めることを常務とさせる。
『晋書』(武帝紀)
【07月】
丁未(ていび)の日(24日)
晋の司馬炎が、汝陰王の司馬駿(しばしゅん)を鎮西大将軍・都督雍涼二州諸軍事に任ずる。
『晋書』(武帝紀)
【09月】
大宛が晋に来朝し、汗血馬を献上する。また焉耆(えんぎ)も来朝し、特産品を献上する。
『晋書』(武帝紀)
【11月】
晋の司馬炎が辟雍(天子が建てた太学)に行幸し、郷飲酒(きょういんしゅ)の礼を執り行う。その際、太常・博士・太学生にそれぞれ差をつけ、帛(きぬ)・牛肉・酒を下賜する。
『晋書』(武帝紀)
★『角川 新字源 改訂新版』(小川環樹〈おがわ・たまき〉、西田太一郎〈にしだ・たいちろう〉、赤塚忠〈あかつか・きよし〉、阿辻哲次〈あつじ・てつじ〉、釜谷武志〈かまたに・たけし〉、木津祐子〈きづ・ゆうこ〉編 KADOKAWA)には、郷飲酒について、「周代、地方から優秀な人物を君主に推薦するとき、郷大夫(郷の長官)が主人となって開く送別の宴。また、郷大夫が郷村の人を集めて、賢者をとうとび老人を養う儀式を行う酒もり。」との説明があった。
【11月】
晋の司馬炎が、皇子の司馬柬(しばかん)を汝南王に封ずる。
『晋書』(武帝紀)
【12月】「孫秀(そんしゅう)の投降」
呉の夏口督・前将軍の孫秀が、軍勢をひきいて晋に来降したため、司馬炎が、驃騎将軍・開府・儀同三司(三公待遇)に任じたうえ、会稽公に封ずる。
『晋書』(武帝紀)
⇒?月
この年、呉の都督の孫秀が晋に逃亡した。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【12月】
戊辰(ぼしん)の日(17日)
晋の司馬炎が、再び鎮軍(鎮軍将軍)の官を設置する。
『晋書』(武帝紀)
【?月】
この年、呉の殿中列将の何定(かてい)が孫晧に上言し、「少府の李勖は、みだりに馮斐を殺害し、勝手に軍勢をひきいて帰還いたしました」と述べる。これを受けて、李勖と徐存(じょそん)の一家眷族(けんぞく)はみな誅殺された。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【?月】
この年、呉の何定が、兵5千をひきいて長江をさかのぼり、夏口で巻き狩りを行った。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【?月】
この年、呉の孫晧が大赦を行った。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【?月】
この年、呉の孫晧の左夫人の王氏(おうし)が死去した。
孫晧は悲しみと思慕に耐えられず、朝夕、柩(ひつぎ)のそばで哭(こく)し、数か月間も人々の前に姿を見せなかった。
そのため民の間では、「孫晧は死んでしまったのだ」という者もあり、「孫奮か、上虞侯の孫奉(そんほう)か、どちらかが即位するだろう」などと、根も葉もないうわさが広まった。
孫奮の母である仲姫(ちゅうき。仲氏)の墓は豫章にあったが、豫章太守の張俊(ちょうしゅん)は、これらのうわさが本当のことかもしれないと考え、「仲姫の墓を掃除するように」と命じた。
このことを聞いた孫晧は、張俊を車裂きにしたうえ、その一族も皆殺しにした。さらに孫奮とその息子たち5人も誅殺し、封国が廃された。
『三国志』(呉書・孫奮伝)
★この記事だけではわかりにくかったが、『三国志』(呉書・孫晧伝)によれば、孫奮は少なくとも鳳皇(ほうおう。鳳凰)3(274)年までは、章安侯として生きていたことがわかる。なので、この年(270年)のうちに誅殺されたわけではないこともわかる。
★この記事について再度調べたところ、確かに『三国志』(呉書・孫奮伝)には、この年(建衡2〈270〉年)に「孫晧の左夫人であった王氏の死」 「孫晧、悲しみと思慕のため数か月間、人前に姿を見せず」 「孫晧は死んでしまったのだといううわさ」 「孫奮か、上虞侯の孫奉か、どちらかが即位するだろうといううわさ」という具合に展開する記事があり、「張俊とその一族の皆殺し」とともに、「孫奮と息子5人の誅殺、封国の廃止」で決着したことになっていた。
ところが、一方で『三国志』(呉書・孫晧伝)には、建衡2(270)年に上のうわさ絡みの記事がなく、後の鳳皇(鳳凰)3(274)年に、「会稽郡で章安侯の孫奮が天子になるだろうとの妖言が流行った……」という記事が出てくる。
となると、その時点(274年)で章安侯の孫奮は当然存命しているわけで、両者の記事にある時期が大きく異なっていることがわかった。このあたりがはっきりしないと、孫奮の死が何年のことなのかもわからない。
★『江表伝』…孫奮父子の最期についての話。
★裴松之(はいしょうし)の考え…(『江表伝』の話について)「この話は現実的に見ると道理に合わない」とある。
【?月】
この年、劉琨(りゅうこん)が生まれた(~317年)。
『正史 三国志8』の年表
特記事項
「この年(270年)に亡くなったとされる人物」
王氏(おうし)F ※孫晧(そんこう)の妻・胡烈(これつ)・司馬景度(しばけいたく)・朱績(しゅせき。施績〈しせき〉)・譙周(しょうしゅう)・孫奉(そんほう)?・羅憲(らけん)
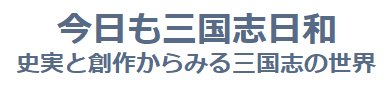

















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます