先に魏公に封ぜられた曹操(そうそう)だったが、彼の追従者たちからは、さらに魏王に爵位を進めるべきだという声が上がる。
このことはすぐに実現をみなかったものの、いよいよ不安を募らせた献帝は、皇后の父である伏完(ふくかん)のもとへ密書を届けさせた。こうした動きをいち早くつかんだ曹操は――。
第206話の展開とポイント
(01)許都(きょと)
魏の大軍が呉へ押し寄せてくるとの飛報は、うわさだけにとどまった。噓でもなかったが、早耳の誤報だったのである。
この(建安〈けんあん〉19〈214〉年の)冬を期して、曹操が宿望の呉国討伐を果たそうとしたのは事実で、すでに南下の大部隊を編制し、各部の諸大将も内々決定していた。
ところが、ここで参軍(さんぐん)の傅幹(ふかん)から長文の上書がある。
「今はその時ではないこと」「漢中(かんちゅう)の張魯(ちょうろ)、蜀の劉備(りゅうび)などの動向の重大性」「呉の新城秣陵(まつりょう)の堅固と長江戦の至難」「魏の内政拡充と臨戦態勢の整備」といった事柄を挙げての諫言だった。
★呉の新城秣陵の堅固というのはいくらか引っかかる。これは建業(けんぎょう)に築かれた石頭城(せきとうじょう)を指しているのだろうか? 石頭城については先の第193話(01)を参照。
曹操も出動を思い直し、なおしばらくは内政文治にもっぱら意を注ぐことにする。新たに文部の制を設け、諸所に学校を建てて教学振興を図った。こうして彼が少し善政を布くと、すぐに誇大にたたえ、お太鼓を叩く連中もできてくる。
侍郎(じろう)の王粲(おうさん)・和洽(かこう)・杜襲(としゅう)などという軽薄輩で、「曹丞相(そうじょうしょう。曹操)は、もう魏王の位に即かれるべきだ。魏王になられたところで何の不思議もない」と運動し始めた。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第66回)では、王粲・杜襲・和洽に加えて衛凱(えいかい。正しくは衛覬〈えいき〉)の名も見え、みな侍中(じちゅう)ということになっている。吉川『三国志』では衛凱(衛覬)を使っていない。
うわさを聞いた荀攸(じゅんゆう)は、お太鼓連をたしなめて言った。
「先に九錫(きゅうしゃく)の栄を受けて、魏公の金璽(きんじ)を持たれたのは、いわゆる人臣の位を極めたというもの」
★曹操が魏公に封ぜられて九錫を受けたことについては、先の第193話(02)を参照。
「そのうえなお魏王の位に進まれたら、俗に言う天井を突き、人心の反映は決してよい結果をもたらさないでしょう。あなた方にしても、それでは贔屓(ひいき)の引き倒しということになろう」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「王は漢代における最上の爵位。高祖劉邦(りゅうほう)により、劉氏一族のみに限ると定められていた」という。
これが人づてに曹操の耳に入る。もちろんその間に、為にする者の肚(はら)も入っているから、曹操は非常な不快を感じた。
「荀攸もまた、荀彧(じゅんいく)に倣おうとするのか。馬鹿な奴だ!」
非常に立腹して、そう罵ったと聞こえたから、それをまた人づてに耳にした荀攸は、いたく気に病む。そして門を閉じ、自ら謹慎したまま、その冬に病死してしまう。
「58歳で世を去ったか。彼も功臣のひとりだったが――」
死んでみると、曹操は痛惜に堪えないようにつぶやき、盛んな葬祭を執り行った。
(02)許都 内裏(天子の宮殿)
こうして魏王に即く問題は、しばらく沙汰やみになっていたが、このことは宮廷の諫議郎(かんぎろう)の趙儼(ちょうげん)から、献帝の耳にも入っていた。
★『三國志人物事典(中)』(渡辺精一〈わたなべ・せいいち〉著 講談社文庫)によると、「(『三国志演義』の趙儼は)弘治本(こうじぼん。嘉靖本〈かせいぼん〉)にのみ登場する人物」だという。
確かに史実における趙儼は、魏の曹芳(そうほう)の時代に司空(しくう)・都郷侯(ときょうこう)まで昇り、正始(せいし)6(245)年に亡くなっている。ここで出てきた諫議郎の趙儼のくだりは創作であるため、一見しただけでは(正史『三国志』に見える)趙儼と同じ人物なのかわかりにくかった。
ところが、ほどなく献帝のもとに、趙儼が市へ引き出されて斬られたとの報告が届く。
伏皇后(ふくこうごう)は、父の伏完に決意のほどをそっと伝え、曹操を刺す謀(はかりごと)を巡らせてもらうよう勧める。使いには穆順(ぼくじゅん)が確かだとも。
★ここで名の挙がった穆順は、先の第28話(05)で出てきた穆順とは別人。
ついに献帝は、厳しい監視の目を忍んで秘勅の一文をしたためる。これを朝臣の穆順に預け、伏完の屋敷へ届けさせた。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、献帝の秘勅ではなく、伏皇后が父あてに書いた手紙を密かに届けさせたとある。
忠節無二な穆順は秘勅を髻(もとどり。髪の毛を頭の上で束ねたところ)の中に隠し、この命がけの使いのため一夜、禁門(宮門)から出た。
朝臣のうちにも曹操の回し者たる、いわゆる見る目や嗅(か)ぐ鼻はたくさんいる。すぐに密告し、曹操の耳へこう伝えた者があった。
「何かそそくさした様子で穆順が内裏を出て、伏完の屋敷へ使いに行ったようです」
勘のよい曹操には、何かピンと響くものがあったに違いない。わずかな武士を連れて内裏の門にたたずみ、穆順が戻るのを待っていた。
深更(深夜)になり、穆順は何も知らずに帰ってくる。門の衛士には、出るときに賄賂を渡してあった。辺りに人影はなく、すたすたと内裏の門へ差しかかる。すると不意に物陰から呼び止める声がした。
曹操の姿を見、ぞっと毛穴をよだてる穆順。夕刻から皇后さまがにわかに腹痛を催されたため、命を受けて医師を求めに行ったのだと言い繕う。
しかし曹操は信じず、武士に命じて穆順の体を改めさせる。だが、衣服を剝ぎ、足の先まで調べたものの、一物も出てこない。とがめるかどもなく、曹操は彼を放した。
虎の口を逃れたように、穆順は衣服を着直すとすぐ走りかけた。ここでかぶっていた帽子が夜風に落ちる。あわてて拾いかけると曹操が再び呼び止め、自ら帽子を子細に改めた。
帽子の中からも何も出ない。曹操が投げ返すと穆順は両手に受け、真っ青になった顔の上に帽子をかぶった。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、このとき穆順が帽子を前後逆にしてかぶったため、曹操は不審に思い、左右の者に髪の毛の中まで探らせたとある。
曹操は三度呼び止める。今度は穆順がかぶり直した帽子を引きちぎり、その下の髻を髪の根まで搔(か)き分けた。
曹操は舌を鳴らす。一通の紙片が現れた。細字で綿密に書いてある。伏完の筆跡で、娘の伏皇后に宛てたものだった。
穆順は拷問にかけられて夜通し責められたが、ひと言も吐かない。一方で伏完の屋敷を襲った兵士たちは、献帝の内詔を発見して持ち帰った。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、伏完の屋敷から見つかったのは伏皇后直筆の手紙。
曹操は冷然と命ずる。
「伏完以下、彼の三族を召し捕って獄につなげ。縁故の者はひとりも余すな」
★井波『三国志演義(2)』の訳者注によると、「(三族については)諸説あるが、漢代において三族皆殺しの対象となるのは、父母・妻子・兄弟姉妹である」という。
さらに御林将軍(ぎょりんしょうぐん)の郗慮(ちりょ)にも、内裏へ入って伏皇后の璽綬(じじゅ。印と組み紐〈ひも〉)を取り上げ、平人(ひらびと)に貶(おと)して罪を明らかにせよと命じた。
武装した御林の兵(近衛兵)は、郗慮を先頭に内裏へなだれ込む。伏皇后はいち早く宮女に助けられ、内裏の朱庫に隠れていた。ここには二重壁があり、壁の中へ身を塗り隠してしまう仕掛けがあった。
郗慮は尚書令(しょうしょれい)の華歆(かきん)を呼んで協力を促し、ともに朱庫の扉を破って内部へ躍り込む。
伏皇后は見えず、郗慮は外へ戻ろうとしたが、華歆は職掌柄ここの構造を知っていた。剣を抜いて壁を切り開くと、たちまち鮮血を吹き、その中から伏皇后が転(まろ)び出る。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、このあたりで華歆と管寧(かんねい)の逸話に触れていた。だが、吉川『三国志』では管寧を使っていない。
伏皇后が素足のまま引っ立てられてくると、曹操はにらみつけて言った。
「われかつて汝(なんじ)を殺さざるに、かえって、汝われを殺さんと謀る。この結果は今に思い知らせてやる」
★ここにある「われかつて汝を殺さざるに……」については、先の第95話(03)を参照。董承(とうじょう)らが曹操殺害を計画して露見した事件に絡み、董承の娘という設定の董貴妃(とうきひ)は自害させられたのに、伏皇后はそうならなかったという意味合いだと思う。
曹操が武士に命じて、鞭(むち)や棒で乱打を加えさせると、伏皇后は悶(もだ)え苦しみながら、ついに息絶えてしまった。
その悲鳴や曹操の罵声は、外殿の廊まで聞こえてきたほど。献帝は髪をつかんで身を震わせ、天へ叫び、地へ昏絶(こんぜつ)した。
「こんなことが、天日の下にあってもいいものか。この地上は、人間の世か? 獣の世か?」
血も吐かんばかりなありさまに、郗慮は武士の手を借りて無理やり献帝を抱え、秘宮の内へ閉じ込めた。
曹操は毒に酔える人のごとく、もうどのようなことでも平然とやってのけた。伏完の一門から穆順の一族縁類の端まで、総計二百何十人という男女老幼を半日の間に残らず捕らえ、宮衙門(きゅうがもん。宮殿の役所の門)の街辻(まちつじ)で首斬ってしまった。
時は建安19(214)年の冬11月、天も悲しむか、曇暗許都の昼を閉じ、枯れ葉の啾々(しゅうしゅう。ここでは枯れ葉が音を立てている様子の意か?)と御林に泣き、幾日も幾日も衙門(役所の門)の冷霜は解けなかった。
曹操は一日、朝へ出て、幽愁の裡(うち)に閉じ籠っている献帝に奏する。
「陛下。承れば供御(くご。天子の御用にあてる)の物も連日お上がりにならない由ですが、どうかもう宸襟(しんきん)を安んじていただきたい」
「臣も何とてこれ以上、情けのない業をいたしましょう。本来、無情は曹操の好んですることではないのですが、ああいう問題が表面化しては、捨て置くわけにまいらないではありませんか」
そして、自分の娘を強いて皇后に薦めた。献帝に拒む力はなく、翌(建安20〈215〉年の)春正月、晴れて曹操の娘は宮中に入り、皇后の位に即いた。
それとともに曹操もまた、国舅(こっきゅう。天子の母方の親類や妻の一族である父兄)という容易ならぬ身分を加えた。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、曹操の娘はこのとき宮中へ入ったのではなく、すでに宮中へ入って貴人の位にあったことが語られていた。
管理人「かぶらがわ」より
曹操の増長ぶりが強調されていた第206話。伏皇后の件はともかく、荀攸の態度や死因についてはまったくの創作です。
曹操のこういう一面だけを取り上げ、「残虐だ」「悪だ」などと決めつけるのはまずいと思います。立場のある者が立場のある者を謀って失敗すれば、この状況で見逃してもらえるはずがありません。
それだけの覚悟と覚悟のぶつかり合いの結果なのですから、「伏皇后はお気の毒」で「曹操はひどい」という片づけ方はないでしょう。もし献帝が善政を布いていたというなら、また話は変わってきますけど……。

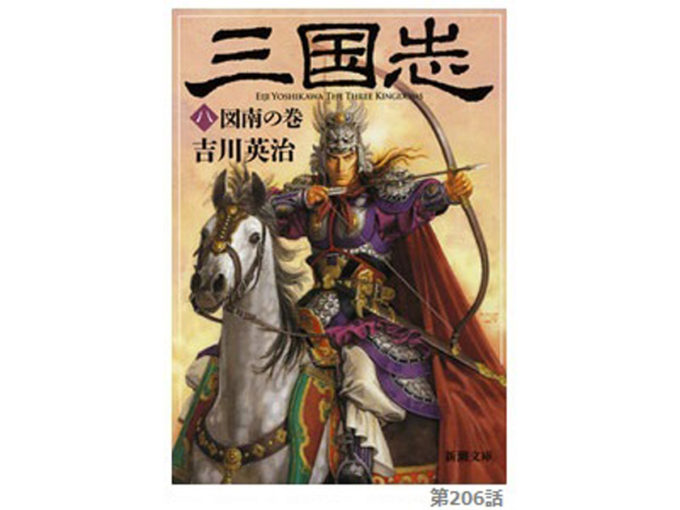


















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます