-262年- 壬午(じんご)
【魏】 景元(けいげん)3年 ※元帝(曹奐〈そうかん〉)
【蜀】 景耀(けいよう)5年 ※後主(劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 永安(えいあん)5年 ※景帝(孫休〈そんきゅう〉)
月別および季節別の主な出来事
【01月】
蜀の西河王の劉琮(りゅうそう)が薨去(こうきょ)する。
『三国志』(蜀書・後主伝)
【02月】
魏の軹県(しけん)の井戸の中に青龍が現れる。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【02月】
呉で火災があり、白虎門(建業城の西門)の北楼が焼ける。
『三国志』(呉書・孫休伝)
【04月】
粛慎国が魏に使者を遣わし、二重三重の通訳を重ねて入貢する。
この報告は遼東郡から届いたもので、献上された品として、長さ3尺(せき)5寸の弓30張、長さ1尺8寸の楛矢(こし)、弩300、獣皮、獣骨、鉄類から作った鎧20領、貂(テン)の皮400枚とある。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
★『正史 三国志1』(今鷹真〈いまたか・まこと〉、井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま学芸文庫)の訳者注によると、「楛は、にんじんぼくに似た落葉高木。矢を作るのに用いた」という。
★弩の数え方について、訳者は「300個の弩」とされていたが、どうもスッキリしない。とりあえず「弩300」とだけしておく。原文には「石砮(せきど)300枚」とあるので、弩というより、砮(鏃〈やじり〉にする石)のイメージかとも思われる。
【07月】
呉の孫休のもとに、「新都郡の始新で黄龍が現れた」との報告が届く。
『三国志』(呉書・孫休伝)
【08月】
壬午(じんご)の日(13日)
呉で大雨が降って雷も鳴り、川や谷があふれる。
『三国志』(呉書・孫休伝)
【08月】
乙酉(いつゆう)の日(16日)
呉の孫休が、朱氏(しゅし)を皇后に立てる。
戊子(ぼし)の日(19日)
呉の孫休が、息子の孫ワン(そんわん。雨+單)を皇太子に立てたうえ、大赦を行う。
『三国志』(呉書・孫休伝)
★『呉録』…孫休の詔。孫休が、4人の息子たちの名とあざなを定めた話。
★裴松之(はいしょうし)の考え…『左伝』(桓公2年)の師服(しふく)の言葉を引き、孫休が類例のない文字を作り出し、典拠のない音を定めたことを非難している。
【10月】
蜀の姜維(きょうい)が、魏の洮陽(とうよう)に侵攻する。魏の鎮西将軍の鄧艾(とうがい)が応戦し、侯和(こうか)で撃破。姜維は逃走した。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
⇒?月
この年、蜀の姜維が、再び軍勢をひきいて魏の侯和に出撃したものの、魏の鄧艾に撃破されて撤退し、沓中(とうちゅう)に留まった。
『三国志』(蜀書・後主伝)
【10月】
呉の孫休が、衛将軍の濮陽興(ぼくようこう)を丞相に、廷尉の丁密(ていみつ)と光禄勲の孟宗(もうそう。孟仁〈もうじん〉)を左右の御史大夫に、それぞれ任ずる。
『三国志』(呉書・孫休伝)
【?月】
このころ、呉の張布(ちょうふ)が朝廷で権力を振るう。
『正史 三国志8』(小南一郎〈こみなみ・いちろう〉訳 ちくま学芸文庫)の年表
【?月】
この年、魏の曹奐が詔を下し、亡き軍祭酒の郭嘉(かくか)を、太祖(曹操〈そうそう〉)の廟の前庭に祭った。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【?月】
この年、呉の孫休が、察戦の官にある者を交趾(こうし)へ遣わし、孔雀(クジャク)と大猪(オオイノシシ)を調達させた。
『三国志』(呉書・孫休伝)
★裴松之の考え…察戦というのは呉の官名である。現在(当時)、揚都には察戦巷(さっせんこう)という地名がある。
【?月】
この年、司馬昭(しばしょう)が嵆康(けいこう)を殺害した(223年~)。
『正史 三国志8』の年表
【?月】「陸雲(りくうん)の誕生」
この年、陸雲が生まれた(~303年)。
『正史 三国志8』の年表
特記事項
「この年(262年)に亡くなったとされる人物」
嵆康(けいこう)・劉琮(りゅうそう)A ※劉禅(りゅうぜん)の息子
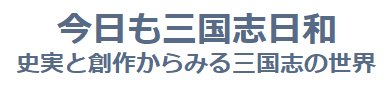














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます