-266年- 丙戌(へいじゅつ)
【晋】 泰始(たいし)2年 ※武帝(司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 (甘露〈かんろ〉2年) → 宝鼎(ほうてい)元年 ※帰命侯(孫晧〈そんこう〉)
月別および季節別の主な出来事
【01月】
丙戌(へいじゅつ)の日(7日)
晋の司馬炎が、兼侍中の侯史光(こうしこう)らに持節させ四方に派遣し、各地の風俗を視察させたうえ、経典にない祭祀を廃止する。
『晋書』(武帝紀)
【01月】
丁亥(ていがい)の日(8日)
晋の担当官吏が七廟の建立を要請したが、司馬炎は労役が重くなることを考慮して許可しなかった。
『晋書』(武帝紀)
【01月】
庚寅(こういん)の日(11日)
晋の司馬炎が、鶏鳴歌(けいめいか)を廃止する。
『晋書』(武帝紀)
★鶏鳴歌の補足が特になかったため、詳細はわからなかった。
【01月】
辛丑(しんちゅう)の日(22日)
晋の司馬炎が、景帝(司馬師〈しばし〉)の夫人である羊氏(ようし。羊徽瑜〈ようきゆ〉)を尊んで景皇后とし、その宮を弘訓(こうくん)とする。
『晋書』(武帝紀)
【01月】
丙午(へいご)の日(27日)
晋の司馬炎が、楊氏(ようし。楊艶〈ようえん〉)を皇后に立てる。
『晋書』(武帝紀)
★ここで立てられた楊氏(楊艶。武元楊皇后)は泰始10(274)年に崩御した。その後、咸寧(かんねい)2(276)年に新たに立てられた楊氏(楊芷〈ようし〉。武悼楊皇后)とは別人。一応補足しておく。

【01月】
呉の孫晧が、大鴻臚(だいこうろ)の張儼(ちょうげん)と五官中郎将の丁忠(ていちゅう)を晋へ遣わし、司馬昭(しばしょう)の死を弔問させる。この晋からの帰路、張儼が病死した。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
★『呉録』…張儼について。
【02月】
晋の司馬炎が、漢の宗室の禁錮(きんこ。任官禁止処分)を解く。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
己未(きび)の日(11日)
晋の常山王の司馬衡(しばこう)が薨去(こうきょ)する。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
己未の日(11日)
晋の司馬炎が詔を下し、県侯の次子を亭侯とし、郷侯の次子を関内侯とし、亭侯の次子を関中侯とし、それぞれ本家の封邑の10分の1を食(は)ませる。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
丁丑(ていちゅう)の日(29日)
晋の司馬炎が、宣皇帝(司馬懿〈しばい〉)を郊祀して天に配し、文皇帝(司馬昭)を明堂に宗祀して上帝に配する。
『晋書』(武帝紀)
【02月】
庚午(こうご)の日(22日。上の記事と干支〈かんし〉が前後しているが……)
晋の司馬炎が詔を下し、自身の過ちを指摘してくれる人材を選び、侍中や常侍を兼務させる。
『晋書』(武帝紀)
【03月】
戊戌(ぼじゅつ)の日(20日)
呉の孫晧が(晋の文帝〈司馬昭〉のために)遣わした弔問の使者が到着したので、担当官吏が司馬炎に、返答の詔書の作成を上奏する。
しかし司馬炎は、孫晧の使者が出発した時点では、まだ国慶(魏から晋への禅譲)を知りようがなかったとし、詔書ではなく通常の書によって返答させた。
『晋書』(武帝紀)
【05月】
戊辰(ぼしん)の日(?日)
晋の司馬炎が詔を下し、陳留王(曹奐〈そうかん〉。魏の元帝)への敬意を示すため、重要な事柄でない場合は(陳留王本人ではなく配下の)王官から上表させることにする。
『晋書』(武帝紀)
【05月】「王沈(おうしん)の死」
壬子(じんし)の日(6月5日?)
晋の驃騎将軍・博陵公の王沈が死去する。
『晋書』(武帝紀)
【06月】
壬申(じんしん)の日(25日)
晋の済南王の司馬遂(しばすい)が薨去する。
『晋書』(武帝紀)
【07月】
辛巳(しんし)の日(5日)
晋の司馬炎が太廟を造営し、荊山で木を伐採し、華山から石を採取する。また、12本の銅柱を鋳造し、黄金を用いて塗り、様々な意匠を彫りつけ、明珠で飾らせる。
『晋書』(武帝紀)
【07月】
戊戌(ぼじゅつ)の日(22日)
晋の譙王(しょうおう)の司馬遜(しばそん)が薨去する。
『晋書』(武帝紀)
【07月】
丙午(へいご)の日(30日)、晦(かい)
日食が起こる。
『晋書』(武帝紀)
【08月】
丙辰(へいしん)の日(10日)
晋の司馬炎が、右将軍の官を廃止する。
『晋書』(武帝紀)
★この記事の後に、これまで司馬炎は漢や魏の制度を踏襲していたが、文帝(父の司馬昭)の埋葬を終えて喪服を脱ぐ時期になっても脱がず、喪中のような振る舞いを続けたという記事が置かれている。
【08月】
戊辰の日(22日)
晋の担当官吏が、司馬炎に喪服を脱いで食膳を(通常のものに)戻すよう上奏したものの、許可されなかった。
司馬炎は葬礼を終えると初めて、装束や食膳を元に戻した。皇太后が崩じた際も同様にした。
『晋書』(武帝紀)
★ここでいう皇太后は、司馬昭の正室で司馬炎の生母である王元姫(おうげんき。文明王皇后)。王元姫は晋の泰始4(268)年3月に崩御した。
【08月】「呉の改元」
呉の孫晧のもとに、「各地で大きな鼎(かなえ)が発見された」との報告が届く。そこで孫晧は、「甘露」を「宝鼎」と改元したうえ、大赦を行った。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【08月】
呉の孫晧が、陸凱(りくかい)を左丞相に、常侍の万彧(ばんいく)を右丞相に、それぞれ任ずる。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【09月】
乙未(いつび)の日(20日)
諫官を兼任している晋の散騎常侍の皇甫陶(こうほとう)と傅玄(ふげん)が、司馬炎に上書して諫め、同様に担当官吏も上奏して(漢魏の制度を超えた服喪の)中止を求める。
これに対して司馬炎は詔を下し、今回の件を詳しく評議するよう命じた。
『晋書』(武帝紀)
【09月】
戊辰の日(23日)
晋の担当官吏が上奏し、「大晋は三代の皇帝が継承し、舜や禹の跡を踏み、天の時に応じて魏から禅譲されました。ですから前代の正朔(せいさく)と服色を用い、みな舜が堯に従った故事のようになさってください」と述べる。
司馬炎は、この上奏を受け入れた。
『晋書』(武帝紀)
【10月】
丙午の日(1日)、朔
日食が起こる。
『晋書』(武帝紀)
【10月】
丁未(ていび)の日(2日)
晋の司馬炎が詔を下し、いにしえの舜や禹の埋葬時の作法や、自身の祖先の簡素を旨とする考え方に鑑み、陵墓を移す先の10里以内の住民を強制移住させる慣行をやめる。
『晋書』(武帝紀)
【10月】
呉の永安で、山賊の施但(したん)らが数千人の徒党を集める。
施但らは、孫晧の異母弟である永安侯の孫謙(そんけん)を強迫し、烏程まで同行させた。そして、孫和(そんか)の陵に副葬されていた楽器や曲蓋(柄が曲がった貴人の儀杖用〈ぎじょうよう〉の傘)を奪い取ったりした。
施但らが建業まで来たとき、その徒党は1万余人にもなっていた。これを呉の丁固(ていこ)と諸葛靚(しょかつせい)が迎え撃ち、牛屯で激戦になった。施但らは敗走し、取り残された孫謙は保護されたものの、自殺してしまった。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
★『呉録』…永安は、今(当時)の武康県である。
★『漢晋春秋』…望気者(普通の人には見えない、王者の気などを見ることができる人物)が孫晧に言ったことと、武昌に遷都したことについての話。
【10月】
呉の孫晧が、会稽郡を分割して東陽郡を、呉郡と丹楊郡を分割して呉興郡を、それぞれ設置する。また、零陵郡の北部を邵陵郡(しょうりょうぐん)とした。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
★裴松之注(はいしょうしちゅう)…孫晧の詔。呉興郡を設置する意義について。
【11月】「倭国の使者」
己卯(きぼう)の日(5日)
倭人が晋に来朝し、特産品を献上する。
『晋書』(武帝紀)
⇒?月
この年、倭の女王が晋に使者を遣わし、献上品を捧げた。
『日本書紀』(神功皇后紀〈じんぐうこうごうぎ〉)の注
★この注は『晋起居注』から引かれており、李軌(りき)の『晋泰始起居注』と同じものだと思われる。また、このときの倭の女王は卑弥呼(ひみこ)ではなく、壱与(いよ)であるとの見方が主流になっている。
【11月】
己卯の日(5日)
晋の司馬炎が、円丘と方丘を南北郊に併せ、二至の祭祀を二郊に統合する。
『晋書』(武帝紀)
【11月】
己卯の日(5日)
晋の司馬炎が、山陽公国の督軍を廃止し、その禁制を解く。
『晋書』(武帝紀)
【11月】
己丑(きちゅう)の日(15日)
晋の司馬炎が、景帝(司馬師)の夫人だった夏侯氏(かこうし。夏侯徽〈かこうき〉)を追尊し、景懐皇后とする。
『晋書』(武帝紀)
★夏侯徽は、夏侯尚(かこうしょう)と徳陽公主(曹操の娘)の娘、夏侯玄(かこうげん)の妹。司馬師の最初の正室で、魏の青龍(せいりょう)2(234)年に死去した。
【11月】
辛卯(しんぼう)の日(17日)
晋の司馬炎が、祖先の位牌を太廟へ移す。
『晋書』(武帝紀)
【12月】
晋の司馬炎が、農官を廃止して郡県とする。
『晋書』(武帝紀)
【12月】「呉の遷都」
呉の孫晧が、武昌から建業へ遷都する。衛将軍の滕牧(とうぼく)が武昌に留まり、旧都の守備にあたった。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【12月】
呉の陸凱が、大司馬の丁奉(ていほう)や御史大夫の丁固と謀り、孫晧の廃位を企てる。しかし、左将軍の留平(りゅうへい)の協力が得られなかったため、この計画は実行されずに終わった。
『三国志』(呉書・陸凱伝)
★『呉録』…この計画が立ち消えに至った話。
【?月】
この年、各地の郡国に合わせて鳳凰6羽、青龍10頭、黄龍9頭、麒(き)と麟(りん)それぞれ1頭が現れた。
『晋書』(武帝紀)
【?月】
この年、王敦(おうとん)が生まれた(~324年)。
『正史 三国志8』の年表
特記事項
「この年(266年)に亡くなったとされる人物」
王沈(おうしん)・王蕃(おうはん)・司馬衡(しばこう)・司馬遂(しばすい)・司馬遜(しばそん)・孫謙(そんけん)A ※孫和(そんか)の息子
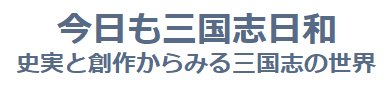


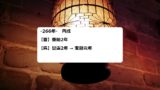













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます