-265年- 乙酉(いつゆう)
【晋】 泰始(たいし)元年 ※武帝(司馬炎〈しばえん〉)
【魏】 咸熙(かんき)2年 ※元帝(曹奐〈そうかん〉) → 晋に禅譲し滅亡
【呉】 (元興〈げんこう〉2年) → 甘露(かんろ)元年 ※帰命侯(孫晧〈そんこう〉)
月別および季節別の主な出来事
【02月】
甲辰(こうしん)の日(19日)
魏の曹奐に、胊䏰県(くじんけん)で捕獲された神秘的な亀が献上される。曹奐は、この亀を相国府に収めさせた。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【02月】
庚戌(こうじゅつ)の日(25日)
魏の曹奐が、かつて鍾会(しょうかい)が反乱を起こした際、成都の諸陣営に鍾会の反逆を知らせて回り、命を落とすことになった虎賁(こほん)の張脩(ちょうしゅう)について触れ、その弟の張倚(ちょうい)を関内侯に取り立てる。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【03月】
呉の孫晧が、光禄大夫の紀陟(きちょく)と五官中郎将の弘璆(こうきゅう)らを魏へ遣わし、先(264年)に魏の司馬昭(しばしょう)から送られた手紙の返書を届けさせる。
このとき紀陟と弘璆は、魏の使者として来ていた徐紹(じょしょう)と孫彧(そんいく)を伴い、魏へ向かった。
しかし徐紹だけは、濡須(じゅしゅ)まで行ったところで呼び戻され、孫晧によって処刑されたうえ、一家眷属(けんぞく)は建安へ強制移住させられた。「もともと呉の臣下である徐紹が、中原(ここでは魏のこと)を称賛している」と、孫晧に言上した者がいたためである。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
★『江表伝』…このとき孫晧が届けさせた返書の様式について。
★『呉録』…紀陟と弘璆について。
★『晋紀』…紀陟と弘璆の洛陽における振る舞いについて。
⇒04月
呉の孫晧が、紀陟と弘璆を魏に遣わして和親を求める。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【04月】
魏の曹奐のもとに、「南深沢県で甘露が降った」との報告が届く。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【04月】「呉の改元」
呉の孫晧のもとに、「蔣陵(蔣山陵。孫権〈そんけん〉の陵)で甘露が降った」との報告が届く。そこで孫晧は、「元興」を「甘露」と改元したうえ、大赦を行った。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【05月】
魏の曹奐が詔を下し、呉の孫晧から献上された品々を、相国・晋王の司馬昭に届けさせようとする。しかし、司馬昭が固辞したため沙汰やみになった。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【05月】
晋の司馬昭が、司馬炎を王太子に立てる。
『晋書』(武帝紀)
⇒05月
魏の曹奐が詔を下し、相国・晋王の司馬昭に、「冠に12の玉飾りを付けること」「天子の旗を立て、出入りの際に先払いの役を配置し、ほかの者を通行禁止とすること」「金根車に乗り、これを6頭立ての馬に引かせ、五時車(5色ある季節の色を塗った車)を副車(そえぐるま)として備えること」「旄頭(ぼうとう)と雲罕(うんかん)を備えること」「八佾(はちいつ。天子の舞楽。8人が8列になって舞う)の舞楽を演ずること」「宮殿に鐘を吊るす台を設置すること」を許す。
また、晋国の王妃を王后に、世子を王太子に、それぞれ昇格させ、王子・王女・王孫の爵号を旧例に従って改めさせた。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【05月】
癸未(きび)の日(30日)
魏の曹奐が大赦を行う。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【07月】「朱皇后(しゅこうごう)の崩御」
呉の孫晧が、先に皇太后から景后(景皇后)に位を貶(おと)した朱氏を死に追いやる。さらに孫休(そんきゅう)の4人の息子たちを呉郡の小城へ閉じ込めたうえ、その後まもなく年長のふたりを殺害した。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
★ここで孫晧が殺害したのは、年長のふたりとだけあった。『三国志』(呉書・孫休伝)および(呉書・孫晧伝)の記事から、豫章王に封ぜられていた孫ワン(そんわん。雨+單)と汝南王に封ぜられていた孫コウ(そんこう。雷+大)のふたりだと思われる。
【08月】「司馬昭の崩御と晋王司馬炎」
辛卯(しんぼう)の日(9日)
晋の司馬昭が崩御し、司馬炎が(魏の)相国および晋王を継ぐ。司馬炎は王令を下し、刑罰を緩め、みなをいたわり役務をやめる。晋の国民は3日間、喪に服した。
『晋書』(武帝紀)
⇒08月
辛卯の日(9日)
魏の相国・晋王の司馬昭が薨去(こうきょ)する。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
⇒08月
壬辰(じんしん)の日(10日)
魏の司馬炎が、父の官職と領地を受け継ぎ、政治万端を取り仕切る。司馬炎の調度や礼式についても、司馬昭の待遇と同じとされた。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【08月】
身長が3丈もある巨人が襄武県に現れ、県民の王始(おうし)に「今まさに天下が太平になる」と告げる。
『晋書』(武帝紀)
⇒08月
魏の曹奐のもとに、「襄武県で3丈余りもある巨人が現れた」との報告が届く。
この巨人は、足跡が3尺(せき)2寸もあった。白髪で黄色の単衣(ひとえ)を身に着けており、黄色の頭巾をかぶり、杖に寄りかかっていた。巨人は王始という平民に声をかけ、「今に呉が平定され、太平になるぞ」と言ったともある。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【09月】
乙未(いつび)の日(?日)
魏の曹奐が、再び大赦を行う。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
★『正史 三国志1』(今鷹真〈いまたか・まこと〉、井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま学芸文庫)の訳者注によると、「ここは乙卯(いつぼう)の日(4日)の誤りか」という。
【09月】
戊午(ぼご)の日(7日)
晋の司馬炎が、魏の司徒の何曾(かそう)を丞相に、鎮南将軍の王沈(おうしん)を御史大夫に、中護軍の賈充(かじゅう)を衛将軍に、議郎の裴秀(はいしゅう)を尚書令・光禄大夫に、それぞれ任じ、みな開府する。
『晋書』(武帝紀)
⇒09月
戊午の日(7日)
魏の司徒の何曾が、晋の丞相に任ぜられる。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【09月】
癸亥(きがい)の日(12日)
魏の曹奐が、驃騎将軍の司馬望(しばぼう)を司徒に、征東大将軍の石苞(せきほう)を驃騎将軍に、征南大将軍の陳騫(ちんけん)を車騎将軍に、それぞれ任ずる。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【09月】
乙亥(いつがい)の日(24日)
魏の曹奐が、司馬昭の葬儀を執り行う。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
★司馬昭の葬儀を執り行った人物は、曹奐としたほうがいいのか、それとも司馬炎としたほうがいいのか? 普通に考えれば息子の司馬炎でいいはずだが、本紀に記すくらいだから国葬扱いなのだろうし――。ここはよくわからなかった。
【09月】「呉の遷都」
呉の孫晧が、西陵督の歩闡(ほせん)の建議に従い、建業から武昌へ遷都する。
その際、御史大夫の丁固(ていこ)と右将軍の諸葛靚(しょかつせい)が、旧都の建業に留まって守りにあたった。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【11月】
晋の司馬炎が、初めて四護軍を設置し、城外の諸軍を統率させる。
『晋書』(武帝紀)
【11月】
乙未の日(?日。「己未〈きび〉の日」なら11月9日となる。なお、翌月の閏11月15日が「乙未の日」である)
晋の司馬炎が、諸郡の中正(ちゅうせい)に王令を下し、以下の6か条をもって下位に留まっている人材を推挙させる。
1、忠恪匪躬(慎み深く、わが身を顧みない)であること
2、孝敬尽礼(親を大事にして上司を敬い、礼を尽くす)であること
3、友于兄弟(兄弟と仲良くする)であること
4、潔身労謙(清廉で功を上げても謙虚)であること
5、信義可復(信義に報いる)であること
6、学以為己(自分のために学ぶ)であること
『晋書』(武帝紀)
【11月】
呉の孫晧が魏へ遣わしていた、紀陟と弘璆が帰国する。ふたりが魏の洛陽に着いたとき、たまたま司馬昭が亡くなったため、すぐに戻ってきたもの。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【11月】
呉の孫晧が武昌に遷(うつ)り、再び大赦を行う。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【11月】
呉の孫晧が、零陵郡の南部を始安郡とし、桂陽郡の南部を始興郡とする。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
【閏11月】
庚辰(こうしん)の日(?日)
魏の曹奐に、康居と大宛から名馬が献上される。曹奐は、献上された馬を相国府に届けさせたうえ、すべての国々をなつけ、遠方からの使者を招き寄せた司馬炎の勲功を顕彰した。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
【12月?】「曹奐の禅譲と魏の滅亡」
魏の曹奐が歴数(定まった運命)のありかを悟り、太保の鄭沖(ていちゅう)に策書を奉じさせ、晋の司馬炎に帝位を譲る。
司馬炎は初め辞退するが、魏の公卿の何曾(晋の丞相でもある)や王沈(晋の御史大夫でもある)らが強く要請したこともあり、これを受け入れた。
『晋書』(武帝紀)
⇒12月
壬戌(じんじゅつ)の日(13日)
魏の曹奐が百官に詔を下し、晋王の司馬炎に帝位を譲る。その際の礼式は、漢・魏の交代の例に倣った。
甲子(こうし)の日(15日)
魏の曹奐が、晋王の司馬炎に使者を遣わし、策(命令を書き付ける札)を捧げ持たせる。
こうして曹奐は金墉城(きんようじょう)に移ることになったが、のち鄴に屋敷を構えた。禅譲したとき20歳だった。
『三国志』(魏書・陳留王紀)
★『魏世譜』…司馬炎は、曹奐を陳留王に封じた。曹奐は、晋の大安(たいあん)元(302)年に58歳で薨去した。その諡(おくりな)を元皇帝という。
★ここでは(原文にも)大安とあったが、太安としたほうがいいのか?
⇒12月
晋の司馬炎が、魏の曹奐の禅譲を受け、新たな王朝を開く。
『三国志』(呉書・孫晧伝)
⇒12月
晋の司馬炎が帝位に即き、「咸熙」を「泰始」と改元する。これが晋(西晋)の武帝。司馬炎は景初暦(けいしょれき)も改め、太始暦(たいしれき。泰始暦)を用いた。
『正史 三国志8』(小南一郎〈こみなみ・いちろう〉訳 ちくま学芸文庫)の年表
【12月】「晋帝司馬炎と晋の建元」
丙寅(へいいん)の日(17日)
晋の司馬炎が、南郊に(受禅のための)壇を築く。(儀式のために)様々な官位にある者や匈奴の南単于、そのほかの四夷から数万人が集まった。
受禅の儀式を終えると、司馬炎は洛陽宮の太極前殿(たいごくぜんでん)に行幸し、詔を下して帝位に即いたことを天下に知らせた。
そして大赦を行い、「泰始」と改元し、天下の人々それぞれに5級ずつ爵位を与える。
さらに、鰥夫(かんぷ。妻と死別した男性)、寡婦(かふ。夫と死別した女性)、子のない老人、孤児で自活できない者には、1人につき5斛の穀物を与えた。
加えて、天下の租賦(そふ)および関所や市場にかかる税を1年間免除し、未納分や負債も回収しないことにした。
また旧弊を除くことにし、禁錮(きんこ。任官禁止処分)を解き、官位や爵位を失っている者はすべて元に戻した。
『晋書』(武帝紀)
【12月】「晋の初封」
丁卯の日(18日)
晋の司馬炎が、太僕の劉原(りゅうげん)を太廟に遣わし、帝位に即いたことを報告させる。
魏帝だった曹奐を陳留王に封じ、その封邑を1万戸とし、鄴宮(ぎょうきゅう)に住まわせる。曹氏のうち王だった者はみな県侯に封じた。
宣王(司馬懿〈しばい〉。司馬炎の祖父)を追尊して宣皇帝とし、景王(司馬師〈しばし〉。司馬炎の伯父)を景皇帝とし、文王(司馬昭。司馬炎の父)を文皇帝とし、宣王妃の張氏(司馬炎の祖母)を宣穆皇后とした。
太妃の王氏(司馬炎の母)を尊んで皇太后とし、その宮を崇化(すうか)とした。
叔祖父の司馬孚(しばふ)を安平王とし、叔父の司馬幹(しばかん)を平原王とし、司馬亮(しばりょう)を扶風王とし、司馬伷(しばちゅう)を東莞王(とうかんおう)とし、司馬駿(しばしゅん)を汝陰王とし、司馬肜(しばゆう)を梁王とし、司馬倫(しばりん)を琅邪王とし、弟の司馬攸(しばゆう)を斉王とし、司馬鑒(しばかん)を楽安王とし、司馬幾(しばき。司馬機)を燕王とし、従伯父の司馬望(しばぼう)を義陽王とし、従叔父の司馬輔(しばほ)を渤海王(勃海王)とし、司馬晃(しばこう)を下邳王とし、司馬瓌(しばかい)を太原王とし、司馬珪(しばけい)を高陽王とし、司馬衡(しばこう)を常山王とし、司馬子文(しばしぶん)を沛王とし、司馬泰(しばたい)を隴西王(ろうせいおう)とし、司馬権(しばけん)を彭城王とし、司馬綏(しばすい)を范陽王とし、司馬遂(しばすい)を済南王とし、司馬遜(しばそん)を譙王(しょうおう)とし、司馬睦(しばぼく)を中山王(ちゅうざんおう)とし、司馬陵(しばりょう)を北海王とし、司馬斌(しばひん)を陳王とし、従父兄の司馬洪(しばこう)を河間王とし、従父弟の司馬楙(しばぼう)を東平王とした。
★ここで初めて王に封ぜられた27人をまとめておく。
司馬孚 安平王 司馬懿の弟 司馬炎の叔祖父
司馬幹 平原王 司馬懿の息子 司馬炎の叔父
司馬亮 扶風王 司馬懿の息子 司馬炎の叔父
司馬伷 東莞王 司馬懿の息子 司馬炎の叔父
司馬駿 汝陰王 司馬懿の息子 司馬炎の叔父
司馬肜 梁王 司馬懿の息子 司馬炎の叔父
司馬倫 琅邪王 司馬懿の息子 司馬炎の叔父
司馬攸 斉王 司馬昭の息子 司馬炎の弟
司馬鑒 楽安王 司馬昭の息子 司馬炎の弟
司馬幾(司馬機) 燕王 司馬昭の息子 司馬炎の弟
司馬望 義陽王 司馬孚の息子 司馬炎の従伯父
※司馬望は、司馬懿の弟である司馬孚の息子だが、司馬懿の兄である司馬朗(しばろう)の家を継いだため、司馬炎の「従叔父」ではなく「従伯父」となっている。
司馬輔 渤海王(勃海王) 司馬孚の息子 司馬炎の従叔父
司馬晃 下邳王 司馬孚の息子 司馬炎の従叔父
司馬瓌 太原王 司馬孚の息子 司馬炎の従叔父
司馬珪 高陽王 司馬孚の息子 司馬炎の従叔父
司馬衡 常山王 司馬孚の息子 司馬炎の従叔父
司馬子文 沛王 司馬孚の息子 司馬炎の従叔父
司馬泰 隴西王 司馬馗(しばき)の息子 司馬炎の従叔父
司馬権 彭城王 司馬馗の息子 司馬炎の従叔父
司馬綏 范陽王 司馬馗の息子 司馬炎の従叔父
司馬遂 済南王 司馬恂(しばじゅん)の息子 司馬炎の従叔父
司馬遜 譙王 司馬進(しばしん)の息子 司馬炎の従叔父
司馬睦 中山王 司馬進の息子 司馬炎の従叔父
司馬陵 北海王 司馬通(しばとう)の息子 司馬炎の従叔父
司馬斌 陳王 司馬通の息子 司馬炎の従叔父
司馬洪 河間王 司馬望の息子 司馬炎の従父兄
司馬楙 東平王 司馬望の息子 司馬炎の従父弟
さらに、驃騎将軍の石苞(せきほう)を大司馬・楽陵公とし、車騎将軍の陳騫(ちんけん)を高平公とし、衛将軍の賈充を車騎将軍・魯公とし、尚書令の裴秀を鉅鹿公(きょろくこう)とし、侍中の荀勖(じゅんきょく)を済北公とし、太保の鄭沖を太傅・寿光公とし、太尉の王祥(おうしょう)を太保・睢陵公(すいりょうこう)とし、丞相の何曾を太尉・朗陵公とし、御史大夫の王沈を驃騎将軍・博陵公とし、司空の荀顗(じゅんぎ)を臨淮公とし、鎮北大将軍の衛瓘を葘陽公(しようこう)とした。
そのほかの者にも、それぞれ差をつけて増封や進爵の沙汰があり、文武の官はみな位階が2等級進んだ。
また、景初暦を改めて太始暦(泰始暦)とし、臘(ろう)の祭りは酉(ゆう)の日に、社の祭りは丑(ちゅう)の日に、それぞれ行うことにした。
『晋書』(武帝紀)
【12月】
戊辰(ぼしん)の日(19日)
晋の司馬炎が詔を下し、大いに倹約を推進することにし、御府に保管してある珠玉や玩好品(がんこうひん)を放出し、王公以下に差をつけて下賜する。
また、中軍将軍の官を設置し、宿衛の7軍を統率させる。
『晋書』(武帝紀)
【12月】
己巳(きし)の日(20日)
晋の司馬炎が詔を下し、陳留王(曹奐)に天子の旌旗(せいき)を掲げること、五時(季節を表す5色)の副車を用いること、魏の正朔を用いて天地を祀ること、礼楽や制度はみな魏の旧制に従うこと、上書する際に臣と称さなくともよいことを認める。
また、山陽公の劉康(りゅうこう。後漢の献帝の孫)と安楽公の劉禅(りゅうぜん。蜀の後主)の息子1人ずつを駙馬都尉(ふばとい)に任ずる。
『晋書』(武帝紀)
【12月】
乙亥(いつがい)の日(26日)
晋の司馬炎が、安平王の司馬孚を太宰・仮黄鉞(かこうえつ)・大都督中外諸軍事に任ずる。
また、詔を下し、かつて大逆罪に問われた王淩(おうりょう)と鄧艾(とうがい)の家族を大赦し、爵位を返して跡継ぎを立てさせた。
さらに、魏の曹氏の禁錮を解き、将吏のうちで親を亡くした者には懇(ねんご)ろに服喪を終えさせ、万民の徭役をやめさせ、部曲将の長吏以下から質任(人質)を取るのをやめさせる。
そして、郡国からの献上品を減らし、楽府の派手な曲芸や技巧を凝らした彫刻、田猟に用いる道具の製作を禁じ、直言する道を開き、諫官を設置してそのことを掌らせた。
『晋書』(武帝紀)
【12月】
この月、各地の郡国に合わせて鳳凰6羽、青龍3頭、白龍2頭、麒(き)と麟(りん)それぞれ1頭が現れた。
『晋書』(武帝紀)
特記事項
「この年(265年)に亡くなったとされる人物」
朱氏(しゅし)C ※孫休(そんきゅう)の妻・孫コウ(そんこう。雷+大)・孫ワン(そんわん。雨+單)
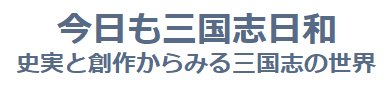

















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます