【姓名】 王連(おうれん) 【あざな】 文儀(ぶんぎ)
【原籍】 南陽郡(なんようぐん)
【生没】 ?~?年(?歳)
【吉川】 第263話で初登場。
【演義】 第087回で初登場。
【正史】 登場人物。『蜀書・王連伝』あり。
塩鉄の利を図り国庫を富ます
父母ともに不詳。息子の王山(おうさん)は跡継ぎ。
王連は劉璋(りゅうしょう)の時代(194~214年)に蜀へ入り、梓潼県令(しとうけんれい)に任ぜられる。
211年、劉備が益州(えきしゅう)へ入り、翌212年に葭萌(かぼう)から反転して劉璋を攻めた。このとき王連は城門を閉じて降伏しなかったが、劉備は彼の義心に感じ入ったので、あえて威圧することはなかった。
214年、劉備が成都(せいと)で劉璋を降した後、王連は什邡県令(じゅうほうけんれい)や広都県令(こうとけんれい)を務め、それぞれの任地で治績を上げる。
王連が司塩校尉(しえんこうい)に昇進すると、塩や鉄から得られる収入が大幅に増えて国庫は潤った。
また、このころ王連は有能な属官を選抜し、呂乂(りょがい)・杜祺(とき)・劉幹(りゅうかん)らを登用したが、後に彼らはみな大官となる。
王連は蜀郡太守・興業将軍(こうぎょうしょうぐん)に昇進し、塩府の業務も引き続き担当した。
223年、王連は屯騎校尉(とんきこうい)に転じて丞相長史(じょうしょうちょうし)を兼ね、平陽亭侯(へいようていこう)に封ぜられた。
諸葛亮(しょかつりょう)は南方の諸郡が服従しないため、自ら討伐にあたろうと考える。しかし王連は南方の厳しい風土を案じ、諸葛亮自身が赴くことを諫め続けた。
これを受けて諸葛亮もしばらく成都に留まっていたが、そのうち王連は死去(時期は不明)し、息子の王山が跡を継いだ。
なお、諸葛亮は225年に南征を決行し、自ら大軍をひきいて成功を収め、その年のうちに帰還した。
管理人「かぶらがわ」より
塩や鉄を国の専売にすることで、莫大(ばくだい)な利益がもたらされたのはわかりましたが、それらの制度を運用するための工夫に触れられていなかったのは残念でした。
そのあたりに王連の非凡さが表れていたと思うので、ひとつでもふたつでも実践例が書かれていたら、貴重な史料になったでしょう。
そして王連の死後に行われた南征でしたが、これが1年もかけずに完結できたことと、この間に諸葛亮の身に何事もなかったことは、蜀にとって幸いでしたね。
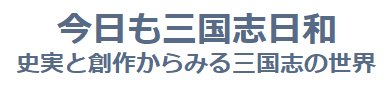














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます