-237年- 丁巳(ていし)
【魏】 (青龍〈せいりょう〉5年) → 景初(けいしょ)元年 ※明帝(曹叡〈そうえい〉)
【蜀】 建興(けんこう)15年 ※後主(劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 嘉禾(かか)6年 ※大帝(孫権〈そんけん〉)
月別および季節別の主な出来事
【正月】
壬辰(じんしん)の日(?日)
魏の曹叡のもとに、「山茌県(さんしけん)で黄龍が現れた」との報告が届く。
このとき担当官吏が曹叡に上奏し、「魏は地統を得ておりますので、建丑(けんちゅう)の月(12月のこと)を正月とされるべきです」と述べた。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★ここは理解できない部分があったため、こういう書き方に留めておく。『正史 三国志1』(今鷹真〈いまたか・まこと〉、井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま学芸文庫)では、正月壬辰(の日)を18日と解釈されていたが、これについてもよくわからなかった。
【01月】
呉の孫権が詔を下す。3年の服喪の定めについて触れ、「肉親が亡くなったとき、すべての職務を放棄して葬儀に駆けつけることは許さない」という現在の規定について、「中央および地方にある官僚たちは、もう一度このことの是非を詳しく検討し、正しいあり方を理解させるように努め、この方針を細心に実行するように」というもの。
交代の者を待たずに、職務を放棄して肉親の葬儀に駆けつけた者への罰則については、様々な意見が出された。丞相の顧雍(こよう)が意見を取りまとめ、孫権に死刑の罰則を定めるよう上奏した。
その後、呉県令の孟宗(もうそう)が、職務を放棄して母の葬儀に駆けつけた。孟宗は葬儀を終えた後、自分から名乗り出て武昌で投獄され、いかなる刑でも甘受する考えを示した。
陸遜(りくそん)の命乞いを容れ、孫権は孟宗の死一等を減じたが、今後は同じように刑を減ずることのないよう命じた。それ以降、職務を放棄して肉親の葬儀に駆けつけるという風はなくなった。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【02月】
呉の陸遜が、昨年(236年)反乱を起こした鄱陽の賊徒の彭旦(ほうたん)らの討伐に向かう。そして、この年のうちにすべて討ち破った。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【03月】「魏の改元」
魏の曹叡が暦を改定し、「青龍」を「景初」と改元したうえ、この月(3月)を4月とする。
衣服は黄色を尊んで用いることにし、犠牲(いけにえ)には白い獣を用い、軍事では頭が黒の白馬(?)に乗り、大きな赤い旗を立て、朝廷の会合には大きな白い旗を立てた。
また、太和暦(たいわれき)を改めて景初暦と名付けた。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★『魏書』…曹叡の太子時代の論著。
★ここで曹叡の太子時代とあったが、曹丕はなかなか太子を定めず、危篤に陥って初めて、曹叡が太子に立てられたはず。曹叡の皇子時代ならわかるが、やや不可解だった。
★裴松之(はいしょうし)の考え…このとき曹叡が取った措置の考察。
★『正史 三国志1』の訳者注によると「これより景初3(239)年の12月まで景初暦が用いられ、暦が1か月ずつ繰り上がることになる」という。
★また、『三国志』(魏書・公孫度伝〈こうそんたくでん〉)に付された「公孫淵伝(こうそんえんでん)」の『正史 三国志2』(井波律子、今鷹真訳 ちくま学芸文庫)の訳者注には、「明帝(曹叡)は青龍5(237)年3月、『景初』と改元すると同時に新暦を用い、旧暦の3月を4月とし、12月を正月とした」ともある。
⇒03月
魏の曹叡が、「青龍」を「景初」と改元したうえ、青龍5年3月を景初元年4月とする。また、服色(王朝のシンボルカラー)を黄色と定め、太和暦を景初暦と改めた。
『正史 三国志8』(小南一郎〈こみなみ・いちろう〉訳 ちくま学芸文庫)の年表
【05月】
己巳(きし)の日(2日)
魏の曹叡が洛陽宮に還幸する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【05月】
己丑(きちゅう)の日(22日)
魏の曹叡が大赦を行う。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【06月】
己亥(きがい)の日(3日)
魏の曹叡が、尚書令の陳矯(ちんきょう)を司徒に、尚書右僕射(しょうしょゆうぼくや)の衛臻(えいしん)を司空に、それぞれ任ずる。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【06月】
丁未(ていび)の日(11日)
魏の曹叡が、魏興郡から魏陽県を、錫郡(せきぐん)から安富・上庸の両県を、それぞれ分割し、上庸郡を設置する。また錫郡を廃止し、錫県を魏興郡に併せた。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【06月】
戊申(ぼしん)の日(12日)
魏の洛陽で地震が起こる。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【05月】
14日、呉で地震が起こる。
『三国志』(呉書・歩騭伝〈ほしつでん〉)
★ここでは(原文にも)5月14日とだけあり、干支(かんし)についての記述はなかった。この時期、魏の暦が繰り上がっている関係から、記事としてはこの位置に入ると思われる。
【06月】
魏の担当官吏が曹叡に上奏する。「太祖(曹操〈そうそう〉)・高祖(曹丕〈そうひ〉)・烈祖(曹叡)の三祖の霊廟は、万世の後まで壊さずにおかれ、そのほかの四廟(天子の廟は七廟)は、近い関係が絶えれば順次取り壊されて、周の后稷(こうしょく)・文王・武王の三祖の霊廟の制度と同じようになさいますように」というもの。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★ここで「孫盛(そんせい)はいう」として、この上奏について、「曹叡がまだ亡くなってもいないのに、前もって曹叡自身を烈祖と尊び、顕彰していること」を指摘し、この上奏と曹叡を批判している。
【07月】
丁卯(ていぼう)の日(2日)
魏の司徒の陳矯が死去する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【07月】
呉の孫権が、朱然(しゅぜん)らに2万の兵を付けて遣わし、魏の江夏郡を包囲する。魏の荊州刺史の胡質(こしつ)らが反撃したため、朱然は退却した。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【07月】
以前、呉の孫権は、高句驪(高句麗)に使者を遣わして誼(よしみ)を通じ、遼東を攻めようとしていた。
そこで魏では、幽州刺史の毌丘倹(かんきゅうけん)に、諸軍および鮮卑と烏丸の軍勢も統率させ、遼東の南境に駐屯するよう命じた。さらに、曹叡の詔によって公孫淵(こうそんえん)が召し寄せられた。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【07月】
遼東の公孫淵が魏に背く。魏の幽州刺史の毌丘倹は、軍を進めて討伐しようとしたが、ちょうど10日間も雨が続き、遼水が満ちあふれる。曹叡は毌丘倹に詔を下し、右北平への引き揚げを命じた。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【07月】
烏丸の単于(ぜんう)の寇婁敦(こうろうとん)と遼西の烏丸都督王の護留(ごりゅう)らが、住んでいた遼東から部族をひきいて魏に帰順する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【07月】
己卯(きぼう)の日(14日)
魏の曹叡が詔を下し、遼東の将校・軍吏・兵士・庶民のうち、公孫淵に脅迫されてやむなく従った者たちをみな許す。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【07月】
辛卯(しんぼう)の日(26日)
太白星(金星)が昼間に現れる。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【?月】「公孫淵の自立、一時的ながら四国状態に」
遼東の公孫淵が、魏の毌丘倹が引き揚げた後、自立して燕王と称し、独自の百官を設置する。また、年号を建てて「紹漢(しょうかん)元年」と称した。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【06月】「張皇后(ちょうこうごう)の崩御」
蜀の張皇后が崩御する。
『三国志』(蜀書・後主伝)
★この記事についても、魏の暦が繰り上がっている関係から載せる位置が難しい。
【?月】
魏の曹叡が詔を下し、青州・兗州・幽州・冀州の4州に、大々的に海船の建造を命ずる。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【09月】
冀州・兗州・徐州・豫州の4州が洪水に見舞われたため、魏の曹叡は、侍御史を遣わして巡行視察を命じ、洪水で溺死した者や財産をなくした者に、官倉を開いて救済を図る。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【09月】「毛皇后(もうこうごう)の崩御」
庚辰(こうしん)の日(16日)
魏の毛皇后が崩御する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
⇒09月
魏の明帝(曹叡)が郭氏(かくし)を寵愛し、毛皇后を殺害する。
『正史 三国志8』の年表
【10月】
丁未(ていび)の日(13日)
月が熒惑星(けいわくせい。火星)を犯す。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【10月】
癸丑(きちゅう)の日(19日)
魏の曹叡が、悼毛后(毛氏)を愍陵に葬る。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【10月】
乙卯(いつぼう)の日(21日)
魏の曹叡が、洛陽の南にある委粟山(いぞくざん)に円丘(冬至に天を祭る場所)を造営する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★『魏書』…このときの曹叡の詔。
【10月】
呉の孫権が、衛将軍の全琮(ぜんそう)を遣わして六安(りくあん)を攻めさせる。しかし、全琮は戦果を上げることができなかった。
『三国志』(呉書・呉主伝)
【12月】
壬子(じんし)の日(19日)
魏の曹叡が、初めて冬至に祭祀を執り行う。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【12月】
丁巳(ていし)の日(24日)
魏の曹叡が、襄陽郡から臨沮(りんしょ)・宜城・旍陽(せいよう)・邔県(きけん)の4県を分割し、襄陽南部都尉の官を設置する。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【12月】
己未(きび)の日(26日)
魏の担当官吏が曹叡に上奏し、「都(洛陽)に文昭皇后(甄氏〈しんし〉)の霊廟を建立されますように」と求める。
『三国志』(魏書・明帝紀)
【12月】
魏の曹叡が、襄陽郡から鄀葉県(じゃくようけん)を分割し、義陽郡に併せる。
『三国志』(魏書・明帝紀)
★『魏略』…この年、長安にあった、もろもろの鐘や簴(きょ。鐘や太鼓を支える台)・駱駝像(らくだぞう)・銅人・承露盤を洛陽に移した話。
★『漢晋春秋』…上の『魏略』の話の補足。「明帝(曹叡)が承露盤を移そうとした際に壊れ、その音は数十里まで響き渡り、金狄(黄金の鋳造物)がすすり泣いたため、そのまま霸城に承露盤を留め置いた」という。
★『魏略』…司徒軍議掾(しとぐんぎえん)の董尋(とうじん)が、曹叡への上奏文で述べた諫言。
【?月】
この年、呉の諸葛恪(しょかつかく)が、山越(江南に住んでいた異民族)平定の任務を終え、北へ出て廬江に軍を駐屯させた。
『三国志』(呉書・呉主伝)
特記事項
「この年(237年)に亡くなったとされる人物」
呉壱(ごいつ。呉懿〈ごい〉)・周魴(しゅうほう)・曹抗(そうこう)・張氏(ちょうし)H ※劉禅(りゅうぜん)の妻・陳矯(ちんきょう)・毛氏(もうし)
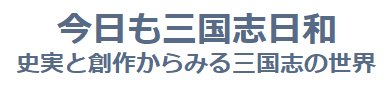


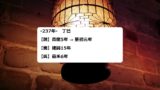














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます