吉川『三国志』の著者である吉川英治(よしかわ・えいじ)先生の三国志観から、諸葛菜(しょかつさい)と呼ばれ、現代でも食べられているという蕪(かぶ。蔓菁〈まんせい〉ともある)の逸話までが語られた篇外余録の1話目。
吉川先生が、諸葛亮(しょかつりょう)の死をもって本編の幕引きとした理由が興味深い。
篇外余録(1)の全文とポイント
(01)吉川先生の三国志観
三国鼎立(ていりつ)の大勢は、ときの治乱が起した大陸分権の自然な風雲作用でもあったが、その創意はもともと諸葛孔明(しょかつこうめい。孔明は諸葛亮のあざな)という一人物の胸底から生れ出たものであることは何としても否みがたい。
まだ27歳でしかなかった青年孔明が、農耕の余閑、草廬(そうろ)に抱いていた理想の実現であったのである。
時に、三顧して迎えた劉玄徳(りゅうげんとく。玄徳は劉備〈りゅうび〉のあざな)の奨意にこたえ、いよいよ廬を出て起たんと誓うに際して、「これを以てあなたの大方針となすべきでしょう。これ以外に漢朝復興の旗幟(きし)を以て中原(ちゅうげん。黄河中流域)に臨む道はありますまい」と、説いたものが実にその発足であったわけだ。
そして遂に、その理想は実現を見、玄徳は西蜀に位置し、北魏の曹操(そうそう)、東呉の孫権(そんけん)と、いわゆる三分鼎立の一時代を画するに至ったが、もとよりこれが孔明の究極の目的ではない。
孔明の天下の三分の案は、玄徳が初めからの志望としている漢朝統一への必然な過程として選ばれた道であった。
しかし、この中道において、玄徳は世を去り幼帝(みなしご)の将来とともに、その遺業をも挙げて、――すべてをたのむ。と、孔明に託して逝ったのである。
孔明の生涯とその忠誠の道は、まさにこの日から彼の真面目(しんめんもく。本来の姿)に入ったものといっていい。
★劉備は蜀の章武(しょうぶ)3(223)年4月に崩御(ほうぎょ)した。
遺孤(みなしご)の寄託、大業の達成。――寝ても醒(さ)めても「先帝の遺詔」にこたえんとする権化のすがたこそ、それからの孔明の全生活、全人格であった。
ゆえに原書「三国志演義」も、孔明の死にいたると、どうしても一応、終局の感じがするし、また三国争覇そのものも、万事休(や)む――の観なきを得ない。
おそらくは読者諸氏もそうであろうが、訳者もまた、孔明の死後となると、とみに筆を呵(か)す興味も気力も稀薄となるのを如何(いかん)ともし難い。これは読者と筆者たるを問わず古来から三国志にたいする一般的な通念のようでもある。
★ここで吉川先生が、ご自身を「訳者」と表現されていたのが意外だった。
で、この迂著(うちょ。自著の謙称)三国志は、桃園の義盟以来、ほとんど全訳的に書いてきたが、私はその終局のみは原著にかかわらず、ここで打ち切っておきたいと思う。即ち孔明の死を以て、完尾としておく。
原書の「三国志演義」そのままに従えば、五丈原以後――「孔明計(はかりごと)ヲ遺シテ魏延(ぎえん)ヲ斬ラシム」の桟道焼打ちのことからなお続いて、魏帝曹叡(そうえい)の栄華期と乱行ぶりを描き、司馬(しば)父子の擡頭(たいとう)から、呉の推移、蜀破滅、そして遂に、晋が三国を統一するまでの治乱興亡をなお飽くまでつぶさに描いているのであるが、そこにはすでに時代の主役的人物が見えなくなって、事件の輪郭も小さくなり、原著の筆致もはなはだ精彩を欠いてくる。要するに、龍頭蛇尾に過ぎないのである。
従って、それまでを全訳するには当らないというのが私の考えだが、なお歴史的に観て、孔明歿後(ぼつご)の推移も知りたいとなす読者諸氏も少なくあるまいから、それはこの余話の後章に解説することにする。
それよりも、原書にも漏れている孔明という人がらについて、もっと語りたいものを多く残しているように、私には思える。それも演義本にのみよらず、他の諸書をも考合して、より史実的な「孔明遺事」ともいうべき逸話や後世の論評などを一束(いっそく。ひとまとめ)しておくのも決して無意義ではなかろう。
それを以てこの「三国志」の完結の不備を補い、また全篇の骨胎をいささかでも完(まった)きに近いものとしておくことは訳者の任でもあり良心でもあろうかと思われる。
以下そのつもりで読んでいただきたい。
(02)『三国志』の主役交代、曹操から諸葛亮へ――
布衣(ほい。官位のない平民)の一青年孔明の初めの出現は、まさに、曹操の好敵手として起った新人のすがたであったといってよい。
曹操は一時、当時の大陸の八分までを席巻して、荊山楚水(けいざんそすい)ことごとく彼の旗をもって埋め、「呉の如きは、一水の長江に恃(たの)む保守国のみ。流亡これ事としている玄徳の如きはなおさらいうに足らない」とは、その頃の彼が正直に抱いていた得意そのものの気概であったにちがいなかろう。
それを彗星(すいせい)の如く出でて突如挫折を加えたものが孔明であった。また、着々と擡頭して来た彼の天下三分策の動向だった。
曹操が自負満々だった魏の大艦船団が、烏林(うりん)、赤壁(せきへき)にやぶれて北に帰り、次いでまた、玄徳が荊州を占領したと聞いたとき、彼は何か書き物をしていたが、愕然(がくぜん)、耳を疑って、「ほんとか?」と、筆を取り落したということは、魯粛伝(ろしゅくでん)にも記載されているし、有名な一挿話となっているが、それをみても如何に彼が、無敵曹氏の隆運を自負しきっていたかが知れる。
★赤壁の戦いは、漢の建安(けんあん)13(208)年に勃発した大戦。曹操自ら指揮する十数万の大軍と、孫権配下の周瑜(しゅうゆ)が指揮する数万の軍勢が激突。曹操軍に疫病が蔓延したことや、季節風を利用した孫権軍の巧みな火計により、曹操軍が惨敗。劉備は孫権と盟約を結び、この戦いを側面から支援した。
しかも以後、(劉備麾下〈きか〉に青年孔明なるものがある)を、意識させられてからというものは、事ごとに、志とたがい、さしもの曹操もついに、身の終るまで、自己の兵を、一歩も江漢へ踏み入らせることができなかった。
★曹操は漢の建安25(220)年1月に崩御した。
――とはいえ、曹操という者の性格には、いかにも東洋的英傑の代表的な一塑像を見るようなものがある。
その風貌ばかりでなくその電撃的な行動や多感な情痴と熱においても、まことに英雄らしい長所短所の両面を持っていて、「三国志」の序曲から中篇までの大管絃楽(だいかんげんがく)は絶えず彼の姿によって奏されているというも過言でない。
劇的には、劉備、張飛(ちょうひ)、関羽(かんう)の桃園義盟を以て、三国志の序幕はひらかれたものと見られるが、真の三国志的意義と興味とは、何といっても、曹操の出現からであり、曹操がその、主動的役割をもっている。
しかしこの曹操の全盛期を分水嶺(ぶんすいれい)として、ひとたび紙中に孔明の姿が現われると、彼の存在もたちまちにして、その主役的王座を、ふいに襄陽(じょうよう)郊外から出て来たこの布衣の一青年に譲らざるを得なくなっている。
ひと口にいえば、三国志は曹操に始まって孔明に終る二大英傑の成敗争奪の跡を叙したものというもさしつかえない。
この二人を文芸的に観るならば、曹操は詩人であり、孔明は文豪といえると思う。
痴や、愚や、狂に近い性格的欠点をも多分に持っている英雄として、人間的なおもしろさは、遥かに、孔明以上なものがある曹操も、後世久しく人の敬仰をうくることにおいては、到底、孔明に及ばない。
千余年の久しい時の流れは、必然、現実上の両者の勝敗ばかりでなく、その永久的生命の価値をもあきらかに、曹操の名を遥かに、孔明の下に置いてしまった。
時代の判定以上な判定はこの地上においてはない。
ところで、孔明という人格を、あらゆる角度から観ると、一体、どこに彼の真があるのか、あまり縹渺(ひょうびょう)として、ちょっと捕捉できないものがある。
軍略家、武将としてみれば、実にそこに真の孔明がある気がするし、また、政治家として彼を考えると、むしろそのほうに彼の神髄はあるのではないかという気もする。
思想家ともいえるし、道徳家ともいえる。文豪といえば文豪というもいささかもさしつかえない。
もちろん彼も人間である以上その性格的な短所はいくらでも挙げられようが、――それらの八面玲瓏(はちめんれいろう。どこから見ても鮮やかで美しい様子)ともいえる多能、いわゆる玄徳が敬愛おかなかった大才というものはちょっとこの東洋の古今にかけても類のすくない良元帥であったといえよう。
良元帥。まさに、以上の諸能を一将の身にそなえた諸葛孔明こそ、そう呼ぶにふさわしい者であり、また、真の良元帥とは、そうした大器でなくてはと思われる。
とはいえ、彼は決して、いわゆる聖人型の人間ではない。孔孟の学問を基本としていたことはうかがわれるが、その真面目はむしろ忠誠一図な平凡人というところにあった。
(03)諸葛亮の素顔
彼がいかに平凡を愛したかは、その簡素な生活にも見ることができる。
孔明がかつて、後主劉禅(りゅうぜん)へささげた表の中にも、日頃の生活態度を、こう述べている。
――成都ニ桑(そう)100株(しゅ)、薄田(はくでん。痩せた田地)15頃(けい)アリ。子弟ノ衣食、自(おのずか)ラ余饒(よじょう)アリ。臣ニ至リテハ、外ニ任アリ。別ノ調度ナク、身ニ随(したが)ウノ衣食、悉(ことごと)ク官ニ仰ゲリ。別ニ生ヲ治メテ以テ尺寸(せきすん)ヲ長ズルナシ。モシ臣死スルノ日ハ、内ニ余帛(よはく)アリ、外ニ嬴財(えいざい)アラシメテ、以テ、陛下ニ背カザル也。
枢要な国務に参与する者の心構えの一つとして、孔明はこれを生活にも実践したものであろう。後漢以来、武臣銭を愛すの弊風は三国おのおのの内にも跡を絶たなかったものにちがいない。
無私忠純の亀鑑を示そうとした彼の気もちは表の辞句以外にもよくあらわれている。
彼は清廉であるとともに、正直である。兵を用いるや神算鬼謀、敵をあざむくや表裏不測でありながら、軍(いくさ)を離れて、その人間を観るときは、実に、愚ともいえるほど正直な道をまっすぐに歩いた人であった。
子のように愛していた馬謖(ばしょく)を斬ったなども、そのあらわれの一つといえるし、また、劉玄徳が死に臨んで、「遺孤(みなしご)の身も、国の後事も、一切をあげて託しておくが、もし劉禅が暗愚で蜀の帝王たるの資質がないと卿(けい)が観るならば、卿が帝位に即いて、蜀を取れ」と、遺言したにかかわらず、彼は毛頭そんな野心は抱かなかった。
★馬謖は蜀の建興6(228)年春、諸葛亮の命令に背いて街亭(がいてい)の山上に陣取り、魏の右将軍(ゆうしょうぐん)の張郃(ちょうこう)に大敗。その責任を問われて処刑された。この出来事は「泣いて馬謖を斬る」の故事として現在まで残る。
だから晩年、年を次いでの北伐遠征には、ずいぶん孔明に従って行った将士が、他山の屍(しかばね)となって帰らなかったが、蜀中の戦死者の遺族も、決して、彼にたいして怨嗟(えんさ)しなかった。
のみならず、孔明の死に会うや、蜀の百姓は、廟(びょう)を立て、碑を築き、彼の休んだ址(あと)も、彼の馬をつないだ木も、一木一石の縁、みな小祠(しょうし)となって、土民の祭りは絶えなかった。
また、彼は内政と戦陣にかかわらず、賞罰には非常に厳しかったので、彼のために左遷させられたり逼塞(ひっそく)したものもずいぶんあったが、すべて彼の「私なき心」には怨む声もなく、かえって孔明の死後には、そうした人々までが、「――再び世に出る望みを失った」と、みな嘆いているほどである。
「いやしくも一国の宰相でありながら、夜は更けて寝(い)ね、朝は夙(つと)に起きいで、時務軍政を見、その上、細かい人事の賞罰までにいちいち心を労(つか)い過ぎているのは、真の大器量でないし、また、蜀にも忠に似てかえって忠に非(あら)ざるものである」という彼への論評などもないではなく、後世の史家は、そのほかにもいろいろ孔明の短所をかぞえあげているが、要するに、国を憂いて瘦軀(そうく)を削り、その赤心も病み煩うばかり日々夜々の戦いに苦闘しつつあった古人を、後世のご苦労なしの文人や理論家が、暖衣飽食しながら是々非々論じたところで、それはことばの遊戯以外の何ものでもないのである。
いわんや晩年数次にわたる北魏進撃と祁山(きざん)滞陣中の労苦とは、外敵の強大なばかりでなく、絶えず蜀自体の内にさまざまな憂うべきものが蔵されておったような危機に於(おい)てをやである。
思うに、孔明はまったく、その体が二つも三つも欲しかったろう。或(ある)いは、その天寿を、もう10年とも、思ったであろうと察しられる。
やはり彼の真の知己は、無名の民衆にあったといえよう。今日、中国各地にのこっている――駐馬塘(ちゅうばとう)とか、万里橋(ばんりきょう)とか、武侯坡(ぶこうは)とか、楽山(らくざん)とか称(よ)んでいる地名の所はみな、彼が詩を吟じた遺跡だとか、馬をつないだ堤だとか、人と相別れた道だとかいう語り伝えのあるところである。
そういう純朴な思慕の中にこそ、むしろ彼の姿はありのままに、また悠久に、春秋の時をも超えて残されていると思う。
(04)生前から神仙化されていた諸葛亮
――しかし、ただ困るのは、民間の余りな彼への景仰(けいこう)は、時には度がすぎて、孔明のすべてを、ことごとく神仙視してしまうことである。
その二、三の例をあげると。
――孔明の女(むすめ)は雲に乗って天に上った。それが葛女祠(かつじょし)として祭られたものだ。「朝真(ちょうしん)観記記事」
――木牛流馬(もくぎゅうりゅうば)は入神の自動器械で、人の力を用いず自(ひとり)でに走った。「戎州志(じゅうしゅうし)」
――彼は時計も作った。その時計は、毎更に鼓を鳴らし、三更(午前0時前後?)になると、鶏の声を三唱する。「華夷考(かいこう)」
★三更は真夜中ごろだと思うが、なぜ夜明けではなく、三更に鶏の声を三唱する仕掛けなのかよくわからなかった。
――孔明の用いた釜は今でも水を入れるとひとりでにすぐ沸く。「丹鉛録(たんえんろく)」
――孔明の墳(つか)のある定軍山(ていぐんざん)に雲がおりると今でもきっと撃鼓の声がする。漢中(かんちゅう)の八陣の遺蹟(いせき)には、雨がふると、鬨(とき)の声が起る。「干宝晋記(かんほうしんき)」
そのほか探せば数限りないほどこの類(たぐい)の口碑(こうひ)伝説はたくさんある。純朴愛すべきものもあるが、中には滑稽でさえあるのもある。
「三国志演義」の原著書は、史実と伝説とを、充分に知悉(ちしつ。知り尽くすこと)していながら、しかも多分にそういう土語民情の中に伝えられている孔明の姿をも取り容れて、さらにそれを文学的に神仙化しているのである。
彼の兵略戦法を語るに、六丁六甲(りくていりくこう)の術を附し、八門遁甲(とんこう)の鬼変を描写している件(くだり)などはみなそうであるし、わけて天文気象に関わることは、みな中国の陰陽五行と星暦に拠ったものである。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「六丁六甲は道教の神の名。六丁とは丁卯(ていぼう)・丁巳(ていし)・丁未(ていび)・丁酉(ていゆう)・丁亥(ていがい)・丁丑(ていちゅう)の6人の陰神」だという。また「六甲は甲子(こうし)・甲戌(こうじゅつ)・甲申(こうしん)・甲午(こうご)・甲辰(こうしん)・甲寅(こういん)の6人の陽神を指す」という。
さらに「彼らは天帝(天をつかさどると言われる神)の配下で、風雷を起こし、鬼神を制することができ、また道教の僧(法師)に呪文で招請され、厄払いに携わると信じられていた」ともいう。
★同じく『三国志(十)』(吉川英治著 新潮文庫)の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(八門遁甲は)道教経典『秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真経(ひぞうつうげんへんげりくいんどうびとんこうしんけい)』のことか。招風の術や縮地の法を収め、諸葛亮が習得したと記す」という。
けれど五行観も、宿星学も、これは根深く、黄土大陸の庶民に、久しい間信ぜられていた根本の宇宙観であり、それと結ばれていた人生観でもあったのだから、これを否定しては、「三国志演義」は成り立たないことになる。またかくの如く民衆のあいだに長く読み伝えられてもこなかったにちがいない。
――で、私のこの新訳「三国志」も、そういう箇所にかかる度、すくなからず苦労が伴った。近代の読書人に対しては何としても余りに怪力乱神の奇異を語るに過ぎなくなるからである。
ただその点において救われ得る道は、ただ一つ詩化あるのみであった。
その点は原書も大いに意を用いたらしく思われるが、私の場合も、一種の民族的詩劇を描くつもりで書いていった。同時に、そうした妖しき粉彩も音楽も、背景も一切削除するなく、原書のまま書きすすめた。
ちと横道へそれたが、中国の民衆が、時経つほど、いかに孔明を神仙視したかという話では、唐代になってからでも、こんな挿話がひろく行われていたのを見てもわかる。
――唐の頃、盗アリ、先主ノ墳ヲ発(あば)ク。盗数名。斉(ひと)シク入リシニ、人アリ、燈下ニ対シテ碁ヲ囲ムモノ両人、側ニ侍衛スルモノ十数名ヲ見ル。
盗、怖レテ拝ス。其時(そのとき)、座ノ一人、顧ミテ盗ニ曰(いわ)ク。汝等(なんじら)、能(よ)ク飲ムカト。
而(しか)シテ、各ゝニ美酒一杯ヲ飲マセ、マタ玉帯数条ヲ出シテ頒(わ)ケ与ウ。
盗、畏震(いしん)シテ、速ヤカニ坑(あな)ヲ出デ、相顧ミテ、モノヲ云ワントスレバ、唇(くち)ハ皆、漆ニ閉ジラレテ開カズ、手ノ玉帯ヲ見レバ、各ゝ、怖ロシゲナル巨蛇ヲ摑(つか)ミテアリシト。後ニ里人ニ問エバ、此陵(このりょう)ハ諸葛武侯ガ造ル所ノモノナリト曰(い)ウ。
これは「談叢(だんそう)」という一書のうちに見える記事である。
書物の話が出たついでに孔明の著作についていえば、兵書、経書、遺表の文章など、彼の筆になるものと伝えられるものはかなりある。しかし、多くは後人の編志、或いは代作が多いことはいうまでもない。
そのうちでも代表的な孔明流の兵書と称する「諸葛亮五法五巻」などは日本にも伝わって、後のわが楠流(くすのきりゅう)軍学や甲州流そのほかの兵学書などと同列しているが、もとより信じられるものではない。
彼が、陣中でよく琴を弾じていたということから「琴経(きんきょう)」という琴の沿革や七絃の音譜を書いた本も残されている。真偽は知らないが、孔明が多趣味な風流子であったことは事実にちかいようである。
「歴代名書譜」にも、――諸葛武侯父子、皆画ヲ能クス。と見えるし、その他の書にも、孔明が画に長じていたことはみな一致して記載している。しかしその画と信じ得るようなものはもちろん一作も伝わってはいない。
(05)隙がなかった諸葛亮
何事にも、几帳面だったことは、孔明の一性格であったように思われる。
孔明が軍馬を駐屯した営塁のあとを見ると、井戸、竈(かまど)、障壁、下水などの設計は、実に、縄墨(じょうぼく。規則)の法にかなって、規矩(きく)整然たるものであったという。
また、官府、次舎、橋梁(きょうりょう)、道路などのいわゆる都市経営にも、第一に衛生を重んじ、市民の便利と、朝門の威厳とをよく考えて、その施設は、当時として、すこぶる科学的であったようである。
そして、孔明自身が、自らゆるしていたところは、謹慎・忠誠・倹素の三つにあったようである。公に奉ずること謹慎、王室につくすこと忠誠、身を持すること倹素。――そう三つの自戒を以て終始していたといえよう。
こういう風格のある人に、まま見られる一短所は、謹厳自らを持す余りに、人を責める時にも、自然、厳密に過ぎ峻酷(しゅんこく)に過ぎる傾きのあることである。潔癖は、むしろ孔明の小さい疵(きず)だった。
たとえば日本における豊臣秀吉(とよとみ・ひでよし)の如きは、犀眼(さいがん。鋭い目)、鋭意、時に厳酷でもあり、烈(はげ)しくもあり、鋭くもあり、抜け目もない英雄であるが、どこか一方に、開け放しなところがある。
東西南北四門のうちの一門だけには、人間的な愚も見せ、痴も示し、時にはぼんやりも露呈している。彼をめぐる諸侯は、その一方の門から近づいて彼に親しみ彼に甘え彼と結ぶのであった。
ところが、孔明を見ると、その性格の几帳面さが、公的生活ばかりでなく、日常私生活にもあらわれている。なんとなく妄(みだ)りに近づき難いものを感じさせる。
彼の門戸にはいつも清浄な砂が敷きつめてあるために、砂上に足跡をつけるのは何かはばかられるような気持を時の蜀人も抱いていたにちがいない。
要するに、彼の持した所は、その生活までが、いわゆる八門遁甲であって、どこにも隙がなかった。つまり凡人を安息させる開放がないのである。これは確かに、孔明の一短といえるものでなかろうか。
魏、呉に比して、蜀朝に人物の少ないといわれたのも、案外、こうした所に、その素因があったかもしれない。
孔明の一短を挙げたついでに、蜀軍が遂に魏に勝って勝ち抜き得なかった敗因がどこにあったかを考えて見たい。
私は、それの一因として、劉玄徳以来、蜀軍の戦争目標として唱えて来た所の「漢朝復興」という旗幟が、果たして適当であったかどうか。また、中国全土の億民に、いわゆる大義名分として、受け容れられるに足るものであったか否かを疑わざるを得ない。
なぜならば、中国の帝立や王室の交代は、王道を理想とするものではあるが、その歴史も示す如く、常に覇道と覇道との興亡を以てくり返されているからである。
そこで漢朝というものも、後漢の光武帝(在位25~57年)が起って、前漢の朝位を簒奪(さんだつ)した王莽(おうもう。「新」を建国。在位8~25年)を討って、再び治平を布いた時代には、まだ民心にいわゆる「漢」の威徳が植えられていたものであるが、その後漢の治世も蜀帝、魏帝以降となっては、天下の信望は全く地に墜(お)ちて、民心は完全に漢朝から離れ去っていたものなのである。
劉玄徳が、初めて、その復興を叫んで起った時代は、実にその末期だった。玄徳としては、光武帝の故智に倣わんとしたものかもしれないが、結果においては、ひとたび漢朝を離れた民心は、いかに呼べど招けど――覆水(ふくすい)フタタビ盆ニ返ラズ――の観があった。
ために、玄徳があれほどな人望家でありながら、容易にその大を成さず、悪戦苦闘のみつづけていたのも、帰するところ、部分的な民心はつなぎ得ても、天下は依然、漢朝の復興を心から歓迎していなかったに依るものであろう。
同時に、劉備の死後、その大義名分を、先帝の遺業として承(う)け継いできた孔明にも、禍因はそのまま及んでいたわけである。彼の理想のついに不成功に終った根本の原因も、蜀の人材的不振も、みなこれに由来するものと観てもさしつかえあるまい。
(06)諸葛亮の子孫や一族の活躍
「三国志演義」のうちの本文にしばしば見るところの――身に鶴氅(かくしょう)を着、綸巾(りんきん)をいただき、手に白羽扇を持つ――という彼の風采の描写は、いかにも神韻のある詩的文字だが、これを平易にいえば、(いつも葛〈きびら〉織りの帽をかぶり、白木綿か白麻の着物をまとい、素木〈しらき〉の輿〈こし〉、或いは四輪の車に乗って押されてあるいた)という彼の簡易生活の一面を、それに依ってうかがうことができるのである。
彼には初め子がなかった。で、兄の諸葛瑾(しょかつきん)の次男、喬(きょう)をもらって養子としていた。瑾は呉の重臣なので当然、その主孫権のゆるしを得たうえで蜀の弟へ送ったものであろう。
この喬は、叔父や父のよい所にも似て、将来を嘱望され、蜀の附馬都尉(ふばとい)に役付(やくづき)して、時には養父孔明に従って、出征したこともあるらしいが、惜しいかな、25で病死した。
孔明の家庭はまたしばらく寂寥(せきりょう)だったが、彼が45歳の時、初めて実子の瞻(せん)をもうけた。晩年の初子だけに、彼がどんなによろこんだかは想像に余りあるものがある。
かつ、瞻はたいへん才童であったとみえ、建興12年、呉にある兄の瑾に宛てて送っている彼の書簡にもこう見える。
=瞻今スデニ八歳、聡慧(そうけい)愛スベシ、タダソノ早成、恐ラクハ重器(ちょうき)タラザルヲ嫌ウノミ。
彼は8歳の児(こ)を見るにさえ、国家的見地からこれを観ていた。
その年、孔明は征地に歿したのである。遺愛の文房のうちから、「子を誡(いまし)むる書」というのが出てきた。
★諸葛亮は蜀の建興12(234)年8月、魏の司馬懿(しばい)と対峙(たいじ)したまま、渭浜(いひん。渭水〈いすい〉の岸辺)で陣没した。
その後、瞻は17の時蜀の皇女と結婚、翰林中郎将(かんりんちゅうろうしょう)に任ぜられた。
父の遺徳は、みな瞻の上に幸いして、善政があるとみな瞻のなしたようにいわれた。しかし、その名声はすこし溢美(いつび)に過ぎていたようである。
孔明が生前すでに観ていたように、(この子、おそらくは大器にあらず)という所がやはり瞻の実質であったようである。
蜀亡(ほろ)ぶの年、瞻は、37で戦死した。
★諸葛瞻は蜀の炎興(えんこう)元(263)年冬、魏の鄧艾(とうがい)と緜竹県(めんちくけん)で戦って死んだ。
子の尚(しょう)もまだ16、7歳であったが、長駆、魏軍のなかに突き入って奮戦の末、果敢な死をとげた。
決して、国家の大器ではなかったにせよ、孔明のあとは、その子、その孫も、共に国難に殉じて、みな父祖の名を辱めなかった。
尚の下にも、なお小さい弟があったといわれるが、この人の伝はわからない。また、孔明には他の母系もあったという説もあるが、それも真偽はさだかでない。
★『三国志』(蜀書・諸葛亮伝)に付された「諸葛瞻伝」には、諸葛瞻の長男として諸葛尚、次男として諸葛京(しょかつけい)の名が見えている。
孔明の家系は、こうしてもとの草裡(そうり)に隠れてしまったが、この諸葛氏なる一門からは、この三国分立時代に、3人の将相を同族から出していたのみでなく、その各ゝが、蜀、魏、呉と別れていたのは一奇観であった。
すなわち、孔明は蜀に、兄の瑾は呉に、従兄弟の誕(たん)は魏に。そして誕のことは余りいわれていないが、一書に、――諸葛氏ノ兄瑾、弟誕、並ビテ令名アリ。各ゝ一国ニ在ルガ故(ゆえ)、人以テ曰ウ、蜀ハ龍ヲ得タリ、呉ハ虎ヲ得タリ、而シテ、魏ハソノ狗(イヌ)を得タリト。
これは少し酷評のようである。誕は分家の子で早くから魏に仕え一方の将をしていたが、孔明と瑾の間のように親交がなかったので、三国志中にもあまり活躍していないだけにとどまるのだ。
ただ、後に魏を取った司馬晋(しばしん。司馬氏の晋〈西晋〉)に叛(そむ)いて敗れ去ったため、晋人の筆に悪く書かれてしまったものとみえる。
誕についても、語ることは多いが、余りに横道にそれるから略す。孔明死後の蜀のことは後に略説する。
しかし彼の死後なお30年間も蜀が他国に侵されなかったのはひとえに彼の遺法余徳が、死後もなお国を守っていたためであったといっても過言ではあるまい。
(07)諸葛菜
頼山陽(らいさんよう)の題詩「仲達、武侯の営址(えいし)を観る図に題す」に、山陽はこういっている。
――公論ハ敵讐(しゅう)ヨリ出(い)ヅルニ如カズ、と。
至言である。山陽は、仲達が蜀軍退却の跡に立って、「彼はまさに天下の奇才だ」と、激賞したと伝えられている、そのことばをさしていったのである。
これ以上、孔明を論じ、孔明を是々非々してみる必要はないじゃないか――と世の理論好きに一句止(とど)めをさしたものといえよう。
だが、ここでもう一言、私見をゆるしてもらえるなら、私はやはりこう云いたい。仲達は天下の奇才だ、といったが、私は、偉大なる平凡人と称(たた)えたいのである。
孔明ほど正直な人は少ない。律義実直である。決して、孔子孟子のような聖賢の円満人でもなければ、奇矯なる快男児でもない。ただその平凡が世に多い平凡とちがって非常に大きいのである。
彼が、軍を移駐して、ある地点からある地点へ移動すると、かならず兵舎の構築とともに、附近の空閑地に蕪(蔓菁ともよぶ)の種を蒔(ま)かせたということだ。
この蕪は、春夏秋冬、いつでも成育するし、土壌をえらばない特質もある。そしてその根から茎や葉まで生でも煮ても喰(た)べられるという利便があるので、兵の軍糧副食物としては絶好の物だったらしい。
こういう細かい点にも気のつくような人は、いわゆる豪快英偉な人物の頭脳では求められないところであろう。正直律義な人にして初めて思いいたる所である。
とかく青い物の栄養に欠けがちな陣中食に、この蕪はずいぶん大きな戦力となったにちがいない。戦陣を進める場合も、そのまま、捨てて行って惜し気もないし、また次の大地ですぐ採取することができる。
で、この蔓菁の播植(はしょく。種まき)は、諸所の地方民の日常食にも分布されて、今も蜀の江陵(こうりょう)地方の民衆のあいだでは、この蕪のことを「諸葛菜」とよんで愛食されているという。
もうひとつ、おもしろいと思われる話に、こんなのがある。
蜀が魏に亡ぼされ、後また、その魏を征して桓温(かんおん)が成都(せいと)に入った時代のことである。
その頃、まだ100余歳の高齢を保って、劉禅帝時代の世の中を知っていた一老翁があった。
桓温は、老翁をよんで、「おまえは、100余歳になるというが、そんな齢(とし)なら、諸葛孔明が生きていた頃を知っているわけだ。あの人を見たことがあるか」と、たずねた。
老翁は、誇るが如く答えた。
「はい、はい。ありますとも、わたくしがまだ若年の小吏の頃でしたが、よく覚えておりまする」
「そうか。では問うが、孔明というのは、いったいどんなふうな人だったな」
「さあ? ……」
訊(き)かれると、老翁は困ったような顔をしているので、桓温が、同時代から現在までの英傑や偉人の名をいろいろ持ち出して、「たとえば……誰みたいの人物か。誰と比較したら似ていると思うか」と、かさねて問うた。
すると、老翁は、「わたくしの覚えている諸葛丞相(じょうしょう)は、べつだん誰ともちがった所はございません。けれども今、あなた様のいらっしゃる左右に見える大将方のように、そんなにお偉くは見えませんでした。ただ、丞相がおなくなりになってから後は、何となく、あんなお方はもうこの世にはいない気がするだけでございます」と、いったということである。
仲達の言もよく孔明を賞したものであろうし、山陽の一詩も至言にはちがいないが、私は何となくこの老翁のことばの中にかえってありのままな孔明の姿があるような気がするのである。
丞相ノ祠堂(しどう) 何(いず)レノ処(ところ)ニカ尋ネン
錦管(きんかん。錦官)城外 柏森々(はくしんしん)
階ニ映ズ 碧草(へきそう)自(おのずか)ラ春色(しゅんしょく)
葉(よう)ヲ隔ツ黄鸝(こうり) 空(むな)シク好音(こういん)
三顧頻繁ナリ 天下ノ計(はかりごと)
両朝開済(かいさい)ス 老臣ノ心
師(いくさ)ヲ出シテ未(いま)ダ捷(か)タズ 身先(まず)死ス
長ク英雄ヲシテ 涙襟ニ満(みた)シム
孔明を頌(しょう)した後人の詩は多いがこれは代表的な杜子美(としび)の一詩である。
沔陽(べんよう)の廟前に後主劉禅が植えたという柏(カシワ)の木が、唐時代までなお繁茂していたのを見て、杜子美がそれを題して詠(うた)ったものだといわれている。
管理人「かぶらがわ」より
吉川先生の諸葛亮への思い入れが、大いに語られた篇外余録でした。吉川『三国志』は、「曹操に始まり諸葛亮に終わる」という壮大な歴史物語なのですね。
しかし、ここまで諸葛亮を粉骨砕身させたものは、ホントのところ、いったい何だったのでしょう? 劉備との絆だけでは、とうてい説明しきれないものを感じます。

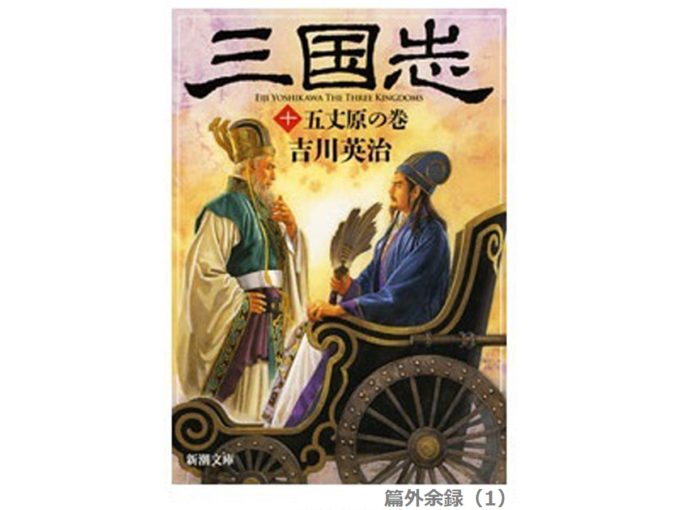


























コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます